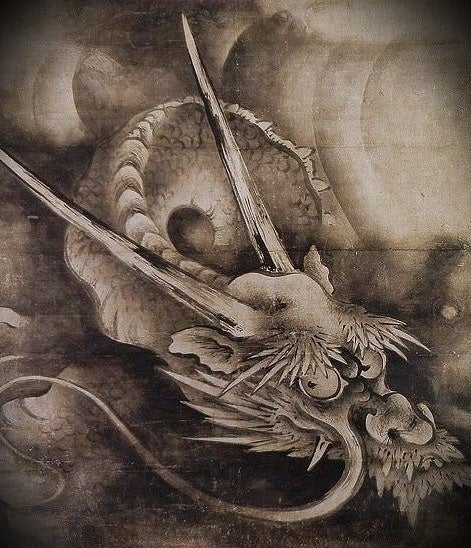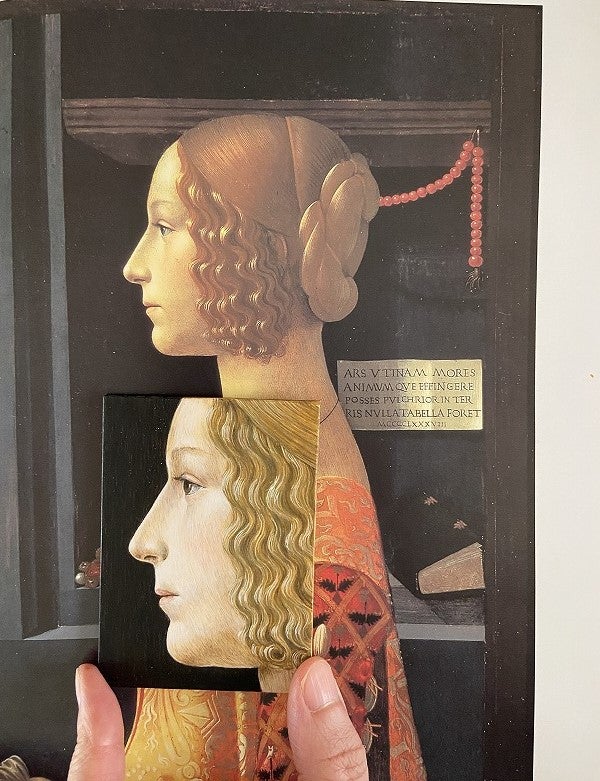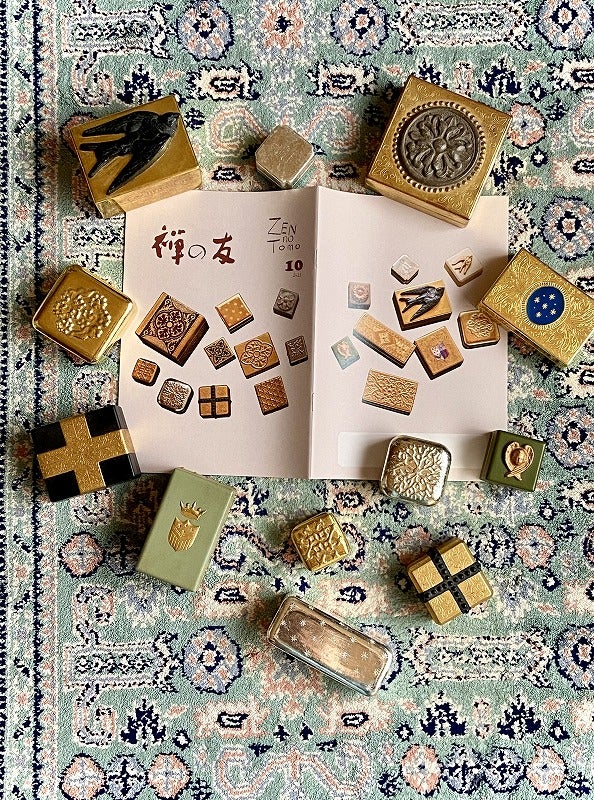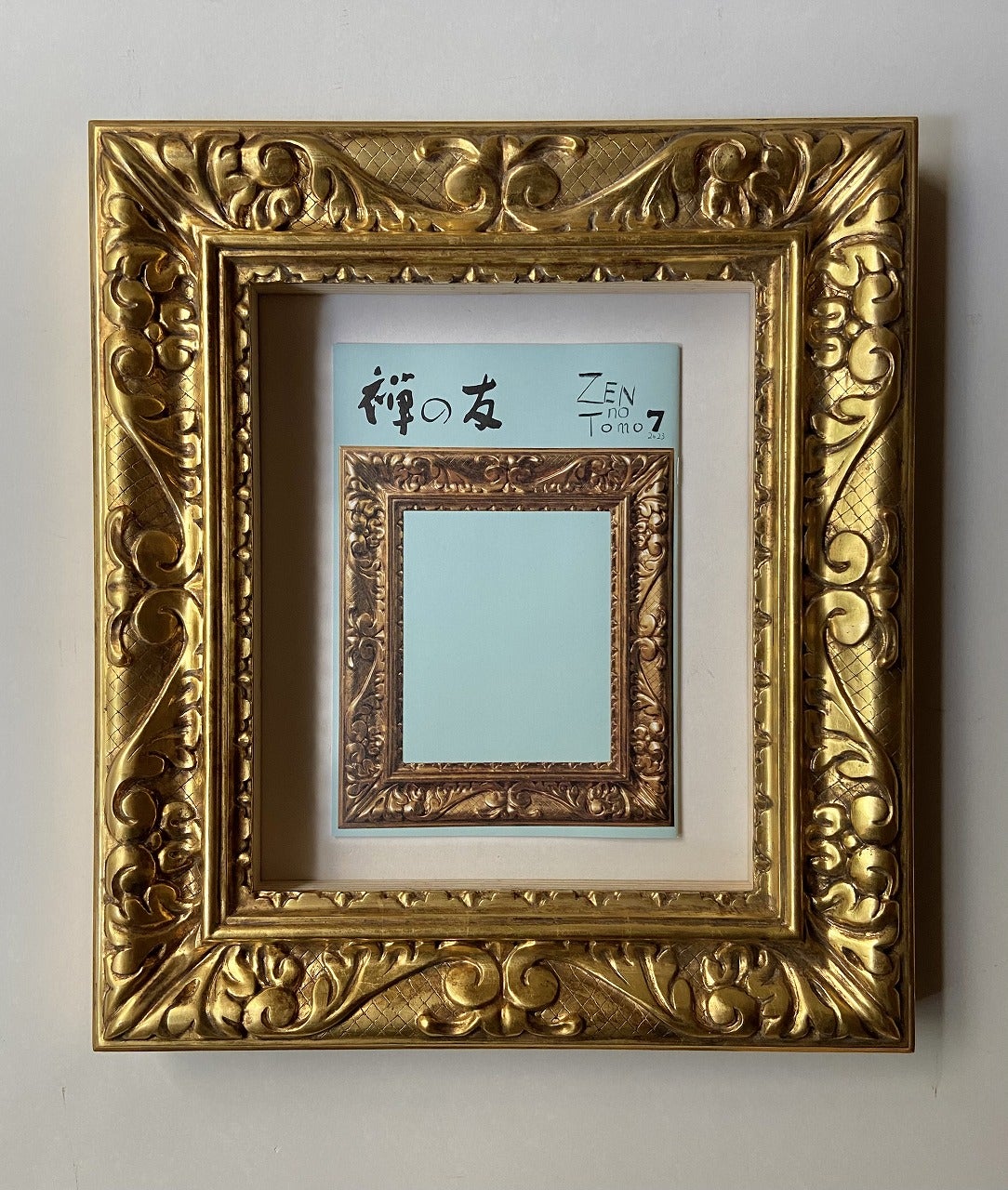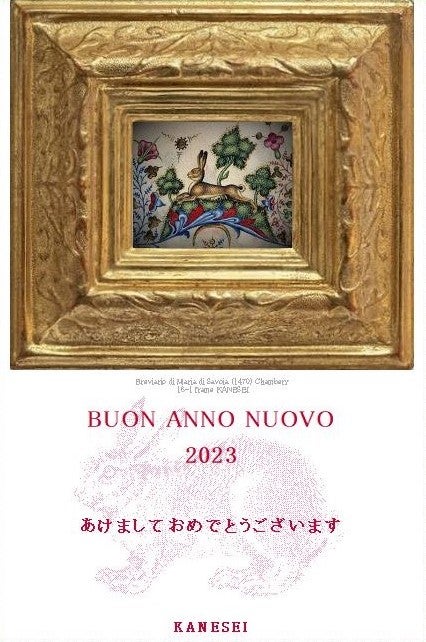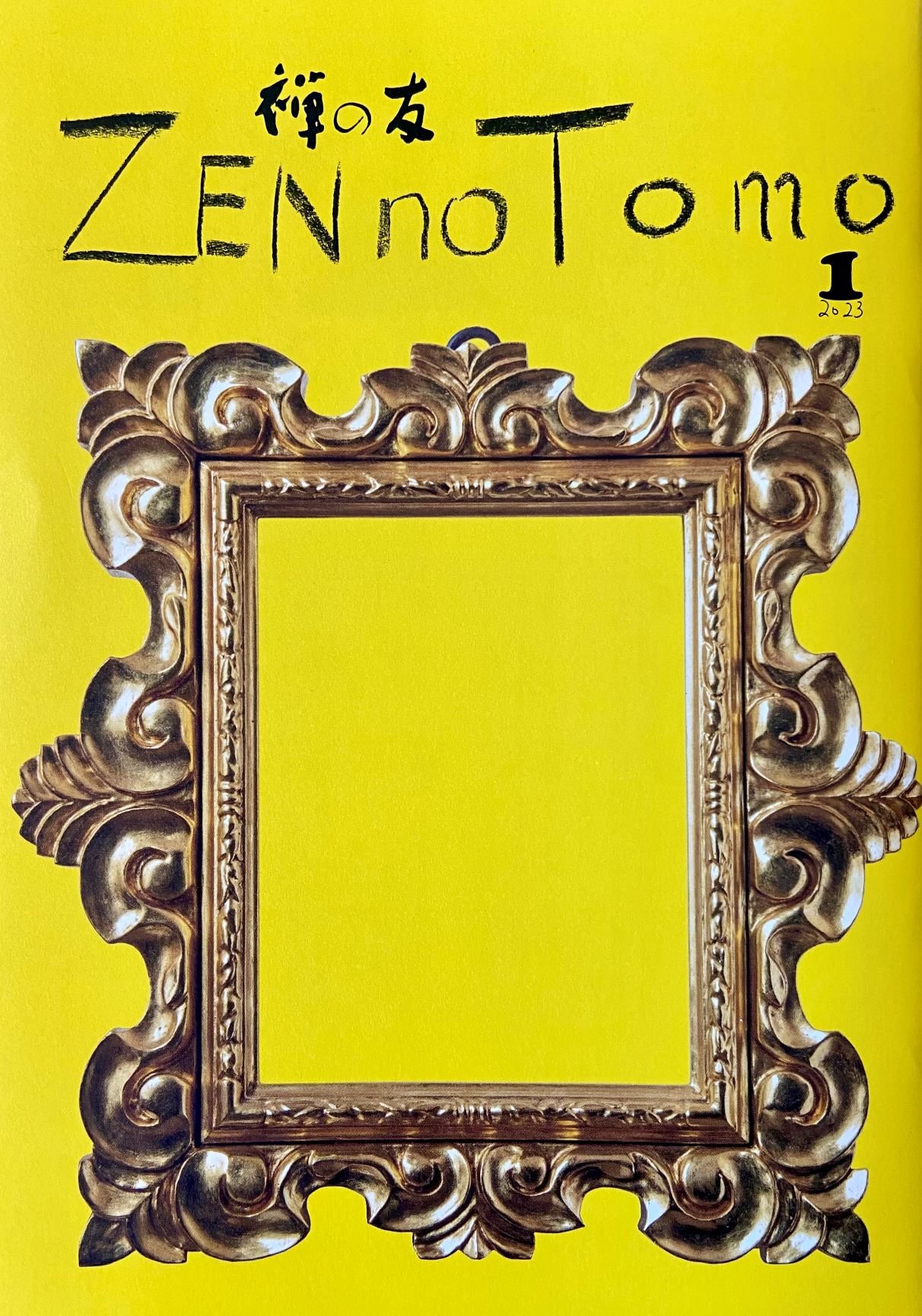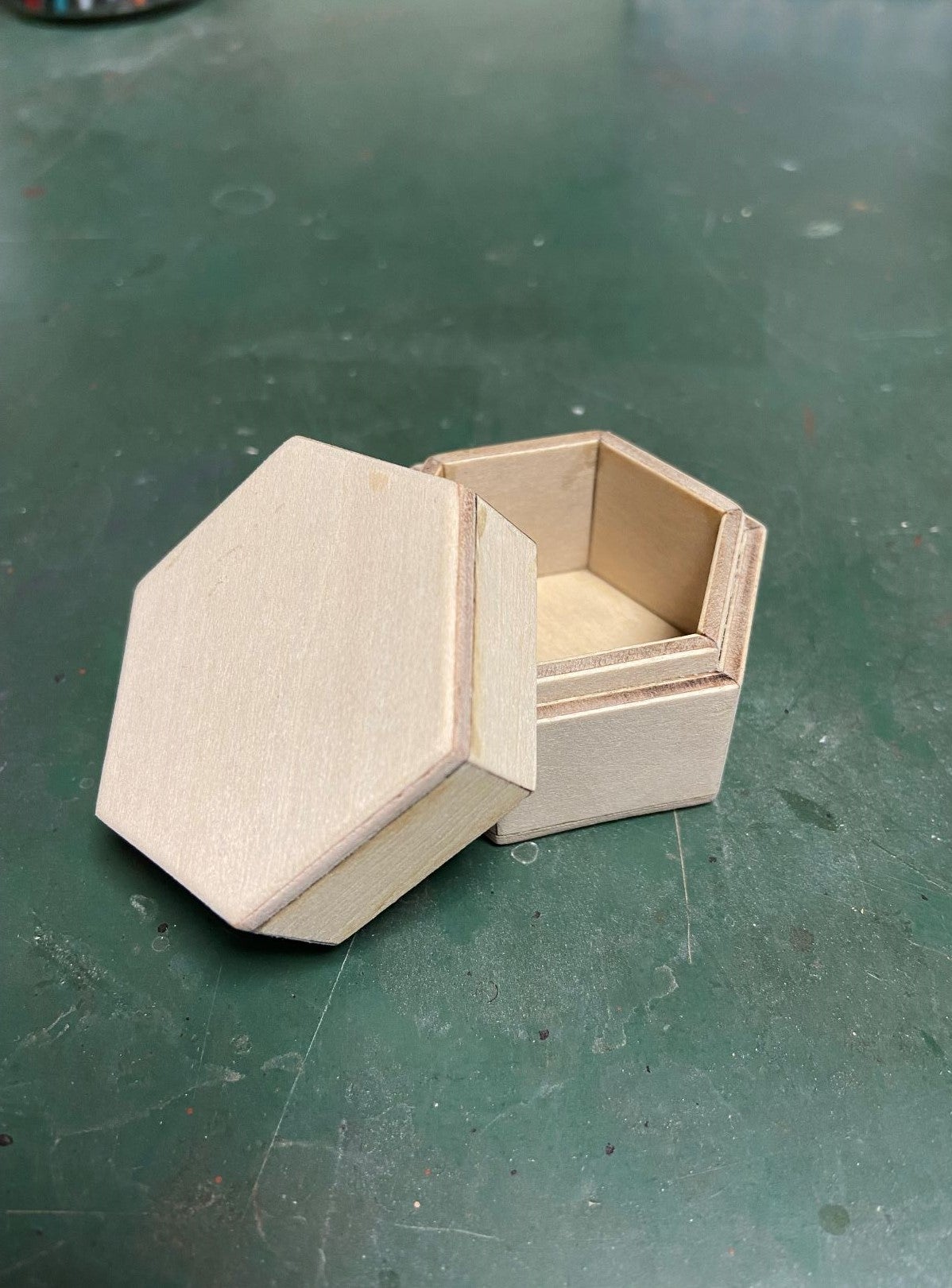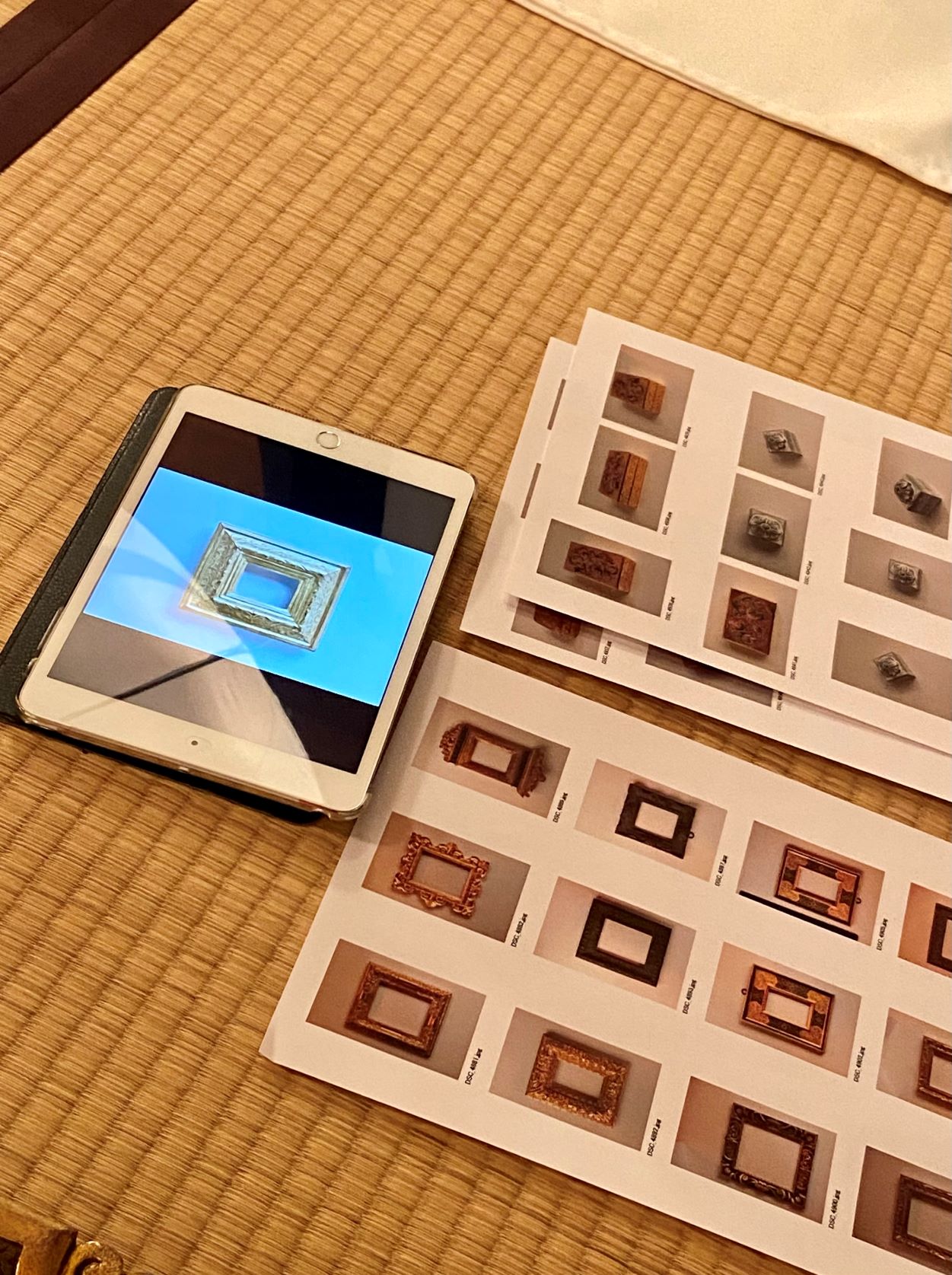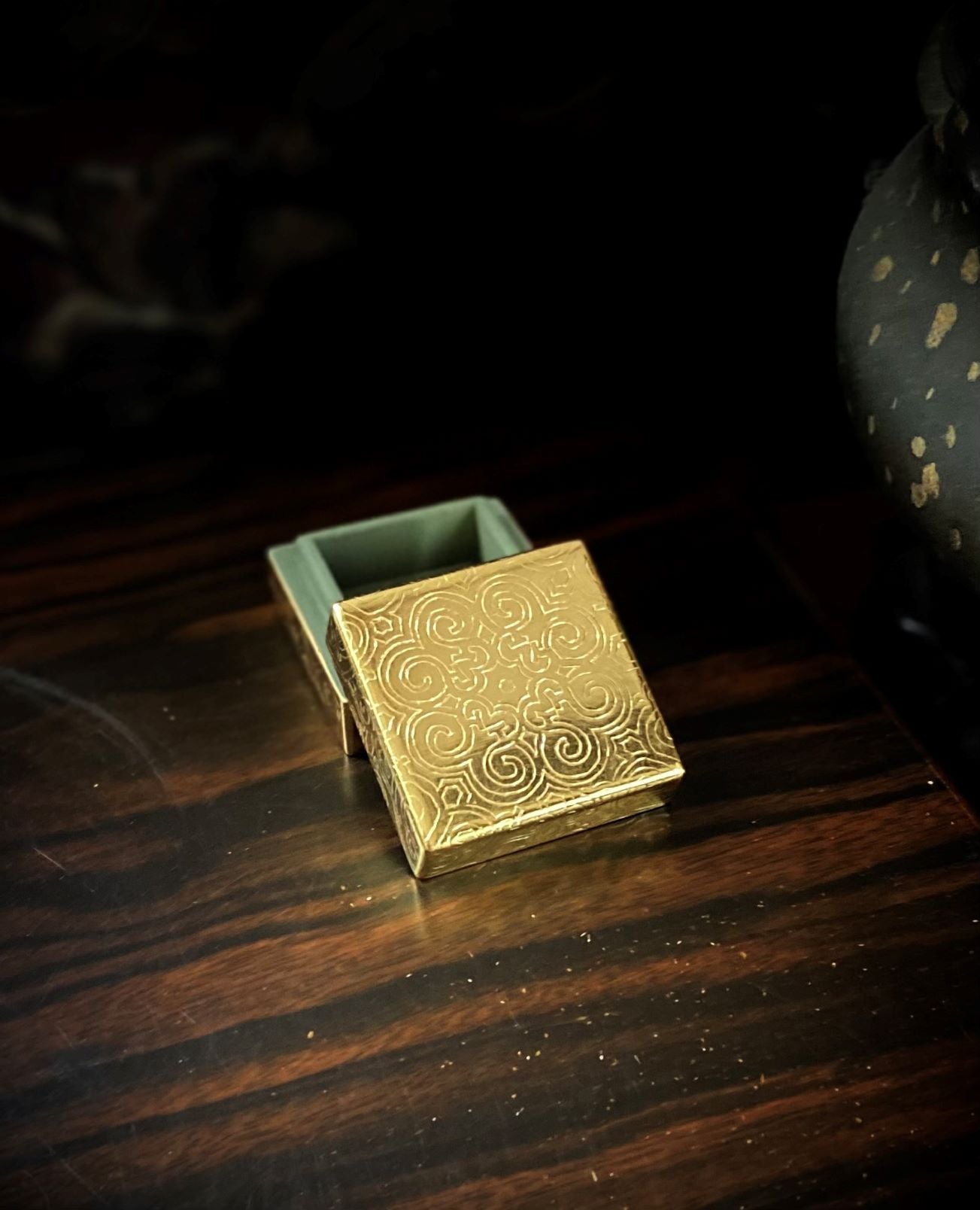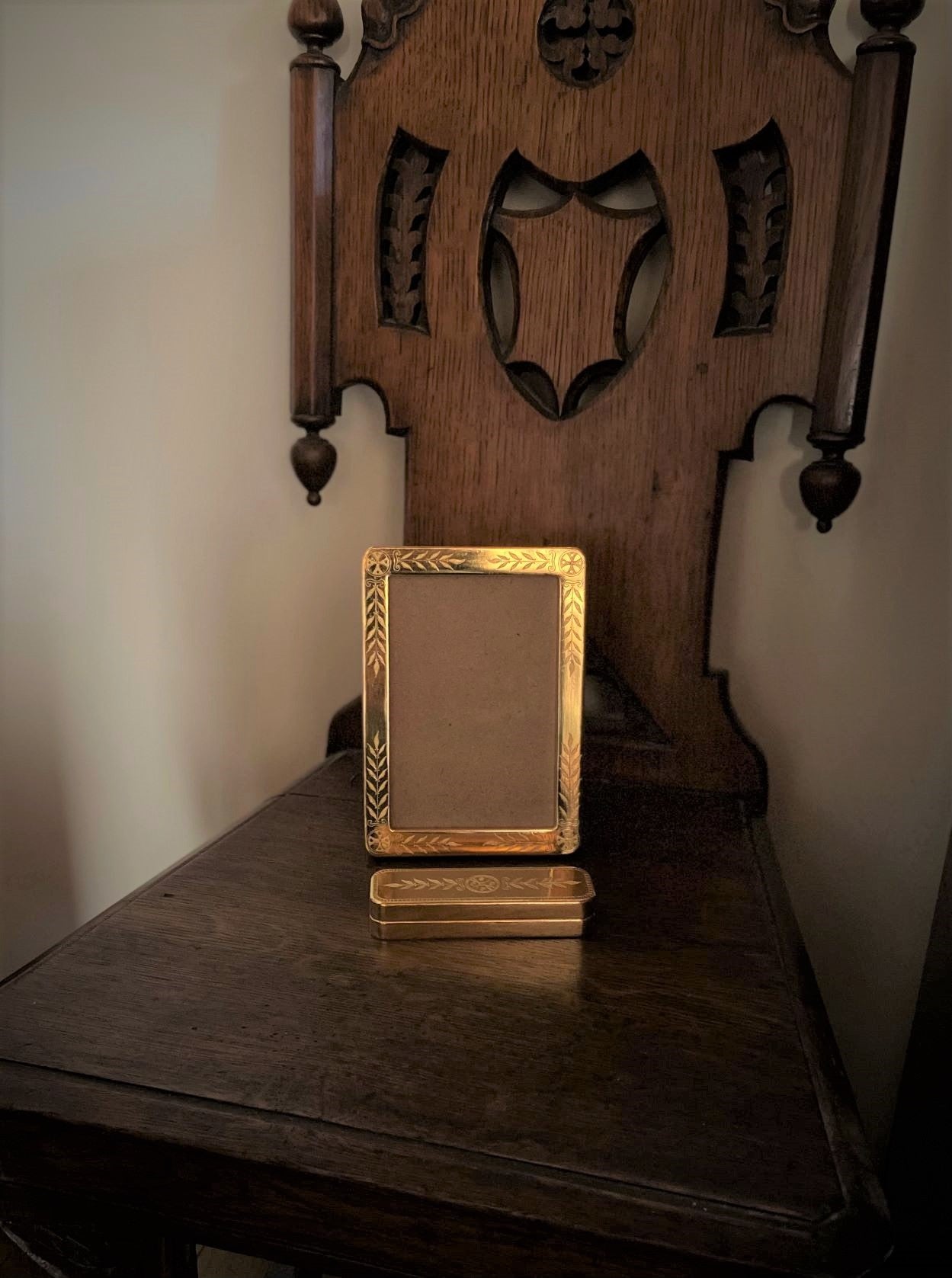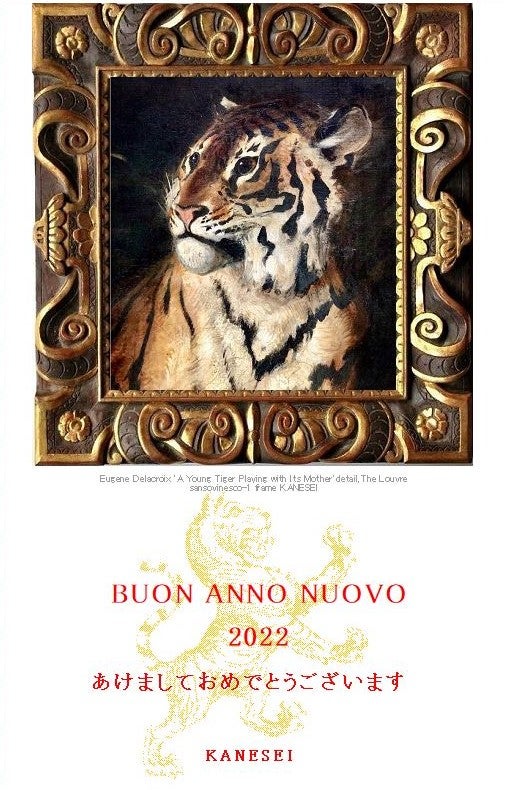diario
イタリアへ 2月17日
2月16日から1か月間、イタリアへ行って参ります。
ここ数年は毎年この時期にイタリアへ行き、
会いたかった人々、見たかったもの、行きたかった場所
食べたかったもの等々、欲望を満たすことに勤しんでいます。
この時間があるから制作が出来ている・・・と思っています。
アウトプットして中身が空っぽ状態の今、
イタリアでじゃんじゃんとインプットする所存です。
毎度のことではあるのですが
イタリアへの出発間近になりますと何故か
「行きたくない症候群」を発病します。
自分で行くと決めて準備したくせに。
だれも行けと言っていないのに。
先取りホームシック。
でもまぁ当然ながら、着いてしまえば
楽しく嬉しく過ごすのです。
それが分かっているから出発できるのです・・・。
例年ですとブログを書き溜めて投稿するのですが
今年は帰国後までお休みすることにいたしました。
とは言え!
3月後半には必ず再開いたしますので、
その際には変わらぬご贔屓をお願い申し上げます。
イタリアで得たものを制作に生かす、そして皆様に見て頂けるよう。
行って参ります。
一歩進めた額縁 2月13日
何時作り始めたか記憶も定かではない「果物ぐるぐる額縁」は
昨年12月半ばに石膏をようやく磨き終え、また1か月半放置。
作業部屋で埃を被りながら、じっとわたしを見つめてくる額縁・・・
(もちろんわたしの妄想ですが)
もうその視線に耐えられない!と箔貼りを決行しました。
やるべき作業は他にあります。分かっているけれど。
ここからコッテリ古典技法の話になります。
▲石膏下地で放置された姿。無言でわたしを責め立てる。
赤色ボーロを全体に塗りました。
彫刻で凹凸の深い場合は黄色ボーロを塗ってから
凸に赤ボーロがセオリーですが、今回は赤のみです。
▲すこし厚めに塗りました。
普段は4号箔を使っていますが
思い立って秘蔵の3号箔を貼ることに。
ここ最近の金相場の上がり様には仰け反るばかり
4号箔と3号箔の価格の差も結構なものでして悩ましい。
ですが、しばらく4号以外の金箔を扱っておらず
もしかしたら近々に1号箔というもう少し純金に近い箔
(23.7カラット等)を使う機会があるかもしれず、
気休め程度の練習も兼ねて3号箔をば。
ちなみに1号箔のさらに上に純金箔24カラットもあります。
1号箔と3号箔は2%程度しか金の量は変わりませんが
3号より1号のほうが赤味が強くとても柔らかい。
作業の感覚も変わるのです。
さて、そんな訳で3号箔を引っ張り出して貼ります。
貼るというか、金箔で包む感じでしょうか。
▲一番高い場所から貼り始める。
▲3時間かかってここまで(遅い)。側面は翌日に貼り終えました。
作業部屋か寒いので、メノウ磨きは居間の床暖に座ってガサゴソ。
さぁ、磨き終わりです。
▲金の反射でなにがなんだか。
今回は中央の彫刻無し部分と、ねじねじリボンの内側は
磨かずに艶消しにします。すこし変化を付けてみる。
さてさて、残すは古色付けを残すのみ。
ここからまたしばらく時間が空きそうです・・・。
天の采配か? 2月10日
昨年から作り始めた楕円形の額縁は作るのも楽しく、
お客様からも「楕円の額縁を探していたけれど
中々気に入ったものが見つからなかった。
やっと手に入って嬉しい。」とのお言葉を頂戴して
わたしも喜んでおります。
問題は木地の入手が難しいこと。
楕円ってバランスが難しい、需要が少ない、
材料に無駄が多く出る等理由はあるのです。
昨年使っていた木地は友人がフィレンツェで手に入れてくれたものですから
もったいなくて使えない&ご注文を受けるのも難しい
(サイズが選べない)という問題が。
▲秘蔵の楕円木地。残り僅か・・・
そして一念発起(大げさ)しまして様々探しましたところ
ようやく楕円形額縁の木地を販売するイタリアの会社を
オンラインで見つけました。やったー!
おまけに裏板とガラスもあるのです!これまたバンザーイ!
楕円型額縁制作の課題の一つがガラスでした。
普段はアクリルガラスを自分でカットしますが
楕円に切る苦労と言ったらもう。
もちろん工具があれば簡単ですが
わたしの場合は手切りですので
小さなアクリル板を楕円に切り出すだけで1時間はかかってしまう!
ひとまず最小サイズから30センチ弱まで7種類を注文しました。
Paypal決済ができて日本までの発送も可。
今回はイタリア在住の友人宅へ発送してもらいました。
発注から3日後には到着!素晴らしい・・・!
訪伊時に受け取って持ち帰る予定です。
日本へ配送をお願いした場合は・・・もしかしたら
購入価格より送料が高くなる可能性もありますが
まぁ、友人と共同で買うとか
大量にストックしてじゃんじゃん作るとか、また改めて考えます。
最近やる気がないなどとブツクサ言っていたから
天が「じゃぁこれでどうだ」とばかりに
楕円木地をくれたのな、つまり
「怠けてないでどんどん作れ」という天の采配かな、と
ふと思ったりして。
それでどうするのぉぉ~ 2月03日
先日、友人に差し上げるお菓子を選ぼうとデパ地下に参りました。
「はて和か洋か、甘味か塩味か・・・」と
楽しく迷いながら歩いておりましたら
ふと目に留まってしまったのでした。
ラデュレの小箱が・・・!
▲蓋と身の絵柄がずれていて恐縮です・・・
な、なんちゅーかわいい箱じゃろか。
友人用に、とか言いつつちゃっかり自分用にも買ってしまいました。
この際、友人の好みかどうかなど飛んで行ってしまいました。
恐るべしラデュレの箱。
▲サイズは手のひらに乗るくらい。
中には金平糖。3種類あって、これはライチ味でした。
金平糖としては珍しい味ですね。
そしてとても美味しかったのでした。
ちなみに他のふたつの箱は黄色とピンク。
味は覚えていません・・・なにせメインは箱なのであります。
▲うっすら透明感のある艶消し純白の金平糖が、すこし入っていました。
帰宅後に家族に鼻息荒く「見て!かわいい!!」と見せびらかしたところ
「・・・箱ぉ?・・・それでどうするのぉぉ・・・?」ですって。
暗に「また箱⁉」と言いたげな。
そうです、美しい空箱がいくつもいくつも溜まっている。
その上で自分でも小箱を作っちゃうのですからね、
我が家にいったいいくつの空箱がある事やら。
どうするのぉぉ?って
そうですねぇ、どうもしないですよぉぉぉ・・・眺めて終わり。
手元にあることの喜び、でしょうか。
毎度痛いところを突く家族。
でも「おいしい金平糖だねぇぇ」と言い、
翌朝にはしっかり保存容器に入れてくれていたので
(わたしは箱が手に入ったら中身は忘れてしまうので)
ありがたや!と思っております。
ラデュレとデメルの箱・・・ううう・・・♡
ブローチとわたし 1月30日
昨日、ついに待ちに待ったものが届きました。
坂田あづみさんの作品、ブローチです。
坂田さんとはお互いの個展に行ったり
何度か美味しいお酒をご一緒したり、
とても楽しくお付き合いさせて頂いています。
ある日、彼女の胸にこの紋章型のブローチがついていて
あまりの欲しさにその場で「作ってほしい!」とお願いしました。
「これ、ずいぶん前に作ったんだけど
この形は作るのが大変だから最近は作っていなくて・・・」
と仰るところ、無理にお願いしてしまいました。
わたしは小箱にも紋章模様を入れるのが好き、
そして黒と金のコントラストが好き、
なのでこのブローチはわたしの心の中心目掛けて刺さったのでした。
▲微妙にピンボケ・・・
このデザインは「EX VOTO」
本来は宗教的な意味合いのものですが
勝手に「熱く燃える志」と自己流に解釈しています。
当然ですがすべて手刺繍、金属の糸
ビーズが使われて、かなり立体的です。
この刺繍技法はヨーロッパで古くからあって
ゴールドワークと呼ばれるとか。
カトリックの豪華な詩祭服や軍服のモールなどのイメージでしょうか。
▲とても細かい。周囲のステッチには青も入っています・・・
ちいさなブローチからは、制作に対する
真摯な気持ちや迫力、緻密で正確な作業など
手で作ったものならではの存在感が感じられる。
坂田さんのブローチをお守りとして
身に着ける人もいるというのも頷けるのです。
(坂田さんご本人はお守りのつもりはないと思いますが・・・。)
黒いコートの襟につけたら絶対かわいいぞ!とニヤニヤしています。
坂田さんもわたしも、ひたすらひとりでせっせと物を作る日々
このブローチはわたしのお守りと言うより
自分への応援の気持ちが強いかもしれません。
お重小箱 1月29日
二段重ね、お重小箱が完成しました。
一昨年から「ちょっと作っては休み」を続きて来たのですが
ようやく完成です。
この小箱、いつもお世話になっている箱義桐箱店さんで
乳歯入れとして販売されている二段重ねの小箱です。
当初はフタに可愛らしい歯のイラストが印刷されていたのですが
角を面取りして石膏を塗って(イラストを隠して)
本金箔仕上げにしました。
点々打ちで星をちりばめてあります。
上下二段、小さな升目が入っています。
上の段の升目をつなげて、少し広くしました。
なにせ乳歯入れと言うくらいで
一枡のサイズが1.5センチと小さいのですが、
小ぶりのピアスが一組入ります。
広げた部分にはネックレスやブレスレットのチェーンがぴったり。
一段目を裏返したところ、裏側に星を純金泥で描きました。
ひっそりと輝くひとつ星です。
アクセサリー以外の用途はなんだろう・・・
と考えますけれど、どうでしょう。
桜貝とか、植物の種とか、あとは・・・
ジュエリーに仕立てる前の宝石とか。
きっとわたしが思いもよらない使い方をしてくださる方が
いらっしゃるのではないかな、と期待しつつ。
焦らずに、と思う。 1月27日
昨年の2024年、いったいいくつの小箱を作ったのかと考えてみたら
おそらく100個前後作ったのでした。
我ながら飽きもせず良く作ったものです。
おかげ様でいくつかのグループ展に出品させていただき
「秘密の小箱」展も無事開催出来て、
必死で作った努力は報われました。
・・・ですけれど、と言いますか、だからと言いましょうか、
現在気持ちがすっからかんになっております。
▲「ほげーーー」・・・とは言っていないんだろうけれど。
知人の作家(かなりの売れっ子)に
「どうにもやる気が出ないときはどうする?」と聞きましたら
「制作じゃなくて全く違うことをする。
展示の準備とか、ギャラリーへのレコメンドを書くとか
することは限りなくあるでしょ。」とのこと。
そうですか、そうですよね、仰る通りでございます。
こうしてコンスタントにハイレベルの作品を
作り続けるメンタルを整えながら、他の仕事もきちんとこなす
だから信用を得て作品も売れてゆくんだな、と納得しました。
と言う訳で、わたしも今できることをする
・・・いや、せねばらならぬことをする。
創作に使わない部分で地道に進めておく時間だと割り切っております。
作るばっかりが制作じゃない。
諸々の準備やインプットがあるから作れるんだ、と
自分に話して聞かせている今日この頃です。焦りつつ。
「あわわ」が早い2025 1月23日
毎年、年度末と言えば確定申告・・・
そして「あわあわ」するのが常ですが
今年2025年はこの「あわあわ」を早めに感じております。
2月からしばらくイタリアへ行く予定なのですが
確定申告提出が帰国後では間に合わず・・・
出発前に済ませねばなりません。
1月だろうが2月だろうが、例年通り期限ぎりぎりだろうと
やらねばならぬ事に変わりは無いのですから
いつしても良いのです。
でも、あの、やっぱり、あわわ・・・
▲公認会計士の友人に「領収書をお菓子の箱にでも
ぼんぼん溜めておけば良いの!後でまとめれば終わるんだから
それくらいできるでしょ!」と言われ
それ以来箱に溜め込む癖がつき・・・
毎年思うのは、月々できちんと集計しておけば
最後にまとめるだけで良いのだから
今年こそきちんとしましょう!なのですが
結局同じことを毎年繰り返しております。
2025年の抱負が思いつかないなんて
ノンキなことを申しましたが、ここでひとつ
「2025年は毎月収支をまとめる」という
具体的な目標を今更ながら持つことにいたします、ハイ。
そろそろ成長したいと自分に期待します・・・!
なんか、こう・・・自己申告じゃなくて
自動で計算して徴収してくれると助かるんだけど・・・もごもご。
なんて、そうじゃないんですよね色々と、きっと。
小さくてドキドキする 1月20日
昨年秋に神楽坂のギャラリー「ラ・ロンダジル」の
グループ展「ロンダの妄想茶道具小品展」に
小箱で参加しましたとき
同時開催で中島完さんの茶道具展も開催されていました。
すべて茶箱用に作られた道具で
それはそれは小さくて美しい道具ばかりが並んでいたのでした。
茶箱は茶道具の一種で、道具一式を納めて
持ち運びできるようにしたものです。
いわばピクニック用お茶道具セットでして
すべて小さめに作ってあります。
初日にギャラリーにお邪魔して
小箱を見に来てくださった方や
一緒に出品されている作家さんとお話したりと
楽しく過ごしていたのですが、
実は心の三分の一は中島完さんコーナーに行ったままでした。
あまりに可愛いのですもの!
そうして鼻息荒くひとつ手に入れましたのは
小さな薄茶器でございます。
同じようなサイズの茶器が
それこそ100個は並んでいたでしょうか
沢山ありすぎて選びきれないのですが
「形と色」選抜、その中から「これぞ!」と選びました。
ああ、なんて小さくて美しいの!
その後に男性の友人に見せびらかしたところ
「・・・ちっさ!!」と叫んで終わりました。
そうですよ、小さいよ、この小ささが良いのよ。
▲蓋はつるっとツヤがあり、本体はしっとりと艶消し
美しいとため息が出ますが、それが小さいと
そこにドキドキが加わる気がします。
小さいだけじゃダメ。
美しくて小さいからドキドキする。
この薄茶器を眺めながら、わたしも
「小さくて美しい」箱を作る気持ちを養います。
美味しいニオイは困ります 1月16日
オンラインショップを始めてから
おかげ様でぽつぽつとご購入いただいています。
ありがとうございます。
ご購入いただいた小箱や額縁は
宅急便会社の指定の箱に入れて発送するシステムでして
コンビニで指定の箱を購入するわけですが・・・
自宅で発送準備をしようと思って箱を組み立てると
なんだかちょっと美味しそうなニオイがするのです。
ニオイのもとをたどってみたら、コンビニで買ってきた箱でした。
から揚げとかドーナツとか、油のニオイが強い。ううむ。
最近はどこのコンビニでも店内調理をしていて
いつも出来立ての美味しいスナックが食べられてきっと便利なのですが
数分入店したら服や髪にニオイが付くようです。
コンビニのお惣菜は美味しいですし
わたしもたまにお世話になりますけれど
小箱を発送する箱から揚げ物臭は困るのです。。。
衣類用の消臭スプレーなどを振りかけましたが
紙に染み付いた臭いはなかなかしぶとくて
どうしたものか。
コンビニで箱を買う&発送(店内で発送待機中にも
ニオイがつきそう)は諦めて
すべて宅急便の営業所にて行うか・・・
でもでもコンビニが近くて便利だし・・・
いやはや。
ギャー!と叫ぶ 1月13日
つい先日、驚くべき事実が発覚しました。
それがですね、大失敗に気付いたのでした。
昨年の「秘密の小箱」展に出した小箱のひとつに
ラテン語の格言を文字装飾として入れたのですが
これが大間違いをしでかしておりました。
純金箔に臙脂色の絵の具で模様をいれて
華やかで気に入っていたのですが
ラテン語の文章がめちゃくちゃで意味をなしていない。
▲こんな「小箱のブロマイド」まで撮ったのに!
いくら「文字は装飾、模様として入れているので
意味は二の次!」と叫んだとて、
ラテン語格言の意味を調べれば一発で間違いは明らかに。
そしてラテン語を理解する方は、きっと
想像以上に身の回りにいらっしゃるのですから。
▲フタ側面にぐるりと文字が入っています。
正面だけ正しく、3面は間違い文章・・・
ある日の夕方に間違いに気づいて
「ぎゃー!!」と叫び、家族に驚かれました。
この小箱、自分で持っているのも何だか・・・
かと言ってどうしよう。
結局、家族に「くやしい!」とブツブツ愚痴りつつ
あげてしまいました。
そうして家族はいそいそと自室に持って行ってしまったので
その日以来わたしの目に留まることも無く。
それにしても不幸中の大きな幸いは
展示会で販売しなかった(売れなかった)ことです。
もしお客様の手に渡っていたら間違いに気づかないまま
末代までの恥となるところでした・・・!
この間違い、肝に銘じることにいたします。
自戒を込めて。
小箱がパカッと開いたら 1月09日
今年2025年に、またもや「禅の友」に
掲載していただけることになりました。
2023年は表紙に額縁でしたが
今年はカラー1ページに小箱です。
そして内容は、回文!
そうです、上から読んでも下から読んでも・・・の回文です。
小箱をパカッとあけたら回文が飛び出す趣向。
玉手箱のようですね。
編集のMさんのとても楽しいアイディアから生まれた1ページです。
1月号は縁起の良い回文に、水色の豆小箱が選ばれました。
やぁやぁ、これは可愛いではありませんか・・・
母(わたし)としては娘(小箱)の
晴れ姿を見せていただけて嬉しい限りです。
毎号に回文ページがある訳でもないとの事ですが
「今月はどうだろう?」と楽しみにもなりました。
毎号最後に載る美術史のお話も楽しみのひとつ。
山下裕二先生の解説です。1月号は川端龍子のお話。
「百子図」には戦後すぐにインドから
上野動物園に寄贈された象インディラと
象の到着を喜ぶ子供たちの様子が描かれていて
胸がぎゅっとなるほど愛らしくて印象に残る作品です。
川端龍子はこんな作品も描いたのですね、初めて見ました。
「禅の友」は1冊80円、定期購読で
毎号お手元まで届きます。
詳しくは下記のページからぜひどうぞ。
こころの贈り物 1月06日
年末に友人がインスタグラムに
お正月準備の様子を投稿していました。
しめ縄飾りも鏡餅も手作りで、日本のお正月の
美しい姿が垣間見られるのでした。
その中でこの友人が豆餅を作っていたのです。
黒豆がギッシリ入って大きくて、それはそれは美味しそうで・・・
つい「美味しそう♡」と一言送ったら
数日後には蜜柑とともに豆餅を送ってくれました。
▲巨大な蜜柑と大きな豆餅スライス!
箱を開けた傍からすぐさま蜜柑を食べちゃう!
お礼の連絡もする前に・・・いかん。
でも外の空気で冷たく冷やされた蜜柑は、ひときわ甘くて瑞々しい。
じゅわ~っと幸せが広がりました。
巨大な蜜柑をひとつ、お仏壇に供えて祖父母達にもお知らせをして
お昼ごはんのメインは豆餅ですよ。
そろそろ飽きたお節の残りの海老やかまぼこ、酢蓮
そしてお雑煮の残り(つまりお味噌汁)しかない食卓が
豆餅の迫力で輝きます。
パクっとひとかじり。
豆の歯ごたえが気持ち良い。
お餅も市販のものより濃いというか、ニッチリと詰まって重々しくて
安易にビョンビョンと伸びたりしません。
この美味しさって説明するのが難しい・・・
水っぽくないお餅ってこんなに美味しいんだ。
もくもくともぐもぐ、大きなお餅を頂いたのでした。
お礼の連絡をする間もなく、胃袋に消えていったお餅・・・
いや、間はあったのに食い意地が勝ったわたしでした。
(食後すぐに連絡しました!)
生まれた時から東京で、祖父母の田舎がなかったわたし。
こうして「季節の手作り贈り物」が届く新鮮さと喜びを
友人からいただいています。
幸せ、ありがとうございます。
いろいろ違う2025元旦 1月02日
改めまして、あけましておめでとうございます。
いかがお過ごしでしょうか。
東京は良いお天気ですが、雪が大変な場所もある様子
お疲れが出ませんよう。
毎年毎年、手作りのお節を準備していた我が家ですが
今年はとうとう買いました。
母がふと思い立って(あきらめて、開き直って、が近い気がしますが)
郵便局へ行ったついでに注文したそうです。
なんという事でしょう・・・!バンザーイ!
これだけの品数を準備する苦労を考えたら
数万円で大晦日に届けていただけるなんて素晴らしい!
そして美味しい!!
ただ、この美しいお料理も食べてしまえばお重は空になります・・・。
自作の場合は大抵お鍋や冷蔵庫に残りがありますから
お重に詰め直せば元通りの姿になるのです。ううむ・・・
「食べたら終わり」が気になって勿体なくて
箸の進みも遠慮がちになりました。
結局、母が準備した黒豆と田作り
わたしが作った酢蓮と紅白なますばかり食べた元旦の朝でした!
慣れないことってありますよね。
ことしも父から頂いてしまったお年玉
半紙に包んで蛇の判子です。
ポチ袋も良いけれど、半紙の包みはお正月らしくて美しいです。
「かわいい~♡」とワイワイ騒いでいたら
「この包み方は昨日見た『禅の友』(曹洞宗の冊子)に
載ってたやり方だよ」とのこと。
毎号に「つつむとも」といって紙で様々な包み方を
紹介しているページがあって、とても面白いのです。
でも実践したことはありませんでした。
こんな風に自分で可愛くできるならわたしもやってみよう、フフフ・・・
ことしのお雑煮は昆布出汁に輪切りの大根、丸餅
細切りのゴボウと人参、ほうれん草、紅白生麩でございました。
亀甲の里芋もあったけれど、入れ忘れました!
毎年なんとな~~く考えている「ことしの抱負」は
どうも今回は思い浮かばず。なんでだろう。
もっとこうしたい、ああしたい、こうしなきゃ、ああしたら良いだろう・・・
そんな風に具体的に思いつかないって我ながら驚きます。
これで良いのか悪いのか不明ですけれども
その時その時でよく考えて、出来ることをする、ということに。
なんだか色々といつもと違う2025年の元旦でした。
あけましておめでとうございます 1月01日
旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
忘れていなかった 12月26日
夏の終わり、ギャラリー冬青で開催されました
写真展に使っていただいた額縁のうちのひとつ
ヴェネツィア風の金額縁を作っています。
「ゆっくりで良いですよ」のお言葉に甘えて
でも甘えすぎになって、いまごろガサゴソ作っております。
A4の変形、といったサイズ。
切って接着して、乾かしています。
接着後にさらに四隅をしっかり固定して
下ニカワを塗ってボローニャ石膏塗り。
いつもの流れです。
2024年後半は小箱ばかり作っていたので
額縁制作が新鮮に感じてしまう!こりゃいかん。
いや、いかんと言うか、なんだかそんな自分に驚いてしまうのでした。
そうして、「やっぱり額縁制作は楽しいなムフフ」
などとノンキに思う自分に安心したりして。
額縁を作りながら工程を考える時に一瞬、ほんの一瞬ですが間があって
(以前は考えなくても流れで出来ていた)すこし焦りました。
でも頭より手のほうが額縁制作を
しっかり覚えていてくれたようです。
額縁も楽しい、小箱も楽しい。それで良いではないか。
好きなものを作れるのですからね・・・。
ありがとうございました!そして 12月16日
怒涛のような11月、12月の小箱展示は
すべて無事に終えることが出来ました。
神楽坂、谷中、京都、お越しくださった皆様に
感謝申し上げます。ありがとうございました。
箱義桐箱店 谷中店での「秘密の小箱」展は今年3回目で
ようやく、なんとなく、展示などの要領が分かってきたような気がします。
でもお客様とお話するのは相変わらず緊張します。
自分で作ったものを自分で勧めることの難しさたるや・・・!
こればかりはまだ慣れませんが、練習した方がよさそうです。
堂々と爽やかに!を目指す。
京都の「梅軒画廊」さんは、今回初めて展示していただきました。
クリスマスとお正月を前にした暖かな企画の
仲間に入れて頂けて嬉しい限りです。
ちょうど「秘密の小箱」展と期間が重なっていたので
在廊が叶わずでした。残念!
展示をご一緒できた方々の作品も拝見したかったし
暮の京都散策もしたかったのでした。
日々、ものすごく遅いスピードで生きていることを実感しました。
この晩秋~初冬は3倍速で過ぎた毎日でした。
でもこれくらい人生にメリハリがある方が気持ちも良いです。
長い時間お待たせしてしまっているお客様、
考えること、するべきこと、次のこと、
ずいぶんと停滞させてしまいました。
小箱以外のことを後回しにしすぎてしまいましたので
これからまた諸々整理して進める所存です。
果物とリボンと子羊の舌の額縁 12月12日
「いったい何時から作っているんだい・・・?」
「ハイ、もう忘れてしまうほど大昔です。」
・・・という脳内会話が繰り広げられるほど
以前から続けております、名付けて「果物ぐるぐる額縁」です。
外側を果物のリース、内側にはリボンがぐるぐる巻き
端先は「変形ラムズタン (lamb’s tongue)」が取り巻くという
彫刻がぎゅうぎゅう詰まったデザインです。
記憶にはございませんが、記録をさかのぼると
今年4月27日に石膏を塗りました。
そしてどうやら彫刻は昨年秋に終えた様子。
ということは、着手は・・・一昨年かもしれません。やれやれ。
▲こうした「苦手な作業」はAtelier LAPIS の講師時間にするに限ります。
熱心な生徒さん方に囲まれていると、わたしも頑張れる気がする
・・・ような気がする。
彫刻をした額縁に石膏を塗るには様々コツがありますが
とにかく、いかに凹凸を均一の厚さに、
筆跡を残さず塗るか!・・・難しい。
凹に溜まった石膏を再度彫って(リカットして)
メリハリを戻し、丸い果物を「ふっくら艶やか」を目指して磨き・・・
うーむ、うーむ・・・
こんな感じで石膏磨きは終了。次は箔作業です。
全面金箔にするか黒と金のコンビにするか、まだ迷い中・・・
どうしよう??
100枚?200枚?それともナシもアリ?? 11月25日
いよいよ金曜日から始まります「秘密の小箱」展です。
その「秘密の小箱展」のDMを作りました。
写真は今年も浅野カズヤさんに撮って頂いたものでして
それをネットで発注するのですが。
さて、何枚作るかな・・・?
昨年は200枚作りましたが、友人に
「少ないんじゃないの?!」と言われちょっと後悔したものの
終わってみればちょうど良かった。
200枚のうち半分は郵送で様々な会社や出版社、
ギャラリーなどなど手あたり次第にお送りした(送り付けた)のでした。
会期中、お客様とおしゃべりして最後に名刺を頂いたら
大変に有名な芸術誌の方でした。
もちろん編集部にDMをお送りしていたのですが
「ああ・・・せっかく送ってくださっても
DMの類は見る機会が無くて・・・」とのお話。
この方はSNSをご覧になって個人的に来てくださったのでした。
あれだけ大きな編集部なら日々DMも大量に届くし
そりゃ目にも留まらんでしょうなぁ・・・。
友人の展覧会のお知らせなどを見ていても
「今年はDMは無し」パターンが半数近く。
と言う訳で、今年は半分、100枚だけ作りました。
その100枚が昨日とどいたのですが、これがなんと
わたしの設定ミスで写真上下に1~2mm白いラインが入っていて
(写真が小さかったみたい)、カッコ悪いったらありゃしません。
おまけに一枚一枚微妙にラインの幅や角度が違う。これいかに。
まとめて切る訳にもいかず、結局1枚1枚カッターで切りました。
不幸中の幸いは、標準紙で薄かった(ケチった)こと、
100枚だけだったこと。1時間で切り終えて、やれやれ。
微妙~~~に幅が違うDMハガキ100枚、準備が整いました。
箱義桐箱店谷中店、アトリエLAPISにて配布させていただきますので
お見かけの際にお手に取って頂けましたら幸いです。
蛇の道は蛇 2024 11月11日
先日、曹洞宗の冊子「禅の友」に掲載していただく
写真の撮影がありました。小箱とちょこっと額縁。
掲載用の写真のほかに、わたしが使って良い許可を頂いて
小箱の集合写真も撮って頂きました。
フォトグラファーは浅野カズヤさんです。
▲編集者の方と浅野さんが色々真剣に。
フォトグラファーの仕事は大荷物がつきもの。
レンズ数種類、照明も数種類、三脚やらカメラ本体や、大変です。
いつもお疲れ様です。
上の写真の四角く光っているのは照明器具で
サイズも重さもタブレット。
光量も色味(青~赤まで)自在に変えられるのです。
いやぁ、日々進化です。大きな照明はもはや必要無し。
このタブレット型照明は自室にも欲しくなりました。
床置きでも棚に置いても、何かの後ろから照らすでも
なんでも可能なのですからね!
小箱の集合写真撮影。
これらの写真は11月末からの個展「秘密の小箱」の
DMやSNSで使わせていただく予定です。
おなじセッティングで、わたしがスマホで撮ったら下の写真。
▲薄らのっぺり。
そしてプロが撮ると
▲手前の箱をひとつ交換していますが
こうなるのです・・・!
立体感も趣も陰影も、クッキリ感も全然違う。
「なんじゃこりゃー!」と叫びたくなる。
いやはや、やはり蛇の道は蛇、でしたっけ、
とにかくプロの技を目の当たりにして大騒ぎでした。
これから頂戴した沢山の写真の中から
数枚を選び出さねばなりません。
これが楽しくも難しい。でも楽しい!
皆さまに早く見て頂きたいと思っております。
ポーチがあれば安全に 11月07日
これ、なんざんしょ?
紐でぐるぐる巻き。答えは
小箱のポーチでした~!!
いや、見てすぐわかりますよね、お粗末様でした。
いま、友人で服飾デザイナーの藤井陽介さんにお願いして
小箱のポーチを計画中。
ポーチがあれば小箱を安心して持ち歩いていただけます。
試行錯誤が続いておりまだ試作で
布や紐も変更かもしれませんけれど、おおむねこんな形です。
そして藤井さんに手描きワンポイントを入れてもらって
コラボしよう!と言う計画。
▲ムフフ・・・もうぜったいカワイイ
そうは言っても時間があまりありません。
11月前半にはなんとか完成しないと!
皆様に手に取っていただける日が待ち遠しいです。
同じ気配の物たち 10月31日
先日ご紹介しました、昭和風味に加工した
キャンドルスタンドですが
オリジナルの商品に実はあと2種類が販売されています。
もう少し背が低くて上部のお皿が広いキャンドルスタンド
それからコンポート皿のような形のもの。
味を占めまして、のこる2種類も購入して同様に加工しました。
上の写真、左が前回に加工した背が高いものです。
中央がコンポート、右が低いキャンドルスタンドです。
どれもオリジナルの姿はナチュラルで爽やかな印象なのですが
▲加工前のオリジナルの姿。写真はショップよりお借りしました。
ふたつにもちょっと削ったり塗ったり磨いたり
コッテリ仕上げにしました。
コンポートには小さな箱なら3つ並ぶ感じ、そして
▲相変わらずお供え感が強い・・・
低いキャンドルスタンドには中くらいの箱が
すっかり収まるサイズです。
ピンクと金と茶色の組み合わせも可愛らしい。
古色をつけた金や黒との相性も良いようです。
なにせどれもこれも古色コッテリですので
発している気配が同じなのですね・・・。
こんな感じで今年は展示してみようと思います!
イタリアの人からコーヒーを取り上げたら 10月28日
先日、父が渡してくれた新聞の切り抜きです。
▲10月5日の日経新聞
イタリアのバールでのエスプレッソコーヒーの値段が
最大60%値上がりの恐れですって。いやはや。
世界中、もはやどこでも何もかも値上がり一方ですけれど
その原因は様々。コロナ禍後の変化、気候変動、戦争・・・
この記事によると「気候変動によってコーヒー豆の
国際的な供給が混乱」とあります。
豆が採れなくなっているのでしょうか。
日本のスーパーで買うコーヒー豆も高くなりましたよね。
イタリアの人からコーヒーを取り上げたら
もはやイタリア人では無くなってしまうかも!と思うくらい
飲む人は朝昼晩と何度も飲んでいますから
(飲まない人は全く飲まない。差が激しい。)
これは大変に切実な問題です。
▲お砂糖を入れて混ぜたところ。まだ飲んでいませんよ。
上の写真は今年2月にフィレンツェのバールで立ち飲みした時のもの。
レシートには10%の税金を含めて€1.30とあります。
日本円でおおよそ210~220円くらいです。
この「SCUDIERI」というバールは
ドゥオーモのすぐ傍にある観光客も沢山訪れるようなお店で、
住宅街に行けば€1.20とか、場所によっては€1なんてお店もあります。
仮に60%上がったとして€2.16、日本円で350円。
立ち飲みのエスプレッソだけで350円かぁ・・・。
た、高・・・もごもご・・・大変だぁ!
その後、イタリア人の友人にこの記事について聞いてみたところ
「エスプレッソ€2・・・高すぎ。
もうバールで飲まないで家だけで飲むかも。」とのこと。
(家で飲むにしても、やっぱり豆も値上げでしょうけれど。)
イタリアの人たちにとってエスプレッソは
パンと同じくらい「生きるために必要なもの」でしょうから、
値上がりは致し方ないにしてもせめて20~30%程度だったら
と思ってしまいました。どうなるんだろう。
ヴェロッキオ先生に許しを請うて 10月24日
今年もまた、この季節になりました。
暮に開催される「小さい絵」展への出品準備です。
今年はヴェロッキオ作の聖母子像から部分
天使の顔をアップで模写しました。
いつものように卵黄テンペラです。
「小さい絵」展に出しますので、絵のサイズは8.5×6センチ
名刺くらいの大きさでしょうか。
▲どうだどうだ、どうなんだ?影が強いような気がするが・・・
模写をすると毎度のことですが、止め時が分からない。
いじくり続けるとドツボにはまってどんどんずれてしまう・・・
という経験から、心身が「わぁ!もうだめだ!」と叫んだ時に筆を置く。
・・・ヴェロッキオ先生、お許し下され。
ヴェロッキオは、かのレオナルド・ダ・ヴィンチのお師匠様
そしてなんとなんと、我が額縁師匠マッシモ&パオラの
額縁店兼工房はヴェロッキオ工房の跡ということが判明しております。
そんな訳でわたくし、ヴェロッキオには勝手に親近感を持っているのです。
さて、今年の額縁は15世紀、ヴェロッキオが活躍していた時代に
フィレンツェで流行したプレッツェーモロスタイルです。
木地にボローニャ石膏、黒色はアクリルガッシュですが
金の模様は模写同様に卵黄テンペラで彩色しました。
古色をつけて擦り切れた印象に仕上げています。
▲木の形が「典型的プレッツェーモロ「」と違うけれど、模様は伝統的に。
オリジナル作品「聖母子と2人の天使」(ロンドン・ナショナルギャラリー所蔵)
には全面金箔の額縁が付けられていますが
わたしの模写はちょっと地味に仕立てました。
▲納品用に白ボール紙でカブセ箱を作ります。
ううむ、ちょっと地味すぎましたかしら・・・。
でもまぁ、金だと絵が負けそうですし(わたしの技術不足ゆえに)
まぁ良しでしょうか。
▲右下の青い部分は、マリア様の衣なのです。青空じゃないのですよ。
いままで「小さい絵」展に出して頂く模写の額縁は
絵に比べて簡単に作って(市販の額縁を使ったこともあり。)いましたが
去年からは額縁も絵と同等程度に心を込めて作ることにしました。
何枚も描いて簡単な額縁を付けていたこともありますが
1枚入魂(念か?)の方が良いのではないかしら、と
最近は思うようになりました。
ええと、まぁ何と言いますか、はい、こんな感じで。
12月に東京・池袋の東武デパート美術画廊にて開催予定の
「小さい絵」展に出品いたします。
詳細はまたご案内させてください。
悶えて唸りつつも、やはり卵黄テンペラの模写は楽しいのです!
令和から昭和に加工 10月21日
今年も11月末から12月にかけて
谷中の箱義桐箱店谷中店の皆様のお世話になりながら
展示会を開催予定なのです。
そして毎度のことながらディスプレイに悩みます。
なにせ小箱と言うくらいですから
ひとつひとつが小さい。
ぽっちらぽっちら並べても
「なんのこっちゃ」という印象ですし
凹凸がありません。
額縁をお盆のようにして(平面を区切って)
小箱の集団をいくつか作ったりしました。
でもやっぱり何か高さが出るものが欲しい。
軽くて小さくて、安全な什器・・・。
そんなことを考えておりましたら
木製のキャンドルホルダーなるものを発見しました。
パイン材ですって。
▲写真はショップからお借りしました
上部のお皿がφ80mmなら小箱を
ひとつ置くのにちょうど良さそう!
という事で、さっそく注文しました。
届いた商品は薄い塗装にニス仕上げで
シンプルで可愛らしい。
・・・小箱展示にはもう少し、なんというか
コッテリ感が欲しい!
まずはニスを溶剤で剥がし、カーブを好みに削って、
ついでに柱中央の丸部分を簡単に彫っちゃって、
色も濃くしてワックス塗って、ふぅむ・・・どうだろう?
▲白い部分が削ったところ。
▲ステインで着色して、お得意(笑)のワックスコテコテ仕上げ
うむ。イタリア風味は感じないけれど
古臭くはなりました。よしよし。
▲ちょっとお供えっぽいのは気のせいですか。
もしかしたら小箱よりも最中やお饅頭のほうが
似合う仕上がりかもしれませんけれど、
そしてなぜか昭和を感じますけれど、これはこれで。
昭和生まれのわたしが作るものを乗せるのですからね、
昭和風味で結構なのでございます。
・・・開き直って。
楽しい工作でした。展示が楽しみです!
カフェオレの香りがする額縁は有りか無しか 10月03日
古典技法で金箔を貼るには
磨いた石膏地の上にボーロと呼ばれる箔下地材(粘土)を
ニカワ液で溶いたものを塗り乾かします。
そこに普通の水、つまり水道水ですけれど
水を塗って箔を乗せます。
そんな風にして作業をするとき
飲み物を横に置いていることがあります。
なかなかに神経を使う作業ですので、リラックスする為に。
▲散らかった机は見逃してください・・・
上の写真、右のマグカップは箔用の水
左がカフェオレです。
そうです、ご想像の通りでございます。
筆をカフェオレに突っ込みました。
いつかやるだろうと思っていた失態、
とうとうやりました。
筆を入れた瞬間に「ギャッ」と気づいたので
幸いにもカフェオレで箔を貼ることにはなりませんでした。
ほんのりとカフェオレの香り漂う
額縁になったのかもしれない・・・と想像します。
でもでも、牛乳はカゼインでしょ、接着剤にもなっているでしょ
もしかしてもしかしたら水より牛乳で箔を貼った方が
より丈夫に仕上がったりして!
・・・水貼りで十分頑丈ですし
虫やらカビやらが寄ってくる方が心配ですね・・・。
▲大切なマグカップ、欠けてしまったので道具として更に活躍。
古典技法の長い長い歴史の中で
同じ失敗をした職人はぜったい、いる。
なんならワインだったかもしれないし!
そんなことを考えながら、そっとカフェオレを飲み干しました。
筆を突っ込んだことはすっかり忘れていました。
一匹狼が三匹 9月26日
東京はある日突然に、秋になりました。
去年の秋の始まりもこんなでしたっけ?
出不精のわたしですが、久しぶりに会った友人二人と
お互いに最近の経験と考えていることを話し合って
そして励ましあって、ずいぶんと元気になりました。
分野は違えどひとりで制作している
またはフリーで活動している友人ですので
一匹狼気質といいましょうか、改めてそんな共通点を感じたのでした。
▲夏に食べたプラム、美しい色
わたしたちに「気づき」を与えようとしている人がいて
でもその人たちは言葉で何かを与えてくるのではない。
きっかけだけを提示して、こちらの様子をうかがっている。
どんな気持ちでこの作品を作ったのか?
あなたは自作のものに対して、どの程度の考えを持って発表しているのか?
などなど・・・。
それをわたしたちが受け取るか受け取らないか
(受け取る気にならないか)は、
そして考えて答えるにはタイミングが大切だよね、と言うこと。
なんだかお互いに共感して
「うんうん、そうだよねぇ・・・」を繰り返した午後でした。
そんな時間が必要だったのでしょう。
箔の上にもできますよ、の種明かし 9月02日
先日Instagramに、金箔2種類の貼り分けを載せたところ
思いがけず沢山の方にご興味を持って頂けたようでしたので
こちらブログでもご覧いただけたらと思います。
ヨーロッパ古典技法の箔の技法に「ミッショーネ」と言って
箔用の接着剤で貼る方法があります。
一般的にはテンペラ絵の具などで彩色した面の上に
例えば衣装の模様や天使の後輪などを入れる技法です。
今回は箔の上に箔を貼ってみます。
まずベースにはいつもの水押し技法(ボローニャ石膏地にボーロを塗り
箔を水で貼ってからメノウ磨き)で貼り磨いてから
その上にミッショーネ液(箔用の糊)で模様を描きます。
そして糊が半乾きの頃にもう1種類の箔を乗せます。
▲今回は4号箔(22カラット金箔)を水押しし
その上に水箔(14カラット金箔)を乗せます。
奥にある白い液体瓶がミッショーネ液。水性です。
そして、しばらくしてから筆で優しく掃うと
糊を置いた部分に模様が残る、という流れです。
▲これが一番楽しい瞬間
わたしは石膏地に模様を線彫りしてからベースの箔を貼り磨きます。
そうすると次の作業のミッショーネ液塗りが楽ですし、
わずかな凹凸でも立体感が出ますので。
▲こんな感じになります。ミッショーネ部分は磨けないので艶消し。
言ってみれば、いつものミッショーネ技法と同じなのですが
箔の上にも出来るよ、という事なのでした。
知り合いの古典技法作家の方が「水押しで貼り分けているのかと思った!
どうやっているのかと思った~」とおっしゃっていましたので
種明かし。でした。
ぎりぎりを攻める 8月29日
桐木地の小箱の形を変えるとき
一番悩むのが「どこまで削るか」です。
箱に使われている板の厚さ(おおよそ4mm)を鑑みて
箱の強度と安全性が保たれるギリギリラインまで攻めるのです。
▲これはもう少しだけ攻められそう。
もともと四角い箱を、どうにかして変化をつけたい!その一心です。
全ての角を丸くする、エッジをつけて丸くする
あるいは角を面で切り落とす・・・
4mmの間でいかに変化をつけるか、難しくも楽しい作業です。
まだバリエーションは増やせそう!
「むぅぅ」の行きつく先は 8月26日
ある日の出来事、どうでも良いけれど
どうでも良くない出来事の日記です。
前夜の寝る直前にsnsで嫌な発見があって
「むぅ」と思いつつも、まぁ仕方がない
そんなもんだ、と振り切って眠りました。
そうしたら案の定、とても嫌な夢を見て
これまた「むぅぅぅ」と起き上がりました。
またもやボンヤリとsnsを見ていたら
友人の幸せな様子が目に飛び込んできて、慌てて目を逸らす。
こんな時はとにかく無心になるのじゃ!と思って
それっ!とばかりに作業部屋に駆け込んで
自分の幸せを数えて(昭和の歌詞のようだけど)
黙々と作業をいたしました。
なにせ頭と心と手と目の接続が悪い時ですので
単純作業が吉。ひたすら点々打ちに没頭しました。
▲わたしを慰めてくれるのは、やっぱり制作なのでした。
夕方近くには気分もすっきりして
「やれやれ」と思っているところにメール着信。
クレジットカード会社から「4500円の
不審なカード使用があったから本人使用か確認したい」とのこと。
その「不審な使用」はつい2分前なのでした。
2分前なんて点々打ちに没頭していた時です。
もちろん「わたしは使っていません」と返信しました。
あっという間にカードは停止され
番号も変わるとの知らせが来ました。
(確認したところ幸いに不審な使用はその時のみ)
新しいカードが届くまで2週間程度かかるとか。
その間はオンラインで買い物できませんし
諸々登録してある支払い(保険ですとか)も番号変更手続きが必要・・・
昨夜から続く「むぅぅぅ」っとした気分が
ここで最高潮になりました。
いつどこで番号が盗まれたのか
だれがどこの国で何を買おうとしたのか
もう分かりませんけれど・・・
カード会社の対応のスピードからして
珍しい出来事ではない様子ですし
漠然とではありますが気をつけないと、と思うのでした。
▲庭のモジャモジャを見て深呼吸
幸いにも金銭的な被害はなかったけれど
心のショックと恐怖と「むぅぅ感」は増しました。
でも不幸中の幸いと言えるのでしょう。
誰も気づかなかったら被害額は増えて
心的疲労も恐怖心も倍増ですもの。
むぅぅ・・・と思っていると
「むぅぅ」な出来事を引き寄せるのでしょうか。
意識して朗らかに過ごしたほうが良いだろう!と頷いたのでした。
ラテン語額縁大活躍の巻 8月22日
6月に完成してお届けした「ラテン語額縁」
(ラテン語のフレーズを装飾として入れた)は
おかげ様で大活躍したそうです。
ご注文下さったのはジュエリーブランド
germedeur の主催者 kaneko さん。
8月、新宿伊勢丹1階で germedeur の
ポップアップショップが1週間オープンして、
ラテン語額縁はガラスケースの中で
美しいジュエリーを展示するお手伝いをしていました。
▲最終日に駆け込みでご挨拶に伺いました。
額縁は伊勢丹の担当の方やお客様にもご好評ですよ!と
kaneko さんから嬉しいお言葉を頂きました。
フル・オーダーメイドの古典技法額縁は珍しいようです。
kaneko さんには額縁以外に小箱も使って頂いておりまして
これまた嬉しい再会です。
▲豆小箱に指輪がひとつ。ピッタリサイズ!
▲錫箔の箱も嬉々として働いていました。
それにしてもなんという下手な写真でしょうか。
実物の展示とジュエリーはもっともっと素敵なのですよ!
・・・それはさておき。
我が娘(額縁や小箱)が嫁ぎ先で大事にして頂き、
さらに喜んで頂いているとは母としてこれ以上の喜びはありません。
また頑張って作ろう!という励ましと
kaneko さんの自信とエネルギーを分けて頂いて
晴れ晴れとした気持ちになりました。
さぁ、残暑は厳しいですが秋は目前、がんばります。
今にして分かること 8月19日
小箱制作では、ある程度まとまった数の小箱に
石膏下地を施しています。
ボローニャ石膏を塗り重ねて乾かしておけば
いつでも思い立った時に装飾作業が出来るという流れ。
今日もウサギ膠にボローニャ石膏を溶いて石膏液を作りました。
そしてふと、フィレンツェ留学時代に
弟子入りしていた額縁工房でのことを思い出しました。
午後に工房へ行くと、同じころに来たパオラがひとこと
「あ!今日の石膏液は良い感じにできてるねぇ!」
それを聞いたマッシモが
「でしょ?午前中に作っておいたんだ。フフフ・・・」と
2人でホクホク喜んでいました。
わたしはその「良い出来」の石膏液を
混ぜたり触ったりして「へえぇ」と思いつつ
今ひとつ「何が良いのか分からない」のでした。
そして今日、小箱用に作った石膏液は、とても良い出来でした。
トロリとなめらか、少しふんわりとしている・・・
とても美味いポタージュのような。
あの時、ふたりが言っていた「良い出来」の石膏液は
きっとこんなだったのかな、と思い出していたのです。
そうして振り返ってみれば
今のわたしは当時の2人の年齢に近づいて来ました。
結局、そういう事なのですよね。
制作をずっと続けて、ああでもないこうでもないと経験しつつ考えて
ようやく積み重なって、石膏液の良し悪しだとか
「どうして今日の石膏液が良くできたか」が理解できるようになった。
しみじみと感慨にふけった午後でした。
未だわからない 8月15日
小箱に金箔を貼って、その上に彩色して模様を入れました。
何色を塗るかは、あっさりと決まる
(その時の気分によって選ぶ)時と、
数日の間、本を見たりして悩んでから決まる
という2パターンあります。
今回は悩んだバージョンでした。
選んだ絵の具の色名はクリムソン
臙脂色というか、青味のある暗い赤色です。
今まで金と赤の組み合わせはあまり選んできませんでしたが
少し違う雰囲気の彩色も良いかしら・・・と選びました。
だけど、なんだか、気に入っているようないないような
未だ釈然としません。
そうこうするうちに彩色も完成しました。
なかなか華やかな雰囲気。
これからアンティーク風に古色をつけて仕上げます。
どうなる事やら??
今日は何の日 8月12日
「今日は何の日?」
「ダメダメの日」
どうにもこうにも細かい作業が上手く行かない日ってあります。
▲ブレちゃってずれちゃってもうどうにもこうにもいやはや。
オフホワイトの絵の具で模様を細く入れたい・・・
ですがブレブレのヨレヨレ。
そんな時はすぱっと止めて
事務仕事でもした方が有意義なのです。
分かっちゃいるけれど、「でもでもだって!
今はこれがしたいんだもの!」と叫ぶ気持ちもある。
仕方がないので、ここぞとばかりに秘蔵(?)の新しい筆をおろして、いざ。
そうして続けると、嗚呼・・・言わんこっちゃない。
・・・とは言いたくないけれど。
いさぎよさも随時必要でございますね。
ぶれた線は明日の午前中に修正します。
金に糸目はつけぬ 8月05日
ペンが一本ほしくて、駅前の文具店に行きました。
そうしたらついうっかり楽しくなってしまって
あれもこれも、そうだテープも・・・などとかき集めてしまって
お会計をしたら5000円ですって。
自分の頭の中では「えーっと、たぶん3000円くらいかな!」などと
能天気なことを考えていましたので一瞬ぎょっとしました。
▲これだけ買えば当然
でもまぁ、どれもこれも使いますし便利ですし
着ない洋服を衝動買いするより有効なのだ!・・・などと思っています。
と言うか、眺めてニヤニヤ、使ってホクホクしています。
先日、知人にわたしが「あの画材があると便利だよ~。
でもちょっと高いし少ししか使わないから勿体ないかもね。」と話しましたら
彼女は「いいの、買う!わたしは画材なら
お金に糸目はつけないから!」と言っていました。
ああ~!ここにもいた。画材には金銭感覚が変わる人。
わたしも同様なのですもの。
なんなんでしょうね、この感覚。
じゃんじゃん使おう 8月01日
額縁の吊り金具(額縁裏に取り付けて紐を通す金具です)
が無くなったので、購入しました。
画材店などでは数個ずつ売っていますけれど、割高ですのでまとめ買い。
そうしましたら、ひと箱1000個ですって。
某モ〇タロウでは1000個が最小ロット。
1000個の吊り金具って、額縁1枚につき2つ使いますから
つまり額縁500枚分です。
一般的な額縁工房ではこうした単位で購入しないと追いつかないはずです。
なにせ作る額縁の枚数が沢山ですからね。
500枚の額縁ですって。
アハハ!・・・死ぬまでに使い切りたいと思います。
いや、そんなことを言ってる間にジャンジャン作って
ジャンジャン金具を使いたいと思います!
どこもかしこも 7月22日
先日、ドイツ人でベルリン在住の友人Kと電話していたのですが
彼女は自分のお店(自作の革製品を販売するお店で奥は工房になっている)
を閉じようと思うとの話。
あんなに頑張っていたし楽しそうにしていたのに、なぜ?と聞くと
「お店のある通りは今はほとんどのお店が閉めてしまった。
人通りも減ったからお客さんも来ないし、
賃貸料の支払いも大変だし・・・」
Kはネットでの販売もしていますが
「2018年頃は売れ行きがすごく良かったけれど、コロナ後は全然。
食品の価格も倍になったし、3つ目のバッグを買う人はいないのよ。」
との事でした。
ミラノ在住でフィレンツェ留学時代の友人Fの話。
彼はとても有名な家具修復工房の3代目で
腕も人柄も良くて安泰と思いきや
「いわゆるクラシックな古い家具って大きいから広い家が必要だけど
若い人はもう大きな家に住む余裕は無いしね。
それにこうした家具は時代遅れでもう好まれないからさ、
今ある修復の仕事はすべて以前からのお客さんで
それもお年寄りばかり。
彼らが亡くなったら家具は二束三文で売られちゃうか
捨てられるだろうね。」と言っていました。
超絶技巧で作られた家具、昔は箪笥2竿でマンション一件分の価格でした。
今まで繰り返し修復し大切にされてきたけれど、それらも顧みる人が居なくなる。
時代の流れ、と言えばそれまでだけど。
どこもかしこも(ドイツとイタリアだけですが)
嬉しい話はあまり聞けません。
バイデンさんとトランプさん、ゼレンスキーさん、プーチン氏、
イスラエルとパレスチナ、その周辺、そして中国、北朝鮮。
他にもわたしが知らないだけで、もめ事は尽きない。
回りまわってわたしたちの日常も不穏ですね。
どうしてこうなってしまったのだか。
考えても考えても、じゃぁこうすればよい
という答えは見つかりません。
それを「ど忘れ」と言って良いのか 7月11日
昨日の午後、魚ニカワ液をつくろうと思ったのでした。
このニカワ液は、古典技法の箔貼りにいつも使っているので
もう何百回と繰り返し作っています。
板になっている乾燥ニカワを小さく刻んで水にふやかし
翌日に湯煎で溶かせば完成です。
上の写真、右のシート状のものが魚ニカワ。
製菓で使う板ゼラチンとそっくりです。
左の瓶は魚ニカワを水に漬けたもの。
で、ですね・・・。
この何百回も作っているニカワ液ですが
1リットルの水に魚ニカワ4枚というのが大体の決まりと言いますか、
わたしがイタリアの学校で習った分量です。
昨日「さて作ろう」とおもったのですが、はて・・・。
突然、本当に突然この分量が思い出せなくなりました。
あれ、水1リットルに1枚だっけ?え、250ミリリットルに1枚だっけ・・・?
ネットで検索してみたら自分が昔書いたブログに行き当たり
無事に1リットルに4枚と確認できた次第です。
そうだそうだ、そうだった。
昔のわたし、書いてくれてありがとう・・・。
だけど、ニカワ液が作れて安心しつつ
自分の脳を心配しつつ、なんともドンヨリした午後でした。
いやはや。
美しいラテン語 7月08日
完成間近になっている額縁は、ラテン語装飾です。
ジュエリーブランド「germedeur」のkanekoさんからのご注文
ジュエリー展示に使っていただけるように作っております。
昨年「ことわざ額縁」と名前を付けた額縁を
ご覧になったkanekoさんが、
ガラスケース内で使えるサイズで文字を入れて・・・
とご注文くださり、さて文章はどうしよう?
ご相談を重ねました。
▲満を持してラテン語文章の装飾を額縁に転写する。
アルファベットの文章で、ぱっと見て意味は
すぐに分からない言葉(英語でもフランス語でも無くて)・・・
で、ラテン語に収まりました。
kanekoさんが日本語で文章を作り自動翻訳でラテン語に訳し
じゃぁこれで行きましょう!となったのです。
が、ご存じのように自動翻訳ってまだまだ危うい・・・
額縁を作り始めてしまったら
文章を変えることはとても難しい。
ここはひとつイタリア人に尋ねるが吉。
そうしましたら案の定「ええと、言いたいことは分かるけど
文章として微妙というか美しくない。」とのこと。
添削してもらいました。
kanekoさんによる日本語文章
「ジュエリーを通じて希望と喜びを分かち合う」
これを自動翻訳では
「Spem et laetitiam per ornamenta participes sumus」
そして添削後
「Spei laetitiaque per ornamentum participes sumus」
構成の変更はなかったけれど、小さな言い回しなのか
単語の活用など変更されていました。
(変更理由など説明してくれたのですが
わたしのイタリア語能力ではいまひとつ理解できず!)
ハッキリ言ってよー分からんのです・・・。
とにかくこれで「正しくてエレガントなラテン語」になったはずです。
イタリア人にとってラテン語は
どんな位置なんだろうと、つねづね思っていました。
日本人にとっての古文?もっと近いのか遠いのか。
きっとある程度勉強したり興味を持っている人なら
読んで理解はできるでしょう。
でも作文や添削となると別、と言った感じです。
そして「より美しい文章」となると、これはぐっと難しくなる。
このイタリア人の友人には感謝です。
きっと高校時代は頑張って勉強したんだろうなぁ・・・と思います。
あなたは何て呼ばれたい? 7月01日
わたしの名前は、ハルコと言います。
アルファベットで書くと HARUKO となりますが
イタリア語では H を発音しません。
HAHIHEHO(はひへほ音)はほぼ全て AIEO の母音のみになる。
で、わたしの名前は彼らイタリア人にとっては大変発音し難いようです。
大抵の人たちは「アル~ゴ~」と、ルにアクセント
そしてなぜかコはゴになることが多くて
ちょっと笑っちゃって楽しいのだけど、釈然としません。
「はるこ、と呼んでください」と一度だけ説明して
きちんと呼んでくれている人は数人います。
とても嬉しい。
ちなみにわたしの工房名というか屋号というか・・・
「KANESEI」かねせい、ですが、こちらは
イタリア人の皆さんには違う意味で難しいのかもしれません。
イタリア語で CANE は犬、SEI は助動詞の二人称単数
「Cane sei」と言うとつまり「お前は犬」と言う意味に取れます。
そしてCane は犬の他に「嫌なやつ、無能なやつ、情け知らず」
というような悪い意味もあって、ううう
イタリアで「Cane sei!!」カネセイ!と誰かに向かって言ってはいけません。
フィレンツェでわたしの小箱を扱って下さるお店 Eredi Paperone で
わたしの小箱解説にはKANESEIの文字は無くて、
わたしのフルネームでご紹介くださっています。
最初は「なんでかな、屋号は知らせたはずだけどな・・・」と思っていたのですが
ある時に「もしかして」と気づいたのでした。
わたしはあえて尋ねませんし、お店の皆さんは何も仰いません。
ただ屋号は使わず名前で紹介してくださっている。
そこに皆さんの優しさを感じます。
ずいぶん昔、留学時代に友人Lは愛称といいますか
短くした呼び名で呼ばれていました。
わたしも同じように呼んでいたのですが、ある日Lが
「・・・その呼ばれ方、本当は好きじゃないんだ」と
ボソッと、でもきっぱり言ったことがありました。
その日以来、彼の名前は短くせずにきちんと呼ぶことにしたのでした。
呼び名、呼び方って難しい。
それは自国でも外国でも同じことなのですけれど
相手に敬意を持っていれば自然と「お互い気持ちの良い呼び方」
に導かれていくのだから、何も難しいことは無いのだな
・・・と思っています。
一年は厚かった 6月24日
2023年の一年間、曹洞宗の月間冊子「禅の友」の表紙に
KANESEIの額縁写真を使っていただきました。
このブログでもたびたびご覧いただいておりました。
1年間分、12冊分って結構な量だな・・・と
思っておりましたが3回の撮影が楽しすぎて
終わってしまったのが残念でなりませんでした。
その1年間分12冊の「禅の友」をまとめた1冊が作られて
わたしにも贈って頂きました。
▲2023年 第881~892号
表紙に1月号~6月号の表紙額縁
裏表紙に7月号~12月号の額縁がモノクロで印刷されていて
やぁやぁ、とてもカッコ良い。
12冊をそのまままるっと綴じてありますので
表紙も裏表紙もそのまま。
▲2月号の裏表紙の小箱と、3月号の表紙額縁。
▲10月号の裏表紙の小箱、そして11月号の表紙額縁
1冊の冊子は40ページ弱ですが
12冊合わさると厚い。そして重いです。
こつこつと毎月発行しておられる編集部の方々
ありがとうございました。お疲れ様です。
毎年この総集編が出ることで達成感も強く感じられる事と思います。
▲厚くて重い
とても嬉しく、感慨深く、大切な1冊です。
満ち足りてしまったから、その時が来るまでは 6月17日
先日のこと、あまりに出不精になって
リハビリが必要なレベルかも・・・と
友人と話したことがありました。
本当にもう、我ながら社会性がどんどん失われるんじゃないかと
(もともと希薄なのに!)思っています。
その良し悪しを考え始めると止まらない。
どうもこの傾向は2020年、コロナ禍以降顕著になったようです。
きっと世の中全体が引き籠りせざるを得なくなって、
でもその時期も終わって、皆さん否応なく元の生活に戻られたことでしょう。
そしてわたしですが、作業部屋が自宅の一角にあること
元から出不精だったこともあって、
コロナ禍が終わってもそのままの生活を引きずっています。
あの友人、かの人はどうしているかなと思って連絡はするけれど
出向いて会うまでに至らないことが増えた。
「あの展覧会、見たいな、会期はあと1週間しかないな」と思っても
出かけて行くことが減った。出かけたいと思わなくなった・・・。
どうしてこうも出不精に拍車がかかったのかな、
以前のようにもっと友人と会ったり美術展や
遠くの大きな本屋さんに出かけたりしなくなったのかな・・・と考えたのですが
つまり、小箱制作が楽しすぎて充実しすぎて
それで満足しているからなのです。
2020年春から本格的に作り出した小箱が
図らずもわたしの人生に対する姿勢まで変えてしまったのでした。
楽しくて仕方がない小箱制作と額縁制作を
ひとりで引き籠れる部屋で毎日好きなように続けることが出来て、
それらを喜んでくださる方々が居て、満ち足りている。
それなら別に、人付き合いが悪くても(もともと良くも無い)
最新の美術界情報に疎くても
今のところはまぁ、良いんじゃないの・・・という結論に至りました。
こんな風に認めるには時間がずいぶんと必要でしたが
それも併せて良いと、自分に言い聞かせています。
きっとわたしも、否応なくこの生活を変える時が来るでしょう。
その時まではこのままで。
ひとりでニヤニヤと制作を続けられる幸せを噛みしめています。
ありがとうございます。
幸せな娘時代を思い出すマダム風 5月30日
現在、ご注文を頂いて作っている額縁は楕円形です。
白木(無塗装)の額縁木地を日本で調達する場合、
木工所に頼むか、木地メーカーから購入するか
既成の木地を買う。おおむねその3パターンです。
そして日本で楕円形の木地を手に入れるのは困難なのです。
需要が少ない上にサイズ調整もできないし
板を刳り貫くので材料費もかかる・・・
入手困難もやむを得ないことでございます。
今回の木地は、ご注文下さったお客様ご自身が購入されて
KANESEIに持ち込んで下さったものです。
イタリア製だとか。いいなぁ、楕円・・・
さてさて、デザインはすぐに決まりました。
パスティリア(石膏盛上げ)で模様と文字
「CHAOS」「ORDER」を入れることになりました。
木地に石膏を塗り磨きまして、わたしの好きな技法
パスティリアで左右に模様。
そして上に CHAOS 上に ORDER とゴシック体で入れます。
文字アウトラインに線刻を入れて
▲額縁サイズはB5の縦長な感じ
純金箔の水押し。古典技法真っ只中を進みます。
▲ボーロは赤。やはり赤が一番美しく仕上がると感じます。
今回、楕円形の額縁の箔作業は初めてでした。
ずいぶん昔に作った楕円額縁は木地仕上げでしたので・・・。
箔作業は、貼り始めの場所を記憶しておくことが必要
(次の作業の開始場所でもあるので)ですが、
四角など角が無い形、始まりと終わりが無い
繋がった形ですので不思議な感覚でした。
楕円(正円)の額縁制作の注意点を知る。
途中、どこから始めたか分からなくなってしまって気づきました・・・。
▲机の上の散らかり様は見て見ぬふりでご容赦ください・・・
箔を貼り磨き、部分的に黒で彩色して、
文字の中をマイクロ点々打ちをして、さて。
楽しい楽しい古色付けです。
キラキラ輝く金箔をスチールウールで擦って傷をつけ
ワックスで汚して、ボロボロ加工をしてアンティーク調にします。
輝く金と艶やかな真っ黒な色が
この加工でしっとりと落ち着いてきます。
勝手なイメージですけれど、古色加工前の額縁は
「露出度高めの黒いドレスを着た若い女の子が
瞳をキラキラさせて楽しくパーティーへ向かう!」
という雰囲気だったのが、古色加工をすると
「50年後、その女の子は沢山の人に愛されて沢山の経験をして
奥底から湧き上がるような美しさを湛えるようになった。
そうして幸せな娘時代を思い出して微笑んでいる」
というような変化。
そんな感じになったら良いなぁフフフ・・・
と思いつつ、今日も嬉々としてガサゴソ作っています。
庭の攻防 5月06日
我が家は東京都23区内とは言え
(よく言えば)自然豊かな場所にありまして
ささやかな庭があります。
父がお仏壇から下げたご飯を鳥用の餌台に入れて
食べに来る様子を家族で楽しんでいます。
来るのは主にスズメとヒヨドリ。
▲ヒヨドリはいつもひとり。
ひよどりひとり。韻を踏む。
▲スズメはふたりで来る。
餌台、変な形と思われるでしょう・・・
この形に至るまで色々とありました。
この台は父の労作でして、数年前に完成した時は
額縁の付いた美しいお盆状のでした。
今はこの状況・・・
白い小さな器はお豆腐が入っていたケースを下げています。
小さい!そして下部の青い三角はネズミ返し・・・。
昔、社会科の授業で弥生時代の高床式住居を習いましたでしょう
その時に覚えたのが「ネズミ返し」、アレです。
柱を上ってきてもこの「返し」でそれ以上登れない仕掛けです。
美しい広い台だと植木からネズミが飛び移ってくる。
ネズミ返しがないと柱をネズミが駆け上ってくる。
なぜ小鳥は良くてネズミはだめなの?!同じ生き物でしょうに!
実際、庭を駆け回る(そうです、居ます・・・)
小さな野ネズミはとても可愛らしいのです。
ベアトリクス・ポターの絵本そのままの姿です。
でもねぇ、家に入ってくるのが、そして子孫繁栄しちゃうのが問題でねぇ。
そんな訳で、我が家の庭には小さな攻防戦が繰り広げられております。
今のところ餌台は父の勝ち、となっております。
必要か必要ではないのか、それが問題だ 5月02日
わたしの制作に純金箔は欠かせません。
必要なのですから買います。
ええ、買いますとも、必要ですからね。
たとえ懐が痛もうとも。
▲主に4号箔を使っています。
金は時価ですからいくつかの金箔メーカーの価格を比較して
その時々で選んでおります。
それにしても、た、たか・・・
いや、これ以上は言いますまい。
タイムマシンがあったら大学時代に戻って
金箔を大量購入したいと思います。
当時に比べたら4倍近いお値段なのですもの・・・嗚呼。
額縁も小箱も生活必需品ではありません。
命にかかわる事でも無し。
わかっちゃいるけど。
金箔の価格で嘆くなんてねぇ・・・。
世界を見回せば、わたしの周りの狭い世界の
なんと穏やかなことよ・・・。
引き込まれて救われて 4月15日
なぜだか分からないけれど
どうにもこうにも嫌な考えのループに嵌ってしまう事があります。
そして自己嫌悪したりして。
昨今はウェブ上にそんな時の解決法がたくさん紹介されていて
瞑想する、運動する、自分を俯瞰的に見る、
そんな自分も受け入れる等々、いくつもあります。
だけど、ううむ、そうじゃないんだよ・・・
と、ひねくれ者のわたしは思う訳です。
運動したって一時しのぎでしょ(大体運動嫌いである。)
そんな自己嫌悪するような自分を受け入れましょうって、
そうしたら、そんな思考回路で止まってしまうじゃないか
・・・ブツブツ。
▲小箱ばっかり作っている場合じゃない。
小箱に逃げている。分かっておる。
そんなある日、偶然に北インドのシタール音楽を聴きました。
シタールはご存じと思いますが、ギターのように
左手で弦を押さえ、右手で爪弾きます。
そしてタブラと呼ばれる太鼓(二つセット)奏者と
2人で演奏するのが多い様子。
このシタール音楽が「ぐるぐる思考」からの脱出に
大変効果があることが分かりました。
・・・わたしだけかもしれませんが。
全く詳しくありませんので勝手な解釈ですが、
伝統的な演奏は短くて30分、おおむね1時間と長い。
そして曲の出だしはシタールのみでジャラララ~~~ン・・・と
地底から響くようにゆっくり始まります。
曲の半分頃にタブラがこれまたゆっくり加わって
そこから徐々にスピードが上がります。
タブラの「タンタカタンタカ」(右手)と「ムーンムーン」(左手)が
どんどん早くになって、シタールのメロディーも競うように早く複雑になって
聴衆の心拍数もどんどん上がる。
そして全員の興奮が最高潮に達したときにジャンッ!と終わるのです。
この、歌詞もなく(意味付けが無く)
聞く機会が少ない音楽なのもポイントに思われます。
少しずつ興奮の渦に引き込まれる時に
徐々にわたしも変な思考から引きずり出され
何も考えずにハラハラドキドキが高まって
ダンッと曲が終わるときにはまるで「サウナから出て
水風呂に浸かって整った」ようなサッパリ爽快な気分になるのです。
驚くほど効果があります。・・・わたしだけかもしれませんが。
長々と説明しても、この不思議な解放感は説明できません。
YouTubeやSpotifyでも「シタール」と検索すると
沢山聞くことが出来ます。
わたしは最近のオシャレなアレンジではなくて
いわゆる巨匠の演奏を選んでいます。(モノクロ写真の演奏)
シタールの音は少し琵琶や津軽三味線のようですし
タブラも鼓のように聞こえる時があります。
もし気になる方がいらっしゃったら
もし聞いてみようかな、と思われたら
Ust Vilayat Khan aged 16 – rare video (youtube.com)
(↑3分ショートビデオ、英語の解説あり)
Shahid Parvez Raga Darbari (youtube.com)
Vilayat Khan – Raag Darbari (1968) (youtube.com)
上記YouTubeの演奏などぜひ。
長いですけれど、きっと引き込まれること請け合いです。
技術とセンス 4月04日
現在フィレンツェに滞在中の友人が
美しい写真を送ってくれました。
EREDI PAPERONE Bottega d’Arte の
ショーウィンドウに並ぶKANESEI小箱です。
写真のセンスと技術があると、こうも違うのですな…!
彼女の配偶者の方はフォトグラファーなので
やはりそんな所もお二人は通じているのかもしれません。
あれ、こんなにカッコいい雰囲気に展示されていたっけ?
おや、こんな美しい陰影が見えていたかな??
実物より良く見えている!?
この小箱たちが良いご縁に恵まれますよう。
もしフィレンツェにお越しがありましたらぜひ
EREDI PAPERONE Bottega d’Arte へお立ち寄りください。
EREDI PAPERONE Bottega d’Arte
Via del Proconsoli,26r Firenze
10::00~13:00/14:00~19:00
考えすぎだとしても 4月01日
3月30日の土曜日、悲しいニュースに触れました。
彫刻家の船越桂さんが肺がんで亡くなったと。
展覧会に行ったり制作過程等のDVDを観たり
お父様の船越保武さん共に尊敬する方でした。
ご冥福をお祈りいたします。
そしてまた、マッシモを思い出したのです。
フィレンツェの額縁師匠マッシモは
昨年初秋に体調を崩して呼吸が困難になり
病院で検査を受けたところ、すでに肺がんが
進んでいて手の施しようがない状態だったとのこと。
妻パオラ曰く「とてもアクティブながん」で
骨や腎臓、リンパにどんどん転移してしまって
治療を施す暇もなくあっという間に行ってしまった。
そしてパオラもまた今、呼吸がつらくて
ほぼ24時間酸素吸入をしています。
確かに2人ともタバコを吸っていたけれど
(パオラは今も吸い続けている!止めてくれない。)
もしかしてもしかしたら、いや可能性として
額縁製作の職業による影響もあったりして・・・?
なにせ古典技法額縁では木屑と石膏粉から
逃れることが出来ません。
そして彼らは咥えタバコでマスクなどしなかった。
仕事として朝から晩まで毎日をこの粉の中で
過ごしていたら、と考えてしまう。
船越桂さんもまた、木彫作家の毎日で
粉塵は避けられない生活だったのではないでしょうか。
考えすぎかもしれないし、そうではないかもしれない。
石膏粉や木屑よりタバコの方が肺にはずっと悪い事は
百も承知だけれど、ううむ。
自分の身体を守れるのは自分だけですものね。
面倒くさがっていても後悔先に立たず。
わたしはマスクをもう少し高性能のものにしようと
改めて思います。
「そういう時」のために 3月25日
先日お話したようにノロウィルスに大打撃を受けた我が一家
おかげ様でそれぞれ快復いたしました。
わたしもどうにかパジャマを脱ぎ捨てて作業部屋に入った日
納期間近の額縁制作を再開したは良いけれど
あわや大失敗!という瞬間がありまして
いやもう、こんな日は急がば回れ、
落ち着いて違うことをした方が良いのです。
かと言って気は焦りますし本を読んだりする気分でもない。
何かしていないと落ち着かない。
「そういう時」のために、制作途中の
マイクロ点々打ち小箱がいくつかあります。
石膏や金箔が乾くのを待つ間の手持無沙汰の時とか
気分を落ち着かせたい時とか、
ひたすら点々打ちをします。
「なにかしている感」が感じられて(実際なにかしているし)
瞑想のような効果もあるようで
気持ちが徐々に落ち着くのでした。
今回のノロ騒動の余波で上の写真の小箱装飾は完成しました。
これも怪我の功名といいましょうか。
うわさ通りのアイツ 3月21日
いたって個人的な事ですけれども
先日ノロウィルスに感染しました。
家族のひとりが外食時に感染したらしく
(同席した方々も感染・・・)、
その後に他の家族も感染、そして最後にわたし。
話には聞いていましたけれど
このウィルスの強さにはもう、どうにもこうにも。
症状はいわゆる「ノロウィルスに感染した時」そのものでした。
お茶を飲むのも恐ろしい。
身体中がウィルスを追い出そうと
奮闘してくれているのを痛感しつつ寝ているのみ。
▲せめて画像は爽やかなフィレンツェの青空
いやはや・・・家庭内では気を付けるにも限度があります。
これはもう、コロナ並みにお風呂もトイレも寝室も
もちろん食事も別にしない事には
避けられなかったと思われます。
後悔先に立たず。
それにしても、どうにかこうにかシャワーを浴びられるまでに快復して
久しぶりに見た鏡の恐ろしさたるや。
10~20年くらい老けていました。
なんというか・・・日帰りした浦島太郎というか・・・
これから春なのに!気持ちの良い季節がやってくる!
わたしもここで老け込んでばかりいられませぬ。
モリモリ食べてジャンジャン作って
心身を盛り上げて回復したいと思います。
皆様も油断大敵、いつどこで何ウィルスが待ち受けているか・・・
ご用心です!
ホカホカマリア様? 2月26日
イタリア語を少しご存じで
古典技法の経験がある方ならば
あるいはイタリア料理を勉強なさった方なら
きっとご存じのイタリア語単語
それは「bagnomaria」、湯煎という意味です。
古典技法で欠かせない石膏地はニカワ液に溶いてありますから
必ず湯煎で温めて液状にして(冷えるとゼリー状になる)使います。
▲右上のガラス瓶に石膏液が入っています。
普段は冷蔵庫に入れておいて、使う時に湯煎で温めています。
下に敷いた紙がびしょ濡れなのは、湯煎して瓶を拭かなかったから・・・。
キャンバスや板絵の下地、額縁にもKANESEI小箱にも
一番ベーシックな石膏下地、つまりニカワで溶いた石膏を
湯煎して塗ってあります。
▲パスティリア(石膏盛上げ装飾)も湯煎した石膏液で垂らし描き。
で、このイタリア語の湯煎という単語「bagomaria」
バーニョマリーアと発音しますが、バーニョはお風呂またはトイレ
マリアとは言わずと知れた聖母マリア様です。たぶん。
この単語を見るたびに湯船につかってホカホカしたマリア様とか
トイレに座ったマリア様とか(大変に失礼ながら!)
イラスト的な画像が頭に浮かんでしまう。
なぜ湯煎が bagnomaria という言葉になったのか
気になりだすと止まらない。
もしかしたらお風呂もトイレもマリア様も
全く関係ないところから来た単語だったり?
それもまた興味津々であります!
今度イタリア人に聞いてみよう・・・
忘れていない 2月22日
すっかり小箱制作ばっかりね
と思われているかもしれない・・・ですが
こちら額縁も忘れておりません。
隙間時間にガサゴソと制作。
1700年代イタリアの額縁風のデザインにしました。
外側には果物と葉。この果物のリース模様は
ぜひ一度作ってみたかったデザインなのです。
中央にはリボン巻き巻き、端先は・・・
これ何と呼ぶデザインでしょう
変形「lumb’s tongue」のような。
次はボローニャ石膏を塗り磨き、
ボーロを塗り金箔を貼ってメノウで磨いて、
ちょいと古色を付けたら完成です。
なぁに、あっという間ですよワハハ・・・ハ・・・
思い入れの有無と距離 2月05日
先日BGM代わりにテレビをつけていましたら
ぬいぐるみ作家の方のインタビューでした。
ひとつずつ違う手縫いのぬいぐるみは
個展でも即完売で、注文も数年待ちだとか。
その方のぬいぐるみ購入者は女性や子どもだけでなく
大人の男性のファンもいるそうで、
家に迎えたら家族のようにペットのように
大切にする方が多いそうです。
インタビュアーがその方に「自分で作ったぬいぐるみを
手放す(売る)のは辛くないか、思い入れはあるのか?」と聞いたところ
きっぱりと「思い入れはしないようにしています。」
と答えていらしたのが、とても印象に残っています。
わたしは小箱や額縁をまるで
自分の分身のような娘のような気持になって
それこそ思い入れ盛沢山でいるのですが、
そうではない作家は一体どんな心境で制作しているのだろう?
「あえて自分とぬにぐるみに一定の距離を取るようにしています。
名前も付けませんし、モノとして扱う。」
というようなことを仰っていました。
特にぬいぐるみなど顔があって気持ちを込めやすいものを作っていると
距離を保つのは自分のためにも必要かもしれませんね。
そしてぬいぐるみに名前を付けたり気持ちを込めるのは
購入してくださる方の特権であって、
その「余白」は作者が入っていく場所では無いのかも。
思い入れモリモリの品は、人によっては重くかんじるでしょうし。
「心を込めて作られた品」は、その品物への
愛情が豊かでリスペクトもあって、という感じですが
「思い入れのある品」って、執着とか
しぶしぶ手放すような暑苦しさも感じられる・・・
品物を作って売るからには「心を込めて」が
お客様も自分も気持ちが良いのだろうなぁ。
小箱・額縁とぬいぐるみ・・・
完成する「もの」は違うけれど、制作する気持ちや
「自作のもの」に対する葛藤は共通なものを感じました。
そうか、なるほど。
手放す前提の品とは心の距離を保つ。
偶然だったけれど、貴重なお話を聞くことが出来ました。
時間は不明だけど 2月01日
小箱についてお話するとき
「ひとつ作るのにどのくらい時間がかかるのですか」
というご質問は度々お受けします。
もちろんデザインやサイズにも寄るのですが
実は「ひとつだけ集中して作る」と言うことが無いので
ひとつ作る必要時間はわたしにも不明だったりして・・・。
下地作りはいくつかの小箱をまとめて作業します。
▲今回の下地作りは22個
ご注文の品があればまずそれを優先して、あとは
「なんとなくデザインのイメージが出来つつある」用の箱を選んでおきます。
そして下ニカワとボローニャ石膏塗りまで終えて
丸一日乾燥させて待機。
いつまで待機するかは、その箱の運命であります。
すぐにご指名がかかることもあれば
いつまでも待機しているサイズの小箱もあったりして。
デザインはず~~っと頭の中でこねくり回して
ようやく表層に上がって来たものを掬い上げて描き起こす感じです。
デザインが決まれば、ようやく石膏磨き、デザイン下描き
箔や彩色、乾くのを待って箔のメノウ磨き
仕上げ塗装、内側の布貼りで完成を迎えます。
これは簡単な場合でして、パスティリア(石膏盛上げ装飾)や
マイクロ点々装飾(細かい刻印打ち)、アンティーク風加工をしたり
作業時間は増していきます。
たいていの場合、2個同時進行します。
3個は多すぎに感じる・・・。
▲左の瓶、大きいのがボローニャ石膏液、小さいのがニカワ
そんな訳でして、ひとつ作るのに
どのくらいの時間がかかるか?とのご質問の答え
それは・・・1か月以上、場合によっては3か月、とか・・・。
流れ作業で心のこもらない制作にならないように
という期間でございます。・・・長いですよね。
できるだけお待たせしないように、励んでおります。
厄は落ちたか拾ったか 1月25日
昨年暮の大晦日間近の日
とつぜんポカッと時間が出来たので
ガサゴソと小箱制作をしていました。
純金箔を貼ってさて、メノウ棒で磨きましょう
・・・と思った時、手から滑り落ちて折れてしまったのでした。
細くてすこしカーブしているので
落とせば折れやすい形ではあるのです。
だけど、これと同じメノウ棒を折るのは2回目。
1本目は留学時に買って、数年後に落として折った。
今回のは2011年にようやくフィレンツェに行って買って、また折った・・・。
何ということでしょう。
古典技法の道具は日本では手に入り辛い、そして高価なのです、トホホ。
きっとこれは2023年の厄落としである!
そう勝手に思い込みまして。
だけど現実的に、このメノウ棒が無いのは大変に不便です。
金箔を磨くにもタイミングを逃すと
美しく輝きませんので「まさに今必要」なのです。
手元にあったゼリー状の瞬間接着剤で張り付けてみました。
このメノウ棒という箔を磨く道具、結構力や体重をかけて磨くようで
一代目は接着してもダメだった記憶があり、今回もダメ元でした。
そうしましたら、しっかり接着出来て早速使うことが出来ました。
折れ方が良かったのか、接着剤の進化か。
とにかく作業も出来て二代目復活、一安心したのでございます。
その夜にお風呂でふと思ったこと。
壊れたのが厄落としだったら、直したら厄は戻ったのか??
折角落としたのにまた拾っちゃったんだったら
ものすごく嫌だな・・・なんて。
でもまぁ、都合よく考えることにします。
厄は落ちた。直したメノウ棒はもう新たなものである!
rinascimento これぞ再生、ルネッサンスでありますよ!
・・・そう思うが吉、でございます。
その時に言うべきこと 1月22日
1月24日の水曜日から、フィレンツェに行って参ります。
いつもは帰国後にご報告でしたが
今回は先にお知らせしてみることにしました。
とは言え、イタリア滞在中もブログは予約投稿いたしますので
変わらずご覧いただけますと嬉しいです。
イタリア滞在記はまた帰国後に。(2023年滞在記も中途半端ですが。)
大学卒業後すぐに留学したフィレンツェで
一番お世話になったのが額縁工房corniceria del’agnolo の
マッシモ&パオラ夫妻でした。
修行先探しに難航したなか、受け入れてくれたのはマッシモでした。
2年間毎日毎日、半日を彼らの工房で修行させていただき
親知らずを抜くときは工房のお客様の歯医者さんを紹介してもらい
(おかげ様で緊急対応していただけた)
頭痛の時の鎮痛剤選びから食事のこと
(激安ワインを飲むくらいならビールを飲みなさい、とか!)の心配、
たまに家に招待してもらって
暖炉の炭火焼きステーキをご馳走になったり・・・
まだまだ精神的に子供だったわたしにとって
本当に「イタリアの両親」でした。
その後、彼ら夫婦にも様々なことがあって
数年前からマッシモは額縁の仕事から離れてしまい
わたしがフィレンツェに行った時も挨拶と少しのお喋りだけ
という状況だったのでした。
パオラから「残念ながらマッシモが数日前に亡くなった」
と連絡があったのは昨年12月でした。
2月に会った時 Come sta? (お元気ですか?変わりない?)と聞いたら
Si, cosi cosi… (うん、まぁぼちぼちね。)との返事でした。
「ちょっと痩せたな」と思ったものの、
その時は慌ただしい挨拶で終わりました。
それが最後になるなんて、もちろん思いもせず。
この人に一体どれだけお世話になって
支えられて、助けてもらっただろう。
その感謝はきちんと伝えただろうか。
せめてマッシモの墓前でご挨拶だけはしたいのです。
後悔先に立たず、人生はいつ何があるか分からない、
一日一日を大切に、一期一会、
そんなことは頭では知っていたけれど。
会いたい人には会っておかないといけない。
せめて感謝は伝えておかないと、と今更思っています。
その扱いの違いを比べる 1月18日
2024年、辰年です。
年男、年女の皆様おめでとうございます。
毎年の年始のご挨拶に干支の動物が描かれた
中世~ルネッサンス時期の絵を探して
自作の額縁と組み合わせたりなんかして
(図々しいけれどお許しを!ハハハ・・・)いるのですが、
今年の辰は困りました。
辰は龍、日本ではとても演技が良くて神様にもなっています。
だけど、西洋での龍(ドラゴン)、どうも悪者なのです。
毒の息を吐くとか、炎を吐いて焼き尽くすとか、確かに邪悪。
▲ウッチェッロ作「聖ゲオルギウスと竜」 1470年頃
悪者退治で槍で突かれる竜・・・これは年賀状には使えません。
鳥のような足と爪、蛇のような尻尾にコウモリ風の翼
目を突かれて血を吐く、ひどい姿で描かれています。
▲「アンティキオの聖マルガリタ」
上の絵なんて、日本の竜とはずいぶんと印象が違います。
笑っちゃうような姿。
ちなみにこの聖マルガリタはドラゴンに食べられちゃったけれど
手に持っていた十字架が竜の胃袋を傷つけたので
無事に生還できた、というお話。
そんな訳で聖マルガリタのガウンの残り布を吐出し中・・・?
方や中国~日本での龍は威厳があって近寄りがたく
この世ならぬ姿で天を駆け巡っています。
地上にいる姿って見たことが無いような?
▲海北友松「雲竜図」
日本の龍も、そうは言っても
ユーモラスな表情をしている絵が結構ありますね。
上の龍も鼻やら目つきに人間味があったりして。
頭の形も剝げたお爺さん(失礼!)みたいだし。
だけど邪悪さは微塵もない。
日本の龍は毒を吐いたり焼き尽くしたりしませんものね。
なにせ水の神様ですからね。
ドラゴンも龍も起源としては近いらしく
紀元前に蛇や爬虫類の姿から始まったとか。
蛇と言えばキリスト教では「悪」ですから
土着宗教の想像上の動物だったドラゴンが
キリスト教に追いやられて(表現が難しいですが)
徐々に「悪」のシンボルになって行ったのかしら・・・と思っています。
文化と宗教を遠くから眺めて比較するって面白い。
人間っていろんなことを考えてきたものですね。
辰年、充実した一年にしたいと思います。
整理したい 1月04日
能登地震、飛行機事故で被害にあわれました方々へ
心よりお見舞い申し上げます。
今日4日から仕事始めの方が多いのでしょうか。
今年のお正月、お節も相変わらずの内容でした。
不穏な日々の中、こんな呑気な話をすることを
おゆるしください。
お煮しめは
三浦大根、金時人参、ゴボウ、蓮根、京芋、綱こんにゃく、くわいです。
銀杏と絹サヤを飾りました。
何だかそれでも足りなくて庭の葉など摘んで。
紅白かまぼこ、二色卵、鮒の甘露煮、コハダの粟漬け。
これらは買いました。
田作り、黒豆、紅白なます、キンカン煮、百合根の卵とじ
たたきごぼう、酢蓮、鰤の塩焼き、酢タコ、鶏の松風焼
海老の含め煮 数の子、の16種。
遅れていた数の子の塩抜きも何とか間に合って一安心でした。
酸っぱい物が多い我が家のお節です。
なにせ家族全員酒飲みですので
おつまみになるようなメニューになってしまいます。
▲そして今年も頂いてしまったお年玉・・・
▲お雑煮は鴨出汁に人参とゴボウの細切り
京芋、大根、小松菜、そして丸餅。
今年のお正月はとにかく眠いです・・・体力不足。
年齢ですかなぁ。
近くの神社へお参りに行きましたら
風が強くて並んでいてもビュービュー寒い。
でも余計なものが吹き飛ばされて清められて
氏神様はご機嫌良さそうな雰囲気でした。
勝手な想像ですけれど。
午後は眠気覚ましにお抹茶と花びら餅です。
いつものテーブルで、お茶入れも篩(ふるい)の
缶のままというスタイル、お湯もヤカンから直接です。
本来なら先にお菓子を頂いてからお茶・・・の順番ですけれど
いや、まぁ、一緒の方が美味しいし・・・。
お点前も何もありませんけれども、ハハハ、美味しかったです。
毎年、なんとなく、なんとな~~く考える抱負。
2024年は、ちょっと諸々を整理しようと思います。
したい事とやらねばならない事があっちこっち散らばっていて
方向と覚悟が定まらぬ。
自分のキャパシティも変化しているようなので確認したいですし。
仕事も日々の生活も頭の中も少しずつ整理して
やめられる事を「覚悟を決めてやめる」、そして
したい事とやるべき事を絞って注力できるようにしたいと思います。
・・・思います。いや、します、ハイ。
あけましておめでとうございます 1月01日
世界が変わったぞ 12月28日
最近なにか、「おお、これは!」と思われたことはありますか?
わたしが「こ、これは世界が変わった!」と思ったもの
・・・それは0.2mm芯のシャープペンシル。
「また大げさなことを言っている・・・」
と思われるでしょう?でも本当なのです。
▲その名もオレンズネロ。極細の芯でも折れにくい工夫がされている。
アトリエLAPISの生徒さんが使っていらっしゃる様子を見て
「こんなものが世の中に存在しているとは!」と驚きつつ
すぐさま購入しました。
ちょっとお高い・・・のですけれど
その細さと繊細さ、書き易さといったらありません。
トレーシングペーパー(わたしが描くと
線が太くなりがちな紙なのです)の細かい下描きだってお手の物!
今まで0.3mm芯を使っていましたが
別世界といいますか、壁の向こう側な感じ。
0.3mmでは描き切れなかった部分、
なんだかモチャッと潰れてしまった部分も
0.2mmですとハッキリ描ける。
変な例えですけれど、目が悪かった人が
初めて眼鏡をかけたような感じと言いましょうか。
0.1mmの差は大きいのです。
たしかにちょっと折れやすいけれど
ペンも色々と工夫してくれています。
Bの芯でも慣れると折れずにスイスイ。
一度手にしたら、もうこれ以外ない。
久しぶりに「おおおぉ・・・!」と感動した品でした。
いつ発売になったのか、もう以前からあったのか。
きっと有名な品なのでしょうけれど
とにかくシヤワセ~な気分になる書き心地。
もし細かい作業がお好きな方がいらっしゃったら
0.2mmシャープペンシルをぜひ。
Buone Feste 2023 12月25日
クリスマスの月曜日でございます。
皆様いかがな年末をお迎えですか。
海外のこの時期のご挨拶として「Season’s Greetings」
(イタリア語だと 「buone feste 良い祝日を」になると思います)が
ずいぶんと増えましたね。
クリスマスはキリスト教の大切な祝日ですから
クリスチャン以外の人には冬至前後に
「これから日が長くなって、春が近づいてくるよ。
新しい季節を迎えよう」と言う意味を込めて
挨拶する方が良いのでしょうね。
日本ではあまり深く考えることなく
楽しいイメージのクリスマスですから
日本人同士でメリークリスマス!と言いあうのは
なかなか素敵なことだと思います。
イタリアの友人知人で、クリスマスの礼拝に行く人は・・・
ひとりしか思い出しません。
他の人たちは、家を少し飾って、家族で集まって食事して
プレゼント交換まではするけれど、と言った感じです。
特に都会の人たちはそんな感覚が多い様子。
今の時代は宗教について話す機会も随分と減りましたしね。
・・・なんてことは、まぁ置いておいて。
皆様、今年のクリスマスも、どうぞ暖かくしてお過ごしくださいね。
良い写真を撮りたい 12月18日
最近つくづく、ブログやインスタグラムにはとにかく
「美しくて目を惹く写真」が必要と痛感します。
大量に流れるSNSや情報を携帯電話で見るとき
流し見していることもありますが
その中で手を止めて見てもらうには、まず写真。
いつ、どこで、誰が見て下さるか分かりませんから
発表するからにはより沢山の方に「おや」と思って頂きたいのです。
それにしても小箱や額縁の金箔・水箔(銀色)を
撮影することも難しさと言ったらありません。
ギラギラしすぎず、自分の影が映り込まず、色も美しく
背景から浮かず、そして美しくて目を惹く写真。
・・・撮りたいけれども。
▲ひとまず暗くすれば雰囲気が出るだろう、という算段・・・
雨戸を閉めて、鏡台の上を片付けて小箱を並べ
角度やら背景を考えて(散らかった背景をいかに隠すか)
右往左往します。
なんだか、こう、釈然としない。
大学の卒業制作で黄金背景テンペラ画を描いていた時
製作途中の記録写真を撮るときの苦労を思い出します。
鈍い鏡のような金箔面に自分が映り込まない角度で撮影したり。
卒制展のカタログ写真をプロの方が
順番に撮影してくださるのですが、
その時にも「うぎゃー、金箔かぁ・・・」と言われた記憶。
美しい黄金色に撮影ってプロでも面倒なのですね。
箔を使っていない彩色小箱も
ちょっとした影や角度で表情が変わるのですから
もうどうしたもんか、どのポイントからがベストか
沢山撮って比べるしかありません。
▲ドイリーなんか敷いてみちゃったりなんかして。
重い一眼レフはもうすっかりお蔵入り
もっぱらiPhoneで撮っています。
でもなぁ、やっぱり最新機種が欲しいな
いや、ミラーレス一眼が良いかな。
いやいや、そもそも写真撮影の腕とセンスの問題では?!
むーんむーんと唸りつつ、今日も母(わたし)は
娘たち(小箱)のお見合い写真を撮る気持ちで励んでおります。
広がる夢のレパートリー 12月14日
いままではオーダーのご依頼といえば
ほとんど額縁だったのですが、
最近ようやく小箱のオーダーも頂けるようになりました。
谷中の箱義桐箱店での展示会でも
いくつもご注文を頂くことが出来ました。
お客様は皆さん「いつでも良いですよ
気長に楽しみに待っています」と仰ってくださるのです。
なんとも有難いお言葉で恐縮です。
とは言え、やっぱり出来るだけ早くお届けしたい。
まずはともあれ、着手します。
上の写真の大きな箱(とはいえB5より一回り小さい)は
指輪ケースです。
蓋に透明なアクリル板が入っているので中が良く見えて便利!
小箱装飾は蓋がメインですので
このスタイルの箱は目にとめていなかったのが正直なところですが、
なんのなんの、側面もたっぷり色々細工できますね。
奥の長細い青い小箱は乳歯入れ。
なので可愛らしい歯のイラストが印刷されています。
この箱、じつは3段のお重のようになっています。
中も細かく仕切られていて、とにかくかわいい。
小ぶりのピアス入れとか、小さな貝殻標本にしたり
想像が膨らみます。
これはご注文の品ではなくて、新しい試みで作る予定です。
完成したらご披露させてください。
指輪の箱、18個のマスに小さなクッションがペアで入れてあって
指輪を立てて入れられるようになっています。
このクッションはなんと箱義の上野本社の社員さんの手作りなのですって!
桐箱ふくめて正真正銘メイドインジャパンでございます。
作業のために一旦外します。
失くしたら大変!なので、きっちり保管。
本当に、小箱と一口で言っても箱義さんには様々な小箱があります。
(大きな箱もありますよ!)
これからレパートリーをさらに増やしたら
もっと楽しくなる!とワクワクしています。
これにておさらば 12月04日
「禅の友」12月号です。
2023年の1年間、毎月の表紙に使っていただいた
「禅の友」の最後の号。
有終の美(自分で言っちゃう!)を飾るのは、この額縁です。
▲乱視かな。いいえ、サイズが近いだけです。
背景は緑を感じるグレー、タイトル文字は濃い緑と白
12月の表記は抑えた赤。
そしてニヤニヤと嬉しそうに笑う額縁・・・
派手なようなシックなような、とても素敵な表紙です。
毎号ながら額縁と色の組み合わせ、バランスには
編集の方のセンスに唸らされております。
それもこの12月号でお終い。
▲ずいずいっと!
1年間、12回って長いし結構な回数だな!と思っていましたけれど
終わってみるとまだ続けたい気持ち満々です。
なにより編集者Mさん、フォトグラファー浅野さんと
お目にかかる機会が遠くなって寂しい。
昨年にこの件のお話を頂いてから楽しい事ばかりで
「禅の友」には大変感謝しております。
▲11月はドタバタでご紹介できなかったのですが
ことわざ額縁を使っていただきました。
この淡い柿色の背景色と渋い文字色も絶妙・・・
来年はイラストが表紙になるそうで
雰囲気もがらりと変わることでしょう。
・・・ううむ、なんだかジェラシー・・・
いやいや、この1年間の経験を基にご縁はさらに広がる予感ですから
ジェラジェラしている場合ではありません。
やりますぞ、張り切っております。
殊の外楽しく、そして有難かった「禅の友」2023年の12冊は
わたしの一生の宝になりました。
ありがとうございました。
KANESEI小箱史黎明期 11月30日
居間にある本棚を眺めていたら
すっかり忘れていた小箱が目に留まりました。
このふたつ、かれこれ・・・いや
思い出せないくらい昔に、初めて作った小箱です。
いつも家族で行く平和島骨董市には
箱義桐箱店さんも出店していて
アウトレットの小箱を買って眺めていたのですが
古典技法で装飾してみようと思い立って
いくつか作った内のふたつ。
なぜ手元にあるかと言うと
不出来だったからなのです・・・。
自分ではあまり見たくない物でしたが
家族は大切に(それなりに)して
本棚に置いてくれていたのですね。
▲和柄、輪違模様
この輪違は側面に下描きの汚れが灰色に残ってしまっている。
▲鳥模様。金はすべて純金箔ミッショーネ。
これも下描きのカーボン紙の黒い線が見えて汚い・・・
輪違小箱にいたっては開けない。
このころはニス(今はラッカー)を使っていたので
無理にこじ開けても壊れるだけでしょう。
もう開くことは無い感じです。
鳥の中は真っ赤、輪違の裏は真緑
塗りムラもひどくてトホホな仕上がりです。
▲側面にはラテン語、底面付近に金のライン。
でもデザインは悪くないな・・・なんて思うのでした。
この頃から好みは結局変わっていないということですかな。
好みに変化がないことが良いのか悪いのか
・・・それはさておき。
自分では忘れたいような不出来作品も
こうして取っておくのも色々思い出したり
考えたりできて悪くありませんね。
この小箱ふたつもまた、わたしの「小箱史黎明期」
(大げさ)を見せてくれたのですから。
今はもっと上手に作れるようになりました。
・・・100個も作れば上達もしますね。
これからもっと上手に作って行こうと思います。
穴から出る日は近いのだから 11月27日
谷中の箱義桐箱店での展示会が成功裏に終わって
気づけばもう何日も経っています。
だけどまだ心身ともにボォォ~ッと気が抜けたままです。
いやはや。
そんなに精根詰めた自覚は無かったのですけれど
根が引き籠りの低空飛行なので
それなりに頑張ったのでした。
やるべきことは山積み。
世の中皆さん同じように日々忙しさに追われている。
わたしだけじゃない、
やるべきことはさっさとやった方が良い。
「そんなこたーわかっておる!
それが出来れば苦労は無いのじゃ!」と
駄々をこねくりまわす自分をどうにかなだめつつ
家族には「山のごとく何もしない」
(つまり役立たずと言いたいみたい)と
嫌味を言われつつ甘えて過ごしております・・・。
▲会期初日に頂いたお花はキラキラでした。
時計の音がカチコチ聞こえて
忘年会のお話もチラホラして
でもまぁ、何とかなるのですよ。
次の額縁制作に向けての図面やら
ご注文頂いている小箱の準備やら
ガサゴソと再開しているのですから。
そのうち誰かにお尻を叩かれるか
どっこいしょと自発的に持ち上げるか分からないけれど、
とにかく穴から這い出るのは分かっているのですから
今はもう少し穴の中でボォォ~ッと過ごします。
秘密の小箱展 終了いたしました 11月20日
11月9日から始まりました「秘密の小箱」展は
昨日19日に無事終了することが出来ました。
お忙しい中お越しくださりありがとうございました。
またお買い上げを頂きありがとうございました。
いよいよ本格的な晩秋に入り
寒かったりお天気の悪い日もあったのですが
遠くから来てくださった方、そしてインスタグラム広告を見てお越しくださった方
そしてお客様の投稿(エックスやインスタグラム)をご覧になって来たと話してくださる方
「禅の友」のお知らせを見てきたよ、という方々など・・・
本当に沢山の皆様が小箱に興味を持ってくださり
見に来ていただく機会になりました。
▲初日朝に展示を終えたところ。
奥のテーブルには「禅の友」バックナンバーも置かせていただきました。
去年の初めての時は友人知人が来てくれるので
気楽と言いましょうか、和気あいあいだったのですが
今回は圧倒的に始めてお目にかかる方が多く
それも「小箱を見る為」に来て下さるお客様ですので
技法の説明など少ししましたけれど、あとは
お邪魔をしないように控えている時間の方が長かったようです。
自分が作ったものを、こんなに喜んで手に取り
真剣に見て下さる方々がいらっしゃる・・・
その幸せを噛みしめ、大きな励ましを頂戴していました。
来年2024年には、もしかしたら初めての場所で
小箱の展示会をする機会が頂けるかもしれません。
武者震いでございます。
気持ち新たに、更に楽しく小箱制作に精進いたします。
この場でのご挨拶で恐縮ですが、皆様にお礼申し上げます。
ありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
ジョヴァンナのお家は 11月09日
先日完成しましたギルランダイオ
「ジョヴァンナ・トルナブオーニの肖像」
卵黄テンペラの部分模写の額縁を作りました。
この絵は毎年暮に開催されます
「小さい小さい絵」展に出品する予定です。
▲先日完成した部分模写
この「ジョヴァンナ・トルナブオーニの肖像」
オリジナル作品は黒と金の額縁に納められておりまして、
じゃぁシンプルながら同じ色の額縁にしましょう
と決めました。
木を組んで下ニカワを塗り
ボローニャ石膏を塗り重ねまして。
さて、いつもならここから石膏地を
紙やすりで磨いて整えるのですが、
今回はこの作業をしませんでした。
わたしの額縁師匠であるパオラ
(フィレンツェの額縁工房経営)によりますと
ルネッサンス時代の一部の額縁には石膏地を磨かずに
そのまま装飾をしているものがある、とのこと。
たしかに・・・
ルネッサンス当時に今のような紙やすりは無い訳ですから
(鮫の皮で磨いていたとか)今でさえ大変な石膏磨き
当時の職人のご苦労は推して知るべし。
その後、美術館や教会で観た額縁は
確かに磨かれていない額縁もありました。
黒など強い色であっても柔らかく暖かな印象で
新たな発見でした。
ギルランダイオは15世紀末に活躍した画家ですから
このスタイルの額縁であっても良いのではないかな
と思い立った次第でございます。
さて前置きが長くなりました。
なにせ塗りっぱなしの石膏・・・ということは
筆跡が丸見えな訳でして、やはりそれなりに
「美しく塗られた石膏」である必要があります。
石膏液の濃度、温度を整え、筆も吟味して
手早く丁寧に塗り重ねまして・・・
乾いたらすぐに赤色ボーロ、内側の端先には純金箔を貼り磨き。
あとはすべて黒にしました。
上の写真、磨いていない感じが見て頂けるでしょうか。
なんとなくニョロッとしているというか
液溜まりの跡があったり。
力強さや動きが感じられるような。
なるほどなるほど。こうなるのですね・・・と言う感想です。
お好みや額装する作品によりますが、これはアリです。
▲絵を入れてみる。
ふむ!ルネッサンスっぽいかも!フフフ。
いや、だけど、く、くらい・・・。
絵の背景も額縁も黒で、ちょっときつい印象かも。
マットに暖かい色の布を貼ってみようと思います。
ひとまず「ジョヴァンナのお家」が出来てほっとしております。
宣伝広告って・・・! 11月06日
少々しつこくお話しております通り
11月9日から小箱の展示会をする予定です。
昨年が第1回目で、友人知人はじめ
沢山の方々にお越しいただき
そしてお買い上げいただき
とても有難く幸せな展示会になりました。
さて、今年は第2回目です。
今回もまた友人知人にしつこくDMをお送りし
こうしてブログでもワーワー騒いでおります。
だけど2回目って正念場です。
いや、1回目が特別なのですよね。
なにせ初めてだから皆さん来て下さるけれど
以降は友人か、本当に興味を持って下さる方かだけ。
閑散とした会場で、ひとり指をモジモジさせる恐怖!
そんな訳で、インスタグラムで今回の
「秘密の小箱展」の広告を出してみました。
▲この美しい写真は浅野カズヤさん撮影
インスタグラムをお使いの方はご存じと思いますが
写真をメインに文章も添えて投稿すると
「この投稿を宣伝」というボタン(?)があって
そこをクリックして日数と一日当たりの費用
(00円くらいから数万円まで。金額によって
表示される範囲と回数が増える)を自分で決めたら
後はメタ社が良きに計らって・・・
つまりこんな小箱に興味を持って下さりそうな世界中の方々に
インスタ上で宣伝してくれるのです。
今回わたしは10日間6000円というプランで申し込みました。
これが安いか高いか、はっきり言って分かりません。
自分で自分を宣伝することなんて、まず無い。
広告とはテレビ、新聞やネットで見せられる物。
・・・と思っていました。
自信満々で作っている訳ではなくて
展示会もデパート催事も必死で
恐怖心と戦っているような状態です。
だけど、自分で作った小箱を眺めたら
ニヤニヤするくらい嬉しくて気に入っているのも本当なのです。
パアッと明るく「これ、見てみて!」と
自分で言える明るさが欲しい。
見て欲しい、だけど見られるのが恥ずかしい、この矛盾。
つまり覚悟が足りないのですよね。
(本当に恥ずかしいならブログだって書かないはず!)
展示会を開催する機会を頂いたからには!
ひとりでも多くの方にKANESEI小箱に
興味を持って頂くのが目的である!
▲今年最後の月下美人が、なぜか明け方に咲き始めて朝日を受けて満開。
こんなことは初めてでした。幸先の良い証と思うことに。
アワワ・・・
謎の月下美人で一息つきまして。
先日からこの広告が始まったのですが
始めた当日は「なんだ、こんなものか」と言う程度の
反応でしたが、翌日から、ちょっとびっくり。
フォローしてくださる方が少しずつ増え
展示会の問い合わせもあったり
今までご縁が繋がりようもなかったような方々にも
見て頂いていることが実感できたのでした。
なるほど・・・やってみないと分からない。
就職面接も受けたことが無く
自己PRなど経験ゼロなわたしですが
自分の広告を出す小さなチャレンジ
(と言うほどでもないけれど)をしてみて
ちょっと楽しかったのでした。
とは言え、世の中そんなに甘くない。
願わくば、この広告をご覧になって
展示会に来て下さる方が
ひとりでもいらっしゃいますように。
マスクする?しない? 11月02日
先日、インフルエンザの予防接種を受けました。
以前は予防接種なんて御免こうむりたい・・・と思って
(そしてまんまと新型インフルエンザ等に感染して)
いましたが、コロナ禍以降
ワクチン接種に慣れたような気がしています。
▲コンスタブルっぽい雲の写真が撮れた。
秋になって、街でマスク姿の方々を見かける数が
ずいぶんと増えました。
アトリエLAPIS(古典技法教室)の
生徒さんマスク着用率は3~4割くらい。
友人からは、子供たちの学校の学級閉鎖やら
家族内感染やら、色々と話を聞きます。
そしてこれらはインフルエンザだけではなくて
コロナも含まれている訳です。
さりとてコロナワクチンは副反応が辛すぎて
(それも回を重ねる毎に酷くなる)
5回目接種も有耶無耶にしています。
否応なく接種しなければならない方々もいらっしゃるのですから
わたしは選べるだけ楽なのですが・・・。
▲サンシュユの実はヒヨドリのおやつになる。
自宅での作業がメインでほぼ引き籠りのわたしですので
「まぁいいか」と思っておりましたけれど、
アトリエLAPISの皆さん、友人知人
そして同居する家族を考えて、
せめて教室や移動時のマスク着用を再開しようか
どうしたもんか・・・と右往左往しています。
するべきと思うならする、必要ないと考えるならしない。
それで良いのだけど。
▲伊勢海老っぽい雲も撮れた。
イタリアはじめ諸外国はどうなのでしょうか。
やっぱりマスクなんて過去の話なのか
コロナで意識が変わった人もいるのか。
興味深いところです。
気が急いても 10月23日
秋になりましたね。
我が家の庭も秋真っ盛りです。
▲今の主役は藤袴
▲柿の食べごろはもう少し先
ニュースでは世界中の不穏なことばかり知らせていて
でもわたしの周りのごく狭い世界は平穏無事な毎日で・・・
ありがたく思うと同時に申し訳なさも感じる。
じゃあ何か少しでも動けば?と思うものの、
その気力体力も追いつかない。
こんなことをブログに書くこと自体が
偽善と取り繕いだと分かっているけれど。
気持ちは急く一方。
いろいろなタイムリミットは目前。
2024年も、もうすぐです。
色と形、どっちで分ける? 10月19日
完成した小箱は不織布の袋に入れてから
箱(いわゆるお道具箱サイズ)に入れて
収納しています。
今のところ、このお道具箱は5つあって
それぞれに仕分けして入れるのですが・・・
さて、サイズ別にするか、装飾技法別、つまり色別にするか。
これがいつも迷うところなのです。
たまに棚卸のようにすべての小箱を出して
価格確認や在庫を数えたりして
その後の片づけ時に毎度迷うのです。
一説によると、形で分類する人と色で分類する人には
それぞれ傾向があるのですって。
色別は女性に多いとか、形別の人は感覚の視野が広いとか。
諸説あるでしょうし、分類する物(小箱か服か食べ物か、
あるいは細胞か星か・・・分からないけれど。)
にもよるでしょうけれど、面白い考察です。
▲これは豆小箱のみ。サイズは同じ、でも色は別々・・・
▲こちらは色別。でもサイズはばらばら。
こうして見ても悩ましい。
色別のほうが、わたしはしっくりくるような気がします。
でも在庫管理としてはどちらが効率的なんだろう??
ううむ。
「狙いの一つをすぐに取り出せる方」が
効率的ということなのでしょうけれど
これはわたしにとっては同じようです。
(自作ですし数も限られますし。)
または制作順とか価格順、お気に入り順とか・・・?
これはなんだか小箱たちに優劣をつけるようで
気分が盛り上がりません。
そんな訳で、結局今日も釈然とせずに
色別とサイズ別の混ぜこぜ保管になっています。
小さな相棒たち 10月16日
とても細か~い彫刻をする仕事のご依頼を頂いてから
いったいどうしたもんかと考えていたのですが
この細密彫刻刀を手に入れて、どうにかこうにか。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが
パワーグリップというシリーズ。
一番細いサイズで刃の幅は1.5mmです。
とても優秀な彫刻刀です。
細かい部分にも小回りがきいて、華奢だけど丈夫。
上の写真、左の1本の丸刃だけ以前から持っていたのですが
今回は5本買い足しました。
このパワーグリップを相棒に
2ミリ幅の葉っぱに溝を並べて入れております。
ハズキルーペをかけてLEDライト付きスタンドルーペを覗き込む・・・
総動員してガサゴソ。
日暮れとともに目が見えなくなってくるのは年齢です、ハハハ!
笑い事じゃないのですがね。
大丈夫、出来ます。額縁修復師の名に懸けてやりますぜ。
・・・と、自分を励ましております。
グオオ・・・
パワーグリップ、お勧めです。
二十歳の女の子の肖像 10月09日
ギルランダイオ作「ジョヴァンナ・トルナブオーニの肖像」
部分模写ができました。
サイズは10センチ×6センチ
名刺のひと回り大きいくらいのサイズです。
オリジナル作品は77センチ×49センチ
スペインの美術館にあります。
▲わたしの模写は・・・
うむ、すみません。お許し下され。
オリジナルの表情より子供っぽいような、
のんきそうな眼差しになってしもうた・・・
▲画像はwikipediaより
若く艶やかな肌、気品ある表情を
ギルランダイオはさすが美しく表現しています。
彼女、ジョヴァンナさんが亡くなって
2年後に描かれた肖像画だそうです。
まるでモデルのジョヴァンナを目の前にして
描いたみたいに感じていましたので、驚き。
名家アルビツィ家に生まれ
18歳でトルナブオーニ家に政略結婚で嫁ぎ、
19歳で第一子を産み、20歳ですぐ第2子、
そして亡くなった・・・二十歳の女の子の肖像。
どんなことを考えていたのかな
何が好きだったのかな、色々想像します。
わたしの模写のような、のんきで
子供っぽい表情をする時間が、彼女にもあったのかな。
政略結婚も、短い人生も、傍から見たら
不自由で辛い人生なのではと感じるけれど、
本当はどうだったんだろう?
ジョヴァンナ本人にしか分からない事ですけれどね・・・。
この肖像画はトルナブオーニ家から
パンドルフィーニ家に渡った時期もあったとか。
トルナブオーニもパンドルフィーニも、そしてアルビツィも、
今もフィレンツェ中心部にある有名な通りの名前です。
Via de Tornabuoni, Via dei Pandolfini, Borgo degli Arbizi ・・・
1400年代後半、その頃はそれぞれトルナブオーニ家
パンドルフィーニ家、アルビツィ家の
屋敷があった通りなのでしょう。
ジョヴァンナやギルランダイオが通ったであろう道を、
視線を少し上げれば当時と変わらない建物が続く道を、
600年後を生きるわたしも歩くことができる・・・
だからフィレンツェから離れられません。
手に取って開くまで 10月02日
「禅の友」10月号です。
今月号の表紙は小箱軍団の登場となりました。
淡い桃色に臙脂色のタイトル文字
「あんこっぽい色で美味しそうだな・・・」と思っていたら
編集さんは「イメージは『しるこサンド』」と!
そこに金色と銀色、すこしの緑色の小箱が散りばめられていて
なんだかとてもかわいらしい表紙~裏表紙になりました。
読者の皆さんからのご感想が気になって
今からちょっとドキドキしています。
9月のお彼岸に我が家もお墓参りに行きまして
帰りのご挨拶時に冊子を頂きました。
真言宗のお寺でして、「光明」という季刊誌です。
今年、曹洞宗月刊誌「禅の友」に掲載して頂くようになって
にわかに「光明」も真剣に拝読するようになりました。
(今までは流し読み・・・罰当たり!)
季刊誌と月刊誌の違いはあるけれど
同じようにお檀家さんに配布する冊子なので構成は似ています。
サイズもおなじ。
ご本山便りから始まって仏典の解説
行事や季節についてのコラム、
読者からの投稿(俳句や詩、感想)、エトセトラ・・・
だけどそれぞれの編集部の好みや傾向があって
取り上げ方や雰囲気の違いが面白いのです。
曹洞宗「禅の友」の方はデザインが若々しくて
手芸やお料理などもあって女性的。
真言宗「光明」は、季刊誌だからかページ数も多くて
オールカラーで見やすい。
文章が多めで、読み物感が強い・・・
(ちなみに表紙は風景や仏像写真)
改めて考えてみれば、冊子を手渡された方が
「読んでみようかな」と興味を持って下さるようにするには
表紙って責任重大ですね。今更ですけれど!
なにせ無料配布(もちろんお寺が購入して
配布してくださるのですが)されるものですから、
読まれずにそのまま・・・なんてことだってある訳ですもの。
微力ながらKANESEIの額縁と小箱の
表紙が皆さんのお目に留まり、
ページを開くお役に立っていますように、と願います。
ギルさま 9月25日
ルネッサンス期にフィレンツェを中心に
活躍した画家、ドメニコ・ギルランダイオの作品
「ジョヴァンナ・トルナブオーニの肖像」の
テンペラ画模写をはじめました。
オリジナル作品は腰から上の姿ですが
わたしは顔だけアップで。
▲完成までの道のりはまだまだ長い。
ギルランダイオの作品は、フィレンツェの教会や美術館で
またローマのヴァチカン美術館でも
観ることができますが、
いわゆる「すごい人気作家」ではありません。
今回模写に使っている画集はフィレンツェの
美術専門古書店で2018年に買いました。
その滞在時、他の古書店でギルランダイオの
画集が見つからなかったのですが
この店主いわく「そうね、ギルランダイオって
そんなに有名じゃないから。」と。
わたしがええっと言うと、申し訳なさそうに
「ほら、ボッティチェリやダ・ヴィンチのように
人気がある訳ではないでしょ。」と言いつつ
この本を探し出してくれたのでした。
言われてみればそうかも。
かの有名なヴァザーリ著「芸術家列伝」にも
書かれていません。
ギルランダイオの作品を見ていて感じるのは
穏やかだけどきちんとしている。
レオナルド・ダ・ヴィンチのような深遠さや謎、
ボッティチェリのような陰りのある優美さ、
フラ・アンジェリコのような静謐な明るさ・・・といった
「大きな特徴」は少ないかもしれません。
だけど、美しく正確に並んだ筆跡
(クリヴェッリのような神経質な硬さは無くて)
モデルとなった老若男女誰にでも
同じ穏やかな眼差しを向けている、
と言った雰囲気です。
変な言い方ですが「きちんとした大人」な
人柄だったのではないかと想像できるような。
絵から不機嫌さ、憂鬱さを感じさせないというか。
穏やかで真摯な人柄、でもそこはかとなく
「俺もやってやるぞ」「俺だってすごいんだぜ」感も
きちんと出ている。
・・・わたしの語彙力が足りなくてうまく説明できない。
▲ギルランダイオの自信溢れる自画像。46歳で亡くなっている。
好きな画家をつい「フラちゃん(フラ・アンジェリコ)」
「ボッちゃん(ボッティチェリ)」などと
親しみを込めて呼んでしまうのですが、
ギルランダイオの画集を見れば見るほど
「ギルちゃん」ではなくて「ギル様」になってきました。
▲髪は難敵・・・つづきは明日。
いま模写している原画はマドリードにあるので
実物を見るのは難しいけれど、
またフィレンツェに行ったときには
サンタ・マリア・ノヴェッラ教会で
彼のフレスコ画を見て、
墓所にご挨拶しようと思います。
何て呼んだら良いですか in English 9月21日
インスタグラムにて、自作の小箱や額縁の写真
(たまに謎のご飯写真)と一言コメントを出しています。
ブログは文章メインで日本の方々に見て頂いていますが
インスタは海外の方の方が多いかも?といった感じです。
▲先日作った小箱。他にやること山積みなのに、逃避制作。
インスタでは、まず拙いイタリア語、それから日本語
そして変な英語と3か国語でコメントを書いています。
(イタリア語、英語は間違いだらけだけど、
書かないよりずっと良いだろうよ!と開き直っております・・・!)
そうすると、インスタだけでやり取りする知り合いが出来ました。
アメリカ、スウェーデン、ドイツとか・・・
もちろん日本とイタリアにも。
▲パスティリア(石膏盛上げ)が乾いたら線刻。鹿エンブレム風・・・
今まで英語で小箱のことを small box
または casquette と書いていました。
今年2月のフィレンツェ滞在で「小箱は cofanetto とも呼ぶ」と知ってから
英語でも素敵な呼び名があるかしら、と思って調べましたところ
キャスケットcasquette にたどり着いたのでした。
▲赤ボーロに純金箔、メノウで磨いて金ぴかに。
放置していた豆小箱もついでに。
先日、あらためてふと
「小箱って英語で何て書けば最適だろうか」と思いました。
だいたい、キャスケットという言葉で小箱を指した時
英語を母国語とする方々にどんなイメージを
持っていただいているのか、気になり始めました。
▲金箔を磨り出して、ワックスとパウダーで古色付け。たのしい逃避・・・
インスタでメッセージのやり取りをしているアメリカのお二人に
「small box と little box と casquette、どの呼び名が良いと思う?」
とお尋ねしました。
そのお答えは、一人の女性(30代くらい)は
「small box が良いと思う!」とのこと。
ふむふむ。
もう一人の男性(多分40代)からは
「それは良い質問! small box が一番良いと思うよ。
というのも、casquette は小箱を指すには一般的ではないし
一部の人は棺を指すときにも使う言葉だからね、
イメージを考えるとお勧めしない。」でした。
きっとこの方、わたしが以前に使っていた「casuquette」の単語を見て
気になっておられたのかもしれません。
キャスケットという単語が棺も指すことは
わたしも読んではいたのですけれど、やっぱりそうなんだ
そりゃそうか・・・納得でした。
▲さぁ、完成しましたよ。諦めて仕事に戻りなさい、わたし・・・
いやはや、お二人に尋ねて良かったです!
腑に落ちました。
単語ひとつでも微妙なニュアンスは違います。
イメージは大切ですからね・・・。
と言う訳で、本日からわたしの小箱は
small box一択 で一件落着!でございます。
ああもう、倒れる3秒前 9月14日
ご注文いただいた額縁を作っているとき
何が一番怖いかって、サイズ間違いです。
材木を切った時点で間違いに気づけばまだ良い方で
(材はもったいないけれど、他でも使える場合があるので)
ある時など金箔作業も終わって完成間近
仕上げの時に気づいたこともあります・・・。
納品後に発覚!という最悪パターンは
まだ無いのが不幸中の幸いですが
それもいつかやってしまう恐怖がいつもあります。
いや、それにしても気づいた時のショックと言ったらありません。
納期が間に合うか、材料が足りるかなど
もう本当に心臓がぎゅっとなる。
そして大変にがっかりします。
自分一人でやっておりますので
失敗のすべては自分のミスです。
慰めようも無いのがまたトホホなところ。
▲火球?! いえいえ、自衛隊の大きなヘリコプターでした。
こんなことを書き連ねましたのも
いま額縁内部に簡単な細工加工をして
サイズ調整を入れる額縁を作っておりまして、
塗装済み、あとは仕上げの段階なのですが
なんだかちょっと心配になってサイズのメモを見たのです。
そうしたら額縁が1センチ大きいじゃないの!
ちょ、ちょ、ちょっと待って・・・
血の気が引いて、もう一度きちんと確認しましたら大丈夫
これで合っているのでした。
最初のサイズはご相談の最中のメモでした。いやはや。
ああ、また寿命がすこし縮みました。倒れそう。
まだ動悸がしています。
▲「天高く馬肥ゆる秋」は間近
わたしが誰かと一緒に工房経営や制作をしない
したくない心理はこれなのでしょう。
自分がミスがほかの人の迷惑になる、ということ。
こう書くとまるでわたしが謙虚な人間のようですが
そうではなくて
いい年齢になっても乗り越えられていない
小心者のプライドと言ったところです。
大勢で出来る仕事の規模や達成感などと
自分一人でする小さな仕事と安心感、
どっちも善し悪しがあって、
結局のところ向き不向き
好みなのだろうなぁと思っています。
なににせよ、サイズ確認は気を付けよう。
押忍。
カードうきうき 9月11日
8月の半ばのいちばん暑いころ
「禅の友」編集のMさんと
フォトグラファーの浅野カズヤさんが
我が家へお越しくださり
額縁と小箱の撮影をして頂きました。
曹洞宗の月間冊子「禅の友」の2023年
一年間の表紙にKANESEIの額縁を使っていただくのも
あと3回になりました。早いものです。
撮影目的のメインはもちろん冊子用の写真なのですが
編集Mさんのご厚意で、浅野さんが撮ってくださった写真を
わたし個人でも使うご許可をいただきました。
そんな訳で!
嬉々としてKANESEIのショップカードを一新いたしました。
▲実物カードは色がもっと綺麗なのだけど・・・
なにせ写真が素敵すぎて1枚に決められず
2種類のカードを作りました。
裏面にはインスタグラムやネットショップの
QRコードを入れています。
以前は自分で撮った写真を市販の名刺用の紙に
プリンターでガタゴトを印刷していました。
紙はペラペラだし印刷のキメも荒くて
おまけにカードの周囲は切り取り線の
ミシン目跡でデコボコ・・・という
手作り感溢れすぎのカードでした。
今回はプロによる写真で印刷も外注!
(レイアウトは自分ですけれど)
これで自信の持てるカードが出来ました。
うれしい。
プロの手をたくさん通って完成したカードを見ると
「自分で作った小箱」のカードなのに
ちょっと遠く感じるというか
まだ他人事に見えるというか。
これから慣れるのでしょうね。
張り切りすぎて100枚ずつ
合計200枚も作ってしまいました。
まずはネットショップでお買い上げくださった方へ
そして11月の箱義桐箱店谷中店での展示会
「秘密の小箱展」で、じゃんじゃんお配りしようと思います!
手抜きはたまに 9月07日
先日、美容院に行きました。
なんと8か月ぶりでした。
以前はもう少し自分のお手入れも色々していたのですが
頻度や使うお金も減る一方でした。
髪を長くしているとどうにかなってしまうので
つい美容院も後回しにしておりましたけれど
帰り道の爽快さと家族の笑顔で
手抜きをしていたことに気づいたのでした。
要るものと要らないものを選別するのが苦手で
整理整頓はわたしに欠ける才能である!
・・・と自他ともに認めておりますが
コロナ禍で否応なくシンプルになった面もあります。
人間関係ですとか、恐怖心ですとか。
まぁいいや、まぁ仕方がない、
なるようになるし、なるようにしかならない。
と思えるようになったのは、この2~3年のことです。
年齢的な事もあるかもしれませんけれど。
でもね、シンプルと手抜きは違うのだよ!
・・・いやぁ、今更ながらですね。
心身も生活もシンプルに。
でも手抜きはあんまりしないで(たまにはあり)
余裕をもって丁寧に。
これが出来れば良いな、と思います。
年末にはだいぶ早いけれど
来年の抱負にしちゃおうかな?
いや、今から目指せば良いのですよね。ハハハ。
考えながら生きる 9月04日
ででーん
ひょっこり
「禅の友」9月号です。
立秋とお盆を過ぎて日もだいぶ短くなって
「禅の友」表紙背景もすこし深い色になりました。
この額縁は「サンソヴィーノ」スタイルと呼ばれるデザインで
渦巻きとウロコが特徴です。
例によって摸刻でして、オリジナルは1500年代後半に
北イタリアで作られたものです。
日本人の「死」に一番近い宗教でもある仏教
(もちろん違う考えの方々もいらっしゃいます。)
この「禅の友」でも、自分や家族の死を迎えるにあたっての気持ち
ひとりで物事を考え整理する時間の大切さなど
毎号に死生観についてのコラムや仏教の考え方などが載っています。
「教え」ではなくて、「私はこう思います。あなたはどう?」
と問いかけられているような文章です。
毎月「禅の友」編集部から届けていただく度に
自分との対話の機会になっています。
9月はお彼岸もありますね。
今月もまた、気持ちの整理をしてみようと思います。
それにしてもまぁ、派手な額縁でございますね!
曹洞宗と古典技法額縁、このギャップを
楽しんでいただければ嬉しいです。
あなたのイニシャルはなに? 8月31日
日本で一番多いイニシャルはなにかご存じですか?
インターネットで調べましたところ
(ですので、正確かどうか不明です)
女性はM、男性はTなのですって。
自分の友人知人を考えてみると、ううむ
確かにそうかもしれません。
そんな訳でMの文字を入れた小箱を作りました。
極小の豆小箱にホワイトゴールド
(おおよそ金と銀が半々の合金属)箔を
貼り磨きまして、マイクロ点々でMを入れています。
あまり主張せず、でも反射の角度によって
キラキラと白く輝くイニシャルです。
古今東西、名前のイニシャルや
モノグラムを入れたものは人気がありますね。
やはり「自分のもの」という特別感があるのでしょう。
イタリアの名前で一番多いイニシャルはなんだろう?
日本ではとんと見かけない P C B G L V F なども
トップ10にはランクインしそうです。
個人的には・・・女性はM、男性はGじゃないかなぁ
と想像しています。
なにせ聖母マリアはM、ヨセフはG
(伊Giuseppe ジュゼッペ)ですから。
・・・なんて。
マリアとヨセフは別にしても
M&G は遠からず、と思っています。
今年秋11月9日から19日まで
箱義桐箱店谷中店にて「秘密の小箱展」開催いたします。
このイニシャル小箱も展示予定です。
ぜひお手に取ってご覧くださいませ。
詳しくは改めてご案内させてください。
遠くて近い異国に嫁いだ娘 8月28日
つくづく、インターネットって便利です。
いまさら何を言っているのだとお思いでしょうね。
インターネット無しの日々はすでに成り立たない世の中になって
もうずいぶんになりますから。
先日インスタグラムから「見知らぬ人が
わたしについて何やら投稿しましたよ」と
お知らせが届きました。
(あなたをメンションしました、のお知らせ)
「イタリアからお気に入りを持ち帰った。
ラヴェンナのガッラ・プラキディア廟堂の
天井モザイク模様を描いた手作り一点物の小箱だ。」
のコメントともに、居間らしき部屋に置かれた小箱の写真でした。
わたしのことも一緒にご紹介くださっています。
この方はラヴェンナ観光後、最後にフィレンツェに滞在して
Eredi Paperone に立ち寄り、イタリア旅行の思い出に
ラヴェンナ小箱を買ってくださったとか。
▲中央の青地に黄色模様の箱がラヴェンナ小箱です。
物を売るとは、その商品が手元を離れれば(つまり納品すれば)
もうその先はわたしの与り知れぬことになります。
自分の手元を離れたのだから、当然のこと。
分り切ったことだけれど、嬉しさと寂しさ不安が半々です。
そんな、まるで自分の分身か娘のように感じる小箱の
行き先をこうして知らせて頂けるのは、本当にうれしいことです。
インターネットの登場で世界と世間が狭く身近になった。
良い事ばかりではないだろう・・・けれど
わたしのように個人で制作販売している身としては
とても恩恵を受けているとつくづく実感しています。
ラヴェンナ小箱を買ってくださったのはアメリカ在住の方。
この小箱をわたしが手に取ることはもう二度とないでしょう。
願わくばラヴェンナ小箱が大切にされて
この方に幸せを運んでくれますよう!
遠い異国に嫁いだ娘とその家族に「幸あれ」と叫ぶ
母の心持ちになった夕暮れでした。
やるぞエミリア、でも気分は倒れる3秒前 8月14日
怒涛の勢いで(自分比)快進撃を続けております
エミリア額縁の摸刻・・・
と書き出しましたけれど
実際のところは動悸息切れ激しいわたしです。
とにもかくにも完成間近になりました。
・・・まだ完成していませんけれども。
▲ボローニャ石膏を塗ります。
木地に下ニカワを塗り、薄めシャブシャブの
ボローニャ石膏を細い筆で塗り重ねます。
溝に液溜まりができないように細心の注意を払います。
▲地獄の石膏磨き
なにせカーブや凹凸が激しいので紙やすりも届きにくい。
ここでモノを言うのが石膏塗の跡です。
石膏液を凹凸にもいかに均一に塗るか!筆跡を残さないか!
その結果によって地獄の石膏磨きの作業時間が左右されます・・・。
そして愛用の三共理化学の空研ぎペーパーはしなやかで大変に宜しいです。
▲黄色ボーロ塗り
さて無事に磨き終えまして、ここで登場するのが
2月にフィレンツェのZECCHIで買った黄色ボーロです。
いままで使っていたシャルボネの黄色ボーロは
何というか黄色というよりオレンジ褐色で
どうも違う・・・と思っておりました。
このZECCHIの黄色は、ローシェンナ色
まさにトスカーナの土の色です。
▲黄色の上に赤ボーロ
やはり黄色ボーロより赤ボーロのほうが
金を磨いた後に輝きますし、色味もきれい。
凹に黄色を残し、凸に赤を重ねます。
▲いよいよ箔作業開始
ゼーゼー・・・息切れが。
金箔を20等分に小さく切り、チコチコと貼ります。
側面や穴、奥の方まで、可能な限り箔を貼り
どうにもこうにも届かない部分や影は金泥でごまかし
とにかく金で額縁を包み込んでいきます。
▲メノウ棒で箔磨き、目が痛くなる。
もはや意識が朦朧としてきました。
・・・いえ、もちろんワタクシ元気ですけれど
気分的には白目をむきそうです。
居間の薄暗がりで、メノウ棒でカタコトと
(木とメノウ石が当たる音がする)磨いておりましたら
家族が見て一言「ウッギャー・・・すごぉ・・・」
「素敵だね」の「すごぉ・・・」では無い。
ええ、分かりますよ、ギンギラギンでコッテコテですからね
これは和室には不似合いかもしれません。
でもこの曲線、輝く金の光と影、これもひとつの美ですぜ!
こうした時に改めて、日本とイタリアの文化と
感覚の違いを痛感します。
安土桃山時代の人々なら・・・織田信長とか
気に入ってくれたかしらん?と妄想しております。
次回は古色を付けて完成した姿をお披露目いたします。
たまには新調 8月10日
ここのところ、新調して「つくづく良かった!」
と思うものがふたつあります。
ひとつは冷蔵庫。
我が家の冷蔵庫はかれこれ30年近く使っていて
ドアパッキンが緩くなるし、たまに変な臭い
(たぶんフロンガスが漏れている・・・)がしていて
電気代も高騰の折、新しい冷蔵庫をお迎えしました。
ひと回り大きいサイズ、冷凍庫もたっぷり、ドアも両開き。
そして何より氷が自動にできて
いつでも使い放題なのですよ!魔法のよう!
・・・もうずいぶん前から自動製氷機能搭載の
冷蔵庫が一般的なのは知っておりますが
実際に使ってこんなに便利と思いませんでした。
夏にありがたさを痛感します。
パカッと開ければ明るい庫内は整理されていて
(以前は一部魔窟化していた)氷もたっぷり。
とても豊かな気分です。
▲先日立ち飲みしたクラフトビール、美味しい!
内容とは関係ありませんが。
そしてもうひとつは日傘です。
これまた大昔の、いちおうUVカットと表示はされているけれど
普通の布地の日傘を愛用しておりました。
日傘って汚れるとか日焼けしてみすぼらしくなる以外に
壊れないので新調する機会がなかったのです。
まだ元気な日傘があるのに新しい傘を買ったら
古い傘は使わない、さりとて捨てるに惜しい。
ですが今年の猛暑は異常。背に腹は代えられぬ。
ちょっと奮発して最新加工のお高め日傘を買いました。
これが!いや、たかが日傘とはもはや言うまい。
傘の下はぐっと暗くなり、体感温度の違いに驚きます。
吹き抜ける風まで冷えて感じるような。
・・・そうですね、この表が白、中が黒の
99%遮光UVカットの日傘が登場してから
もう数年(もっと?)ですので
皆さんは機能の進化と効果はよくご存じですよね。
▲友人と行った中華のピータンと腸詰。美味しい!
内容とは関係ありません・・・
どちらもほかの方々からしたら「今更?!ようやく??」の内容かも。
冷蔵庫はさておき、日傘は投資額に比べれば
今までの我慢があほらしくなるほどの違い。
物持ちが良い(ケチとも言う)も一長一短だなぁと思いました。
快適に過ごすには新陳代謝も適度に必要でございます。
ああ、イタリア女性にもこの日傘の快適さをお届けしたい。
でも彼女らは日焼けしたいのですから余計なお世話かしら。
怖い怖いと言いながら 8月07日
前回ご覧いただいた「ルネッサンス風」
ほぼレプリカ額縁の制作過程をご紹介いたします。
とはいえ、これまた以前ご覧いただいた
「ことわざ額縁」と同じ技法で重複しますので
もしご興味がありましたら、ご覧いただけますと嬉しいです。
さて、木地は参考にしたオリジナルの額縁と
今回額装する作品とのバランスを考えて
簡単なデザイン画を起こしてからお客様にご相談。
微調整をして最終確認をして頂いて・・・
いつものように千洲額縁さんへ木地をお願いいたしました。
▲写真は千洲額縁さんインスタよりお借りしました。
千洲額縁の職人さんは、もうわたしの魔法の玉手箱状態です。
図面と希望を伝えると形にして送って下さるのですから!
そしていつものように下膠(ウサギ膠1:水10)を塗り
ボローニャ石膏液を塗り重ね、乾きましたら紙やすりで磨きます。
▲地獄の磨き(大げさ)を終えたところ。ふぃ~
次はこれまたいつも通り
魚膠で溶いた赤色ボーロを塗り重ねまして、純金箔を貼ります。
▲側面も金ぴか。これからメノウで磨きます。
参考にしましたルネッサンス時代に作られた額縁
もちろん実物を見たことはありません。
お客様から送って頂いた数枚の写真を拡大印刷して凝視して
下描きを「ああでもないこうでもない」と繰り返して数日。
ようやくトレーシングペーパーに転写しまして
お客様にもご確認いただき
▲トレペを載せたところ。まだ完成図には程遠い。
さて、問題はここからでございます。
オリジナルの額縁、当時の諸々を考えると
恐らく模様は黒ベースの可能性が高いんじゃないかな、と思いつつ
お客様のご希望は「オリジナルは深緑に見える。
作品との相性も良いから深緑で。」とのご注文です。
オリジナルの額縁を見ることは叶わず問い合わせも難しい。
問題は、わたしにはどうにもこうにも緑に見えない・・・ということ。
見えない色を再現する難しさよ。
色の認識は人それぞれの感覚ですし
深緑で製作、これはもう全く異存ありません。
額縁職人としての微々たるプライドをかけまして
経験を総動員して「古色加工後の完成時に黒寄りの深緑になる」を
作る覚悟を決めたのでございます。
怖い!でもやるしかない。
色を作って塗って、乾かしてから
古色用ワックスを塗って確認して
という実験を繰り返しまして、
再度覚悟を決めまして(大げさですね。しつこくてすみません。)
▲こんな緑色を卵黄テンペラで塗りました。
▲グラッフィート(模様の搔き落とし)を終えたところ。
実際の緑色はもっと明るかったのですが
写真に撮ると暗くなりました。
いやはや・・・息切れします。日々恐怖との闘いでした。
何が怖い?そりゃ失敗です。
「こんな色になるはずじゃなかった!」とか。ヒィィ。
▲ZECCHI のシェラックニスを塗ってから、いよいよ古色付け。
上の写真は古色付け初日
まだまだ金の輝きも緑の色も鮮やかでした。
これから更にワックスや塗料、パウダーを重ねては拭き
重ねては磨いて、完成しました。
▲コテッと古色仕上げ
それにしても「大変だった怖かった」と書き連ねるほどに
職人として自信がないと自白しているようですね・・・
でもまぁ、わたしの製作の現実はこんな感じです。
額縁伝道 8月03日
曹洞宗の冊子「禅の友」8月号です。
この額縁も7月号同様
イタリア・ピエモンテ州で作られた額縁のレプリカです。
7月号の額縁が1700年代、この額縁は1600年代末。
100年近いひらきがあります。
さわやかなレモンイエローの背景に青葉色のロゴ。
夏らしくフレッシュな感じです。
偶然ながら(または編集さんの楽しい企みか)
表紙の写真と額縁実寸が同じ!
小さい額縁ですから、それが可能だったのですね。
▲実物額縁を探せ!・・・すぐばれますね。でも面白い。
毎月編集の方がこの「禅の友」を数冊まとめて
我が家へ届けてくださるのですが
編集部に届く読者の声をプリントしたものも
同封してくださいます。
これがもう、なんとも嬉しいのです。
わざわざまとめてプリントして送って下さる
編集さんのお気持ちに加え
表紙の感想をわざわざ投稿してくださる
読者の方のお気持ちのありがたさ。
それこそ老若男女からのご感想です。
ひとこと「励まされる」では足りないくらいです。
いままで額縁に興味がなかったけれど、新しい世界を知った
切り抜いて壁に貼って、中に子供が描いた絵を入れて家族で楽しんでいる
額縁の表紙は突飛で最初は驚いたけれど、気づけば毎月面白くなってきた
などなど。
わたし一人の活動では狭い世界でしたが
こうして「禅の友」の皆さんのお力で
いままで接点がなかった方々に額縁の
魅力を感じて頂ける機会になりました。
自分が好きなものを作って手元ばかり見ていたけれど
顔を上げて見回してみたら、いつのまにか
笑顔の人が周りに沢山いてくれた、といった感じです。
ありがとうございます。
いつの間にか残りはあと4か月になりました。
額縁の魅力と楽しさを感じて頂ける機会を
大切にしようと思います。
それぞれの愛を込めて 7月27日
先日、友人と話していた時のこと。
「猫を飼っている人は抜けたヒゲを
大切に保存することが多いから
猫ひげ小箱の需要は実はあるかも・・・」
と教えてくれました。
▲友人が送ってくれた猫の毛ボール写真。
愛があふれて、ボールも小箱からもあふれている。
なにせペットは猫はおろか
一切飼ったことがありませんので
「猫のヒゲが幸運をもたらすお守りになる」のは
知りませんでした。
これぞまさに、目から鱗が落ちました。
さっそく手元にある細長い小箱を
ふたつ選んでいそいそとネットショップに上げました。
おついでの際にでもぜひご覧ください。
「小箱に何を入れるのか問題」は
相変わらずわたしのなかで渦巻いています。
ただ飾る、拾った石(大切な石)を入れる
お母様の形見の指輪を入れる、そして
猫のヒゲを保存する・・・
わたしが何か使用目的をもって作らなくても
持主がそれぞれ自由な発想で、
それこそわたしには思いつかないような発想の
使い方をして下さるのでした。
箱は小さくとも、とても大きく広い世界です。
そしてわたしの心がふわっと幸せになります。
あまり大きな声で提案する内容では
無いかもしれませんが
手元供養にも使っていただけたらと考えています。
大切なご家族、話したり触れることはできなくても
せめて一部だけでもそばにいて欲しい。
そんな時にKANESEIの小箱を使って下さったら
とても嬉しく思います。
使命ある人 7月24日
イタリアの北の街に医師の友人がいます。
寡黙で穏やかで博識な美食家、といった人で
きっと病院ではスタッフや患者さんに
信頼されているだろうと感じます。
この人は人間のお医者様で
毎日患者さんを助けているけれど
野生動物も頻繁に助けています。
今日もまた「昨夜遅くにメスの狐が車に
はねられていたのを急いで救急病院へ運んだ。
ひどい骨折だ。今日まだ命があれば手術になる。」
と知らせてきました。
▲可哀そうな狐ちゃんは車で緊急搬送。
動物病院への連絡用に撮った写真を、後に私にも見せてくれた。
この狐だけでなく、巣から落ちて見捨てられた雛鳥とか
怪我をしたフクロウとか・・・
弱った動物は、まるでこの人が必ず助けてくれると
知っているかのように目の前に現れるのです。
助けた鳥を空に放しては「とても嬉しく寂しい」とつぶやいています。
▲森の中ではない、街の中で倒れていた狐ちゃん。
この子を撥ねたドライバーは今いずこ。
他の人だったら「可哀そうに」と思っても
怖くて近づいて様子を見ないかもしれない。
まだ息があっても「仕方ない」と見捨てるかもしれない。
この友人は人間も動物も同じように「助ける人」
そんな使命があるのかもしれません。
翌朝、この狐は満身創痍でも必死に立ち上がり
命の危険はひとまず回避できたとか。
今は野生動物保護センターで治療を受けていますので
自分のテリトリーに帰る日も来そうです。
良かった!
やるぞエミリア、血と汗だけど涙はない。 7月20日
しばらく休んでいた額縁摸刻ですが
ここ数日に集中して自宅で作業し
彫刻はどうにかこうにか終わりが見えました。
イタリアのエミリア地方で17世紀に作られた額縁のレプリカです。
▲サイズはB5くらいで、結構小さい・・・けれど。
上の写真がモノクロなのは半分カッコ付けていますが
もう半分はカラー自粛であります。
というのも、白木に赤い血の跡が点々とあるのです。
彫刻刀で小さな切り傷を作ってしまっても
ティッシュでチャッと拭いてそのまま作業をするのですが
当然止血はしておりませんから
気づくと赤い染みが付いていたりして。
この灼熱地獄、プレハブの作業部屋はエアコンを
25度設定にしても室温33度なので
(フィルター掃除はしているのですよ)
この額縁は正に「血と汗の結晶」なのです!
・・・おおげさ。涙はない。
この額縁、ローマで知り合ったアンティーク額縁商の
カントさんが書かれた本に載っていて
実物もカントさんがお持ちでした。(今は売却済みとか。)
彫り進めるにつれ、正面だけではない情報が欲しくなり
カントさんに泣きついて斜めからの写真を送って頂いたのでした。
▲カントさんの本を見ながら彫る。
分かったことは、予想外にとても薄い額縁だったこと。
わたしが準備した木地はとても厚くて
オリジナルの優雅さが出ない。
苦肉の策ですが、裏面の面取りを
かなり深く大きく削ることにしました。
結果、「いつわりの薄さ」ですけれど
表から見るとずいぶんと「薄く見える」ようになりました。
わたしの身体中のお肉も面取りして
「薄く見える」ようになりたい・・・。
▲額縁裏側。木地は一枚の厚い板を切り出しています。
ちなみに今になって面取りし忘れた部分が
あることに気づきました。
上部のダイヤ型の穴、ここも削らなくては。
まぁ続きは明日にでも。
この後は、下ニカワ(兎ニカワ1:水10のニカワ液)を塗り
ボローニャ石膏液を塗り乾かし
恐怖の石膏磨き・・・と続きます。
このエミリア額縁は自分のための制作です。
仕事の合間やアトリエLAPISの時間にガサゴソ作っております。
実は完成の締め切りが出来ましたので
若干慌てておりますが、とにかく慌てず焦らず進めます!
それはたぶんこれ 7月17日
先日、アトリエLAPISの生徒さんとおしゃべり中に
「趣味は何ですか?」と尋ねられました。
わたしの趣味・・・はて、何だろう。
以前はピアノを弾くこと(家族が留守の時のみ。
人に聞いてほしくない。)でしたが、最近はめっきり。
お茶(裏千家)の稽古は10年以上続いていますから
これはまぁ趣味と言えるかも。
だけど積極的な何か・・・例えば
アトリエLAPISの生徒さん方が制作に傾けるような
情熱やひたむきさを持って臨む趣味は
無いなぁ・・・と気づいたのです。
最近、父の大切な友人からの頼まれ事で
お湯呑みの金継ぎをしました。
ついで(と言っては何ですが)に我が家の「金継ぎ待機中」
つまり途中で作業が止まっていたお皿も同時進行。
金継ぎを習ったのはかれこれ7~8年前に数か月だけ。
一通りの手順を教わりました。
その後は当時のテキストやら本を見ながら自己流でやっています。
ですから、まだまだ全くもって技術の習得には道のりは長い。
▲欠けた部分を整形して磨き、仕上げの金蒔絵。
赤漆を薄く塗って純金粉を撒く。
額縁制作にしろ金継ぎにしろ、技術は方法を習って
後は繰り返して身に着けるしかありませんね。
その都度技術の上達具合によってコツや
「より良い方法」を教わる必要がありますけれど
あとはとにかく Just do it! でございます。
▲金を撒いたら数日後に「固めの漆」を塗り
更に1日後、ようやく仕上げの磨き。
▲鯛牙(本当に鯛の歯)で磨くと輝きだす。
古典技法のメノウ棒でも可・・・
輝きだす金の美しさがたまらない。
これだけワクワクウキウキできるって
趣味と言っても良いのではないだろうか??
▲完成したお湯呑みとお皿2枚。
色々改善点は目につくものの、おおむね。
次回どなたかに「趣味は?」と尋ねられたら
「金継ぎです」と答えられるようにもう少しマメにやって
秋になったら金継ぎ教室通いも再開して、と思います。
・・・思います。
これまた思うだけではなくて Just do it! でございますね。
思っているだけだと、あっという間に時間は過ぎる。本当に。
これで良いのか悪いのか 7月06日
曹洞宗の冊子「禅の友」7月号です。
この額縁も例によってレプリカでございます。
オリジナルは18世紀にイタリア・ピエモンテ州で作られた額縁です。
ピエモンテ州とはイタリアの北西部で州都はトリノ。
フィレンツェやローマよりずっとスイスとフランスに近く
洗練されてリッチな街というイメージです。
(行ったことがありませんけれども。)
18世紀といえば、すでにルネッサンス時代ははるか昔
ロココ様式が始まっていて、フランス革命とナポレオンの登場
産業革命が起こる頃だとか。
額縁の様式もまた建築・家具・服飾の様式と同様ですので
イタリアの額縁といえど18世紀ピエモンテらしく
何とはなしにロココな風味が感じられます。
実はこの額縁、完成時にもすこしお話したような記憶がありますが
純金箔の上に施す古色仕上げ加工の色艶に
あまり納得できておりませんでして、
だけど具体的にどうしたら改善できるか
どうなったら正解か分からなくて・・・
今回の撮影時にこの額縁を参加させるか迷ったのですが
編集の方から色校を見せて頂いたときに
「おや?!この額縁ってもしかしたら悪くないのでは??」
と思っちゃった不思議!
この淡い黄色みの感じられる青との組み合わせがあまりに良くて
釣られて額縁も良く見えちゃう!
というマジックなのでした・・・。
▲とはいえ、写真の額縁の金は茶色味が感じられる。正解はここか?
ロココは白を基調にパステル系など明るい色味
金も明るく(白~レモン色)に輝くイメージなのですが
ううむ、どうするか。
わたしがコテコテ古色が好きなだけなのだから
ロココ風にこのままオリジナルに近い明るい色を保つか?
これで良いのか悪いのか?
悩みは続きつつも、この表紙には大変に救われたのでした。
曹洞宗の冊子「禅の友」は一般の書店での取り扱いはありませんが
1冊80円(送料別)にてお手元にお届けします。
下記のサイトをどうぞご覧ください。
今日からわたしは 6月05日
小箱を「販売しよう」と作り始めたころから
決めていたことがあります。
それは「同じデザインの小箱は作らない」ということ。
以前に少しお話したことがありましたが
まるっと同じデザインとサイズの小箱は
今まで作らないようにしていました。
同じ模様でも技法違いや色違い、サイズ違いと
少しずつ変化させています。
本当はそれも出来れば避けたい気持ちでした。
3月の阪急うめだ本店での催事で、お客様に
「同じデザインの小箱は作らないようにしています」
とお話したところ「ええっ?!」と驚かれました。
その様子を見てわたしも「えええっ?!」となったのでした。
そんなに意外なことでしたでしょうか。
▲桜咲くころのアトリエLAPIS 生徒さんが少ない日に小箱磨き中
以来なんとなく「なぜ同じものを作らないのだろう?」と考えていました。
ひとつは単純に「マンネリ化したくない」があります。
でもそれだけではない。
思い返してみれば・・・
一番最初、小箱を初めて作ったころは
友人知人にプレゼントする目的で作っていました。
だからと言う訳ではありませんが
「このデザインはあの人のためのもの」のような気持でした。
同じものを作って販売したら
差し上げた相手に申し訳ない気がする・・・と言うか。
だけどまぁ、そこまで考える必要も
ないのかもしれない、と思い始めました。
差し上げた方は何とも思わないのではないかしら、と。
そして何より
とても好きなデザインの小箱は再度作りたいのですもの!
前置きが長すぎました。つまり
「今日からわたしは以前作ったデザインの小箱を再度作ります」
の宣言でございます。
好きなら飽きるまで作ってみよう。
その先にも何かあるだろう。
と、思う今日です。
やるぞエミリア、要らなかったかも・・・? 5月15日
3月に着手しましたエミリア地方16世紀の
額縁レプリカ制作は、何と言いましょうか
進みは遅いですが必死に作っております。
だんだんと目が点になってきている気がします。
一枚の写真だけを参考に
作ったこともない複雑な額縁を真似して作る無謀・・・。
そこで自分を励ます一言を心の中で叫びます。
「この1枚目の木地は失敗しても大丈夫、
なにせもう1枚予備があるから!」
そして思い切って彫り進めることにいたしました。
▲ジェルトン材。柔らかくサクサク彫れますが欠けやすいのが難点。
どこを思い切ったのかい?とのご質問が聞こえてきそうですが
上部と下部の葉が巻いている部分です。
ここは内側に巻き込まれた葉を表現するために
部分的にパーツを別に彫って後から取り付けるつもりでした。
▲彫る前状態。上にある6つのピースが貼り付け予定の部分パーツ。
せっかくのパーツだけど、要らなかったかも・・・?
木地を厚く作って頂いたので
予想以上に高さに余裕がありました。
もしかしたらこのままいけるかも、と彫ってみた次第です。
左肩部分の葉の失敗が痛いですが
(パーツ取り付けのつもりで彫り落してしまった)
ここは当初の予定通りパーツを張り付ければ大丈夫でしょう。
「なぁに心配無用!もう1枚予備の木地がありますので!」
と呪文を唱えて再度自分を励まします。
最後の救世主であるエポキシパテ木部用も準備万端です。
為せば成る、為さねば成らぬ何事も!
・・・為しても成らぬ事もあるけどね・・・。
成るように頑張ります。
モッコウバラの叱咤激励 4月27日
春が終わりに近づいていますね。
毎年のことながら不思議。
4月から5月の連休はなぜか大忙しになります。
ちょうどモッコウバラが咲く季節なので
印象が強いのかもしれません。
我が工房自慢のモッコウバラはもう散ってしまいましたが
この忙しさはモッコウバラからの贈り物と励ましだ!
と思っております。
とはいえ、気持ちと体が追い付かぬ。
モッコウバラよ、お許しを。集中できない。
わたしの「やる気スイッチ」は爆発して消えました。
・・・そんな時もありますよね。人間だもの。
最近なんだか小さな切り傷ばかり作っています。
今もまたハサミで指を切りました。
ハサミで指を切るって、小学生以来かもしれません!自分でびっくり。
引き出しにあった絆創膏、ここぞとばかりに使うことに。
名前も知らないクマちゃんの(クマですよね??)
真っ赤な笑顔に励まされます。
そしてこの「コ―フル」という軟膏はわたしの特効薬です。
切り傷って案外と痛いのですよね。
でもこれを切り口に詰め込む勢いで塗ると、あら不思議
痛みがとても和らぐのです。
たまになる口角炎と靴擦れにも使っています。
どこのお家にも「我が家の特効薬」的な
軟膏ってありましたよね。
オロナインとかタイガーバームとかメンソレータムとか。
我が家の場合は「コ―フル」なのでした。
とりとめもない話になりました。
モッコウバラに「さぁさぁ、わたしもがんばっているよ
君もがんばりなさい!こんな愚痴ブログを書く暇に
さっさとやりなさい」とお尻を叩かれましたが
集中力が散漫なのも、きっと季節の変わり目だからなのだ
人間も生き物だからだ、と言い訳しています。
いや、でも、こつこつ少しずつでも進めます。
とにかくわたしの「やる気スイッチ」の
発掘作業も同時進行しようと思います・・・。
大きいマイクロの楽しい悩み 4月20日
昨年10月に作り始めた大きめ小箱
(大きいのか小さいのか、変な表現ですが)
マイクロ点々でダマスク模様を入れる作業がようやく終わりました。
この点々打ちは本当に地道で地味な作業ですが
小箱と細いメノウ棒があれば作業できますので場所を選びません。
そんな訳で阪急うめだ本店での「クチュールジュエリー展」に
持ち込んで実演(という名の内職)をいたしました。
▲とんとん、てんてん、つんつん・・・なんと表現するべきか。
クチュールジュエリー展終了後に自宅で最後の仕上げをしまして
点々打ち作業終了です。なんとも達成感があります。
晴れた日の光で見るとキラキラして本当にきれい。
いや、自画自賛で恐縮ですが、今回はお許しください・・・。
さて蓋の装飾がひとまず完成しましたので
あとは何色に塗るかで頭を悩ませています。
黒は強すぎますしね。濃い茶色は嫌がる人がひとり家にいますし。
ある人は赤、またある人は若草色、家族は空色・・・と。
つまり何色でも良いんじゃないの?!
なんとなく、わたしの気持ちは若草色かクリーム色に傾いております。
・・・ううむ、空色も捨てがたい。
楽しい悩み。
追:どうやら抜歯は免れそうです!
その運命やいかに・・・?! 4月17日
わたくし事で恐縮ですが
・・・このブログにはわたくし事しか
書いておりませんので今更ですが
歯が痛いです。
いや、正確には「その歯の歯茎が痛い」です。
2023年お正月から違和感があった右下
奥歯と前歯のあいだ辺りの歯。
数年前に欠けて炎症を起こし
神経を抜いて歯の内部を清浄して埋める
結構大工事治療をして頂いたのですが
最近その歯の根元がとうとう大きく膨らんで
何かが溜まっている・・・これはまずい。
もう「いやいや、気のせい。そのうち治まる」
という望みは薄れました。
怒涛のように友人と「おいしいものを食べ飲み」
の予定を入れまくり、意を決して歯科へ行きました。
▲息継ぎに名残の桜などご覧ください。
以前の治療で埋めた詰め物を取り除いても
膿は出てこなかったから再発ではなく、
歯の根元が新たに欠けた可能性、とのこと。
歯の根元が欠けるって、どういうことです!?
殴り合いの喧嘩もしませんし
歯ぎしりした覚えもない。
先生がおっしゃるには
「手入れが悪いとか人為的な理由ではありません。
でも原因は不明」とのことでした。
ちなみに欠けた歯を接着するのはダメ?と質問したら
縦半分に割れた直後なら方法はあるけれど
根本の欠けはダメ・・・とのお話でした。
つい「壊れたら直す」修復精神がムラムラしますが
ダメなものはダメなのですな。
この「歯が欠けて炎症→神経を抜いて埋める治療」は
他の歯でも経験しているのです。
虫歯じゃないし、硬いものを齧ってもいない。
自分で対策ができないのは本当に・・・本当に困ります。
こんな歯を持って生まれた体質としか言えない。
▲花の写真など撮って必死に平静を装う・・・
来週は歯科でレントゲンを撮る予定です。
この時わたしの歯の運命が決まるのですって。
つまり治癒可能か抜歯か!!
抜歯・・・嗚呼。
インプラント・・・という言葉が現実味を帯びて
目耳に飛び込んでくる今日この頃です。
ChatGPTに問う額縁の将来 4月13日
いま、毎日聞かない日はないChatGPTですが
実際にお使いになりましたか?
国会答弁に使うとか、大学のレポートでの使用問題。
イタリアではプライバシーに問題があるとの懸念で
一時的に使用禁止を発表しました。
わたしは文章を書くのは専らこのブログ程度ですので
ChatGPTを使う必要もない日々ですが
あまりに毎日耳にするので使ってみました。
さて。ChatGPTに何を問うか。
「額縁の将来についてどう思いますか?」と打ち込んでみました。
答えは以下のように出ました。(句読点もそのままです。)
”私は、
また、デジタル写真やアート作品が普及している現代でも、
これは、
さらに、額縁は、
ただし、持続可能性の観点から、
製造方法に関する改善が必要となる可能性があります
例えば、リサイクル可能な素材を使用する、
まず驚いたのは「私は、・・・思います。」という
一人称で答えが来たこと。
実在の人物を錯覚しそうです。
答えの内容は、そうですね、未来に依然と需要があるだろう
との予想に一安心しました。
そして、当たり障りない答えでありながらも不思議な説得力がある。
いや、分かっています。
ChatGPTは占い師でもタイムトラベラーでも無い。
でも何故か、見知らぬ人の意見より信憑性を感じてしまうのです。
これが正に恐れるところであり、
分かっていても不安を感じます。
機械が作ったこの「無難すぎる『見本のような』答え」に
背筋がスッと寒くなるような。
ChatGPTをよく理解していないだけでしょうか。
新しいことに対する単なる反発?
自分でもよくわかりません。
将来の激変がどうなるのか。
自分を含め人間がChatoGPTに付いていくことができるのか。
今後に恐々と期待しようかな・・・いや、どうだろう。
皆様はどんな感想をお持ちになりましたか?
クチュールジュエリー展 ありがとうございました 4月03日
3月22日から27日まで大阪の阪急うめだ本店にて開催されました
「クチュールジュエリー展2023」は、無事終了いたしました。
雨の日が多く、足元の悪い中を
お越しくださいました方々に感謝申し上げます。
今回は昨年に続き2回目の参加でした。
大阪在住の方、東京でお目にかかり辛い方々と
お会いできたのが収穫でした。
また、今年は実演と言いますか(内職と言いますか)
テーブルの端で「マイクロ点々入れ」をしていたのですが
こちらにご興味を持って下さる方々も。
▲こちらまだ下描き中・・・
「こんな小箱初めて見た」「こんな技法は知らなかった」など
あるいは既に古典技法をご存じの方とのおしゃべりなど
対話のきっかけになったようです。
2年目の課題としては・・・いろいろ沢山ありました。
こちらについては対策を考えるつもりです。
自分で作った物に値段をつけて
自分で対面で売るというのは
やはり一筋縄ではいかないものでございます・・・。いやはや。
今回のクチュールジュエリー展で
ひとまず小箱の行商はしばらくおしまい。
次は4月末に松屋銀座(わたしは在店できず失礼いたします)
9月には箱義桐箱店谷中店にて昨年同様の展示会を行う予定です。
さぁ、一息ついたらまた小箱を作ります!
そして額縁の修復と制作はいろいろプロジェクトが目白押しです。
いよいよ4月の新年度、やりますぞ!!
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
やるぞエミリア、着手の日 3月30日
自覚はあまり無かったのですが(今はある・・・)
わたしはお調子者の面があるようです。
その場の勢いとか雰囲気で、あまり考えずに
「いいねいいね!やってみよう!やってみないと分からないよ」と口走り
いざ始めてみて「・・・あれ、大丈夫かな」などと思うのです。
これつまり後の祭りと言う。
今回の額縁摸刻もまさにそれ。
▲本の額縁はイタリアのエミリア地方で17世紀に作られた額縁です。
市が尾の古典技法教室 アトリエLAPIS の生徒さん数人と
「この額縁かわいい~♡こんなのつくってみた~い!」と盛り上がり
いそいそと千洲額縁さんへ木地をお願いしたのでした。
届いた木地を見て、そして本の写真と比べてつくづく見て
3月ついに着手する日が来て・・・
おおぅ・・・強烈。いや、分かっていたけど。
同じ木地を購入された生徒さん方が作る前に
講師のわたしが一通り理解していないとなりませんから
何はともあれやるべしやるべし!でございます。
▲上の小さなピースは別に彫ってあとから取り付けます。
下描きをしてみたらやっぱり可愛いムフ。
だんだんと気分が盛り上がってきました。
これまたお調子者です。
なにせ「曲線の額縁」は初めてですので
今回、同じ木地を2枚注文しました。
ひとつはチャレンジ用、もうひとつは完成用。
つまり、ひとつ目は間違えること前提です。
心置きなく失敗して経験して理解して
もうひとつをきっちり仕上げるつもりです。
・・・つもりです。
なぁに、人生何ごとも挑戦ですよ!ワハハ!
・・・ハハ・・・がんばります。
「青き衣」じゃない 3月27日
先日、鼻歌交じりに純金箔を貼り終えた小箱を彩色しました。
「ここはキリッと青と赤にしちゃおう」と思いまして。
緑がかった明るい青と濃い赤を選びました。
塗り終えて、なにか・・・
なにかとても良く知っているものを思い起こさせる。
それはナウシカの「青き衣」なのでした。
▲分かる方にはわかって頂けると期待します。
王蠢の体液に染まった衣・・・
模様の感じとか青の色味とか、似ていませんか。
(「風の谷のナウシカ」をご覧になっていない方には
何のことか分かりませんよね。すみません。)
そう思うともう、そうとしか見えなくなる不思議。
これはまずい・・・。
「その者青き衣をまといて金色の野に降り立つべし・・・」
大ババ様!違います、これは金色の小箱なのです!
ユパ様に相談しまして(嘘)、これは強めの古色を付けて
「脱・青き衣」を狙うべし、となりましたので
つや消しにしてからワックスとパウダーで汚して
青の色味を変えました。
▲ いかがでしょう、「青き衣」感は遠ざかりましたでしょうか。
最初は我ながら「まさかのお蔵入り?」と
どうなることやらハラハラしましたが
古色を付けてみたらすっかり気に入りました。
笑ってしまう。
何となく祭壇型額縁の装飾模様にも見えてきました。
かなり贔屓目ですが!
そしてもう一度「風の谷のナウシカ」を観たくなりました。
箱の内側に貼り込む布を何色にするか悩んでいます。
でも青は選ばないつもりです。
・・・いや、やっぱり青ですかね??
春だからバラ色に 3月20日
毎日ドタバタとしているつもりでしたが
実はものすごく狭い範囲しか移動していません。
はっきり言えば家の中か買い出しのスーパーくらい!
だけど頭の中はものすごく慌ただしく過ごしている今日この頃です。
ご注文いただいた額縁の制作ついでに
(ついでと言っては語弊がありますが!)
小箱も同時進行しています。
この額縁と小箱は、いわば「同じロット」であります。
同じ石膏液、同じボーロを使って同時に箔を貼って磨きました。
ですので古色加工ももちろん一緒に。
ロットナンバー0304「ちょっとコッテリ風味」です。
小箱の中に貼る布は何色にしようかな、と迷い中です。
気持ちを盛り上げたいので「バラ色」にしましょうかねぇ・・・。
春ですしね。
和風に見えてくる不思議 3月06日
「禅の友」(曹洞宗の冊子)の3月号が届きました。
今月は「cassetta-1」という名前で出している
額縁を選んで頂きました。
雛祭りの時期だから、バックはピンクで可愛く!
額縁も併せて可愛らしいものを!!
と編集の方が作って下さった表紙です。
それにしても漢字タイトルが隣にあるせいか
額縁がとても和風に見えてくるのが不思議です。
なんだか金糸で織られた帯のような。
オリジナルの額縁は16世紀半ばに
フィレンツェで作られた額縁なのですが
日本人のわたしがレプリカを作りましたので・・・
なにか「和の血」が注がれたのかもしれません。
▲こうして見ると大して和風でもないような・・・。
影の有無とか?やっぱり和風??
なぞの折衷と言うことで!
この「禅の友」は毎号に山下裕二先生の「体感!日本美術」
というコラム(今月は若冲と田中一村)があったり
今月号には箱根駅伝で総合優勝した駒澤大学の
監督インタビューなども掲載されていて
読みごたえがあります。
お手に取って頂けますと幸いです。
ギャラリーササキ商店「工芸市」ありがとうございました 3月02日
大阪の心斎橋、御堂筋にあるギャラリーササキ商店にて
開催されました「工芸市」は2月27日に無事終了いたしました。
お越しくださり、またお買い上げいただきありがとうございました。
遅ればせながら様子をご報告させてください。
今回は7名それぞれ違う分野での作家のグループ展でした。
丹波布、陶器、椅子、染色、螺鈿、ホームスパン、そして小箱です。
東京からの参加はわたしのみ。
なんだかとても新鮮な気分でした。
▲並べた小箱も額縁も「いつもの」です・・・。
何といってもギャラリーのSさんとNさんが!
それはそれは素敵なお二人で、このお二人のギャラリーなら
何も心配は要らない・・・と思いました。
穏やかでふんわりとした雰囲気
作家にもお客様にも心配りが行き届き
好奇心に溢れ(だから知識も経験も豊富で)冗談と笑いがある。
ギャラリーはシンプルで細部にこだわりがあって
目抜き通りに面しているのにテラスには花と緑があって、中庭もある!
本当に唯一無二だなぁ・・・と
居心地の良さに毎日ボンヤリしてしまうのでした。
▲このシルバーのトレーはNさんの私物を貸してくださいました。
他の参加者6名の作家さん方も、そんなSさんとNさんが
呼び寄せた方々ですので不思議とホンワカした雰囲気で
初対面のわたしを(他の皆さんは顔見知りとのこと)
すぐに仲間に入れてくださり、これまた居心地が良すぎてボンヤリ・・・
昨年3月の阪急うめだ本店でのイベント以来の大阪でしたが
インスタグラムを見たとお出かけくださった方が
何人もいらっしゃって、本当にうれしいことでした。
物を作って発表するって想像以上に勇気と根性が必要と痛感していますが
こうしてお客様が来てくださる喜びも想像以上のものです。
大袈裟に言えば「生きていることが許された」と言うか・・・。
だから、今後もまた小箱と額縁を作ってイソイソと発表しようと思います。
お越しくださいましたお客様、ご一緒して下さった作家の皆様
そしてギャラリーササキ商店の皆様
心よりありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
見るだけだったけれど!のバトン 2月23日
わたしのこのブログ「diario」は、実は
(と言いつつもうご存じの方もいらっしゃる)
アメーバのブログでも同じ内容で出しています。
アメブロは本当にブログの文章のみの「支店」
こちらホームページが「本店」なのです。
古典技法額縁制作修復 KANESEI (ameblo.jp)
↑支店はこちら
そのアメブロの方で面白い企画をしているようで
いわゆる「バトン」が回ってきました。
内容に指定があって、それを書いたら
同じくアメーバでブログを書いている方に回すというもので
題して「2023年自己紹介バトン」です。
下記はアメブロに書いた内容をそのまま転載しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ブログを書き始めてずいぶんと月日が過ぎました。
が、こうしたバトンを受け取るのは初めてです。
「シエナの坂道。。」のラファエラさんから
幻のバトンを渡して頂き、わ~お。
本当にあるんだねー!・・・などと感想を抱きつつ、いざいざ。
ハンドルネーム:
KANESEI (カネセイ)です。
ハンドルネームの由来:
これはわたしの額縁と小箱制作の屋号でございます。
カネはカナジャク(直角定規)、セイは名前の音読み
「直角をきっちり出す仕事をしますぜ」という意味で。
(いやスローガンで・・・。)父命名です。
アイコン:
イタリア・フィレンツェで木工修復を学んだ際に
修了制作で作った祭壇型額縁です。
家族紹介:
これはまぁ、そうですね、数人で暮らしています。
私の画像:
先日2月11日フィレンツェのリッカルディ宮殿の特別展
Christian Balzano の「FUOLI DAL MONDO」展で
ゆがんだ鏡に映ったわたし。雰囲気だけ。
居住地:
東京です。わりと長閑なところ。窓からは緑がたくさん見える。
出身地:
同じく東京。京王線沿線で、今よりもう少しだけ便利な場所でした。
趣味:
ううむ・・・趣味が実益を兼ねる部分も多いのですけれど
以前はピアノを弾くことが好きでした。
最近はめっきりなので再開したいと思いつつ早数年。
長所:
これって自分で全世界に向けて述べる勇気が中々ありません・・・。
あえて申し上げれば、手先が器用、でしょうか。
短所:
これまた自分で全世界に向けて・・・(以下同上)
気が小さいくせに尖っている。しつこい。
当然まだまだある。お恥ずかしくて書けない!
好きな諺:
その時々で変わりますけれど、今は「諸行無常」
こだわってしがみつく性格ですが
この言葉で手を放す気持ちに近づけるような。
好きな人や芸能人:
辻仁成さんのブログと猫沢エミさんのインスタを
読むのがとても好きです。
お二人の日々の様子や綴る言葉に励まされることが多いのです。
JINSEI STORIES | Design Stories (designstoriesinc.com)
Emi Necozawa/猫沢エミ(@necozawaemi) • Instagram写真と動画
好きな曲:
何だろう??色々あって載せきれない。
今はイタリアから帰って来たばかりなので
マスカーニの歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」の
間奏曲にしておきます。
わたしのイタリアに関する良い思い出も忘れたい記憶も、
諸々すべてまとめて「そんな時もあったねぇ」と
慰めてくれるような気がします。
(YouTubeは載せ方分からず・・・すみません)
好きな〇〇:
これまた何だろう??・・・好きな時間帯、にします。
なぜだか不明ですが、制作作業が一番はかどるのが
夕方4時から6時ころで、気持ちも手もジャンジャカ動く
わたしにとっての「輝ける2時間」です。
わたしのこの2時間は、それ以外の制作時間より
目が爛々としているのだと思います。
だけど毎日この「輝ける2時間」が降臨するとも限らない・・・。
今一番のマイブーム:
マイブームと言いますか、ここしばらく気になって仕方がないこと。
それは匂い。
日本って本当に「匂い」(良い香りも悪臭も含めて)が
少ない国だなぁと思います。
人間の体臭も、建物内も外気の匂いも
なんなら猫の背中の匂いも含めて、薄い気がします。
良し悪しは別として。
これは国民性なのでしょうか、それともわたしが感じるだけ?
個人的には匂い(良い香りも悪臭も含めて)は
何でも興味があります。
匂いは個性を表しますし、情報量がとても多いので
嗅いだ一瞬で色んなことを想像したり理解したりできるので。
今年の抱負:
お正月にも書いたのですが、今年はふたつ抱負をあげました。
ひとつの挑戦は先日のフィレンツェ滞在で
何とか達成いたしましたので良し。
こちらに関しては後日改めてお話させてください。
もうひとつは「人生の残り時間を考えて
計画を立て直してみようではないか」です。
行き当たりばったり人生も悪くなかったのですけれど、そろそろ。
最後に一言:
結局、大体の事はいままでブログで書き連ねてきた内容だったりして
でも改めて書き表してみると自分の現状を見直せたような気がします。
いやはや。こんなんで良いのでしょうか。
良いですよね、ハハハ、これにておしまいです。
お付き合いいただきありがとうございました。
「一回お休み」の巻 2月09日
諸事情により、本日 diario お休みです。
わたくし元気でおります。
ちょっとした息継ぎで・・・
▲これはクリスマスのご馳走・・・なつかしい。
また次回に!
よろしくお願いいたします。
皆さまもどうぞ、ゆっくりお過ごしください。
あなただけのカードケースはいかがですか 2月06日
この小箱(と言いましょうか)は
秘密用ではありません、カードケースです。
中央にイニシャルモノグラムを入れて
純金箔水押し。マイクロ点々で装飾して
軽くワックスを塗って完成しました。
箱義谷中店で購入しました白木の名刺入れ、
桐材で軽く、とても美しく仕上げてあります。
もちろんこのままカードを入れれば使えます。
この名刺入れに細工をしようと企みまして
綺麗に丸く加工された角を面取り作戦・・・
▲丸く加工された角に面取りラインを書きこむ。
▲開くとカードディスプレイにも。
ヤスリでせっせと角を落としてから
ルネッサンス風(やっぱりここに戻る)の
枠模様をボローニャ石膏で塗り
イニシャルとラインを線彫りして着色して
さて、完成でございます。
塗装による木地の反りや歪みを恐れましたが
問題ありませんでした。さすが箱義さん製品。
開きますと18枚くらいカードが入ります。
またもやオジサン・・・もとい
マッチョな雰囲気に仕上がったようです。
ビジネスシーンでちょっと目立つ
話題作りに一役買える、
オリジナルのカードケース。
お好みのイニシャルでお作りします。
世界にひとつ、いかがでしょうか。
「世界にひとつ、あなただけのために」とは 1月30日
フル・オーダーメイドのものを
例えば宣伝したり印象付けたいときに
使うフレーズ
「世界にひとつだけ」
「あなただけのために」
など、あります。
いささか使い古された宣伝文句です。
これを聞くと、その「もの」が
とても貴重で珍しくて得難い感じ、
それなりに高価でステイタスを表す。
そしてそれを持つ「わたし」もまた
特別な人物である気持ちにさせられます。
なにか心をくすぐるフレーズなのです。
先日ぼんやりと湯船につかりながら
考えていたのですが、
「世界にひとつ、あなただけのために」
作られたものって実は珍しくないな、ということ。
例えば、朝早起きをして作られたお弁当とか・・・
家族が作ってくれたか、自分で作ったにしたって
とにかく「世界にひとつ、あなただけの」お弁当。
あるいはプレゼントや旅先からの絵葉書も、
たとえその「もの」は市販品で沢山あっても
「あの人はきっとこれが好きだろう」
「これが欲しいと言っていたから・・・」
「遠くに来ているけれど、あなたを思い出している」
そんな気持ちは、広げすぎかもしれないけれど
やっぱり「あなただけのために」なんだなぁ。
気持ちが加わることで、ただの市販品から
「あなただけのため」のものに変わるんだ。
世界にひとつ、あなただけのために。
それはそこかしこに隠れていて、
大切で暖かな、そしてやっぱり貴重なことを
表しているんだなぁ・・・と思ったのでした。
そんな訳でして
KANESEIでもフル・オーダーメイドの
小箱をお作り致します。
あなたやあの人のイニシャルを入れて、
またはお好きな色とデザインで。
これもまた「世界にひとつ、あなただけのために」
のひとつのかたちです。
本業と副業 1月23日
いままで小箱制作はなんとなく
「副業」的な気分でおりましたので、
ホームページ内にあります「works 」には出さずに
「diario」でご覧いただくだけでした。
今回必要もあって、いよいよ「works」に
小箱を出すことにいたしました。
それにしても写真がひどくて恐縮です。
途中にある小箱の集合写真は
フォトグラファー浅野カズヤさんに
撮って頂いたものです。
プロの仕事の美しさ!
なぜ今まで出さなかったのだろう?
わたしは自称「額縁制作者」でありたいのだと思います。
小箱制作が片手間とか、額縁が上で小箱が下とか、
そんなことでは無くて・・・
やはり自分の根、基本、原点が額縁だからなのだろう、と。
わたしは「変化」が苦手なのです。
でも自分の変化って一番気付きづらいですけれど、
やっぱり様々変化しているのですよね。
自分も環境も変化しているのだから
その時に「これぞ」と思う事をすれば良い。
額縁も小箱も、今やどちらもわたしにとって
「これぞ」と思う事です。
そして「これぞ」と思える物に辿り着いたことに
感謝したいと思います。
諸行無常、有為無常
額縁制作者であり、小箱作家でもある。
今はそれで良し、でございます。
極小に極小を 1月16日
ホワイトゴールド箔を使った豆小箱です。
極小の小箱に極小の点々打ちで模様。
ホワイトゴールドとは
純金50%、純銀50%の合金です。
輝きが明るく錆びづらい。
銀より深くプラチナより華やか。
そんな雰囲気の金属です。
箔貼り作業も純金箔より純銀箔より
扱いやすくてとても作業しやすい。
古典技法にもおすすめです。
いかがでしょうか。
なぜかそこにいつも 1月12日
以前、やはりわたし同様に
ひとりで物を作っている方と
おしゃべりをしていました。
その方いわく
「特別に気に入っているわけでもなくて
でもなぜか売る気にもならなくて
ずっと家にある作品があるの。
気が付くといつも『傍らにいる』のよ。
なぜだか知らないけど、とにかく
いっつも近くに『いる』のよ!
こうなったらもうきっと、死ぬまで
身近に持っているしかないのよね~」
ああ、そうなんだ、やっぱり。
わたしだけじゃないんだ・・・。
なぜだか自分でも分からない。
だけど、ふっと気づくといつもいつも
ほんの少し離れた場所——棚の上とか
本の陰とか――にじっと佇んで
こちらを見つめるように「いる」。
そんな小箱があるのです。
▲今日もどこかからわたしを見ている・・・
わたしは物を擬人化して考えるのが癖だから
「見られている」と感じるけれど
もちろんそんなはずは無くて。
きっと無意識に、その作品をくり返し見ることで
自分の内面の何かを切り替えるとか
紐づけて思い出すとか
あるのかもしれません。
計画しよう 1月02日
明けましておめでとうございます。
今年2023年のお正月は週末ですので
お正月休みが短くて残念・・・ですけれど、
今日2日はまだ皆さまお正月休みでいらっしゃることと思います。
元日の初詣に近所の氏神様へ出かけましたら
近年見たことのない人出でした。
鳥居の下から数十メートル並んでお参りし
「やれやれ」と戻りましたら
帰るころには鳥居のはるか先の坂道まで列が続いていたのでした。
コロナ蔓延中で旅行や帰省はしないけれど
自宅待機でもなく、と言った感じのご家族が沢山。
なつかしい穏やかな雰囲気でした。
神社からの帰り道、タクシーや郵便局の車とすれ違い
介護施設には明るく電気が灯っていて、
お正月に働く方々を思いつつ。
31日は毎度のことながらお節作りで大わらわでした。
わたしはなぜか料理をする時は話しかけられるのが嫌いでして、
もくもくと淡々と作り続ける・・・
▲百合根とくわいを料理すると「お正月」な気分になる。
夕方には何とか料理を終え、カマボコや伊達巻の端っこなどを
つまんで年越しそばを頂き、さて。
今回もお重ではなくて大皿に盛ることにしました。
▲元日の朝に急いで庭から南天の葉を摘んで色どりに。
緑を足して取り繕う。
▲朝からお酒・・・お正月ですから!
▲そしていつものお雑煮。平和。
毎年お正月になんとなく、本当になんとな~く
抱負を考えるのですけれど
今年はひとつ挑戦を目前に控えているので
まずはそれを無事済ますこと。
この挑戦は成果が無くても良しとする、
いわば「誰にも頼まれていない、自分で勝手にやる事だし
ダメ元で!」と自分の負担にならない程度に、
でも熱血の本気でやってみようと思っています。
それから・・・
もう少し自分の人生に計画を立てた方が良いかもね・・・
あまりに行き当たりばったり、思い付きで
やり放題な人生を送って参りましたので
ちょっと人生の残り時間なども考えてみようではないか。
そんな風に考えているお正月です。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
あけましておめでとうございます 1月01日
旧年中はありがとうございました。
新春を迎え皆様のご多幸をお祈り申し上げますと共に
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
2023年 元旦 KANESEI
小さい小さい絵展 2022 12月26日
毎年、暮の恒例「小さい小さい絵」展への
テンペラ画模写出品は今年でなんと23年目・・・
眼差しが遠くなってしまいます。
当時生まれた赤ちゃんが、もう23歳ですって。
いやはや。
今年の展示、12月15日から21日まででして
すでに終わってしまったのですけれど
記録としてお話させてください。
夏にブツブツ言いながら描いた模写2点
黒い額縁を付けました。
この額縁は市販品でして
元はベージュでしたが塗装でお色直し。
左の文鳥と右のチューリップで額縁の上下を変えてみました。
装飾が上に来るか下に来るかで印象も変わります。
文鳥は純銀箔背景
チューリップは黄金背景。
どちらの模写も名刺サイズくらいです。
2023年もまた出品させて頂く予定です。
今年はなんだか落ち着かなくてこの2点のみでした。
2023年にはもう少し心落ち着かせて、
完成度も上げたいと思います。
Buon Natale 2022 12月24日
メリークリスマスでございます。
この写真は我が家で一番乙女な父が
撮影して送ってくれました。
この汽車のオモチャはわたしが幼いころ
12月25日の朝、枕元に置いてあったものです。
キャンドルはお仏壇の・・・!笑
東京は穏やかに晴れておりますが
大雪でお困りの場所もあります。
お仕事や勉強、お家のことで
お忙しくお過ごしの方々もいらっしゃいますね。
どうぞ皆さまお身体大切に、穏やかな週末を!
サイズは違っても幸せの大きさは同じように 12月22日
以前、展示会でお世話になっている方に
「大きさを変えてシリーズで作っても
面白いかもね」とアドバイス頂きました。
なるほど、それは楽しそう!
と思って作ってみました。
その方曰く「大中小とあったら
大抵わたしは中を選ぶんだけどね~!」と。
その気持ち、なんだかわかります。
昔話の「大きなつづらと小さなつづら
どちらを選ぶ?」みたいですね。
昔話とは違って
KANESEIの大きな小箱(変な表現)を選んでも
きっと幸せが来ます。たぶん。
中の小箱も小の小箱も
大きさは違えど幸せは同じくらいに。
そんな気持ちで作っています。
特技・寸足らず 12月19日
小箱の型紙を作っています。
トレーシングペーパーを
小箱の展開図にして
デザインを描きこんで転写します。
その型紙を作ると度々
5mm寸足らずになります。
なぜだ??
▲寸足らず。裾が寒々しい・・・
ラジオを聴いて笑いながら作るからか
「今日の晩御飯は」などと考えているからか
とにかく。
5mm足りない度にガッカリして
けっこう疲れます。
5mmの罠から抜けられません。
以前は作り直していましたが
(はいそうです、以前から何度も。)
もはや作り直す気もなくなった・・・
我ながら笑ってしまいます。
いや、笑い事ではありませんが。
ましてや皆さんにお話する事でもありませんが!
▲相変わらず寸足らず。開き直って使う。
でも言い訳をしますと
この型紙作りの時だけ、なのですよ
こんなに間違えるのは。
数字に弱い自覚はありますけれど
大抵ほとんど、ほぼ間違えません。
「あなたの特技は何ですか?」
「ハイ!5mmきっかり寸足らずに
型紙を作ることであります!」
気を付けます・・・
禅の友 2023年1月号 12月15日
以前に「仕事の時間 2」でお話した
額縁の撮影大会ですが、
その時に撮って頂いた写真がこの度
皆さんにご紹介できるようになりました。
曹洞宗が出版している冊子「禅の友」の2023年表紙を
一年間、KANESEIの額縁写真で飾らせて頂きます。
この冊子は書店では購入できませんが、
曹洞宗のお寺、学校や関連施設で配布しています。
また曹洞宗宗務庁にご連絡頂きますと
1冊80円+送料でお届けいたします。
1月号の表紙は、フィレンツェにある
バルディーニ美術館所蔵のレプリカ額縁です。
全面が輝く純金仕上げ、むくむくと膨らむ末広がりなデザイン、
とにかく派手でお目出たい雰囲気で
お正月向き・・・と言った感じです。
背景のバキッとした黄色で
これは編集者さんが選んでくださったのですが、
額縁の陰影や「激しさ」に負けず、引き立ててくれています。
▲キョーレツだけど、それが良い。
昨今、宗教的なことは敏感な内容で
あまり話す機会もありませんね。
わたしは仏壇と神棚がある家に生まれ、
日曜学校にも通い、
今は特定の信仰は持ちませんが
真言宗のお寺にあるお墓に入る予定…
半年後一年後が予測出来ないような日々、
今回この冊子に使って頂く事で
宗教について更に考える機会になり
心の支えとは。
こんな時こそ、背中にそっと手を当てて
「大丈夫だよ」と言ってくれるような「心の支え」が欲しくなる。
それは宗教かもしれないし、隣にいる人かもしれない。
自分自身でも良いのでしょうね。
上の写真は、表紙に使って頂いた額縁に冊子を入れてみた図。
自分で自分を額装・・・
セルフ・フレーミング!(そんな言葉はないかも?)
六角形の小箱が欲しいのだ 12月12日
わたしが普段作っている小箱は
基本的に四角形です。
と言うか、四角形だけです。
せいぜい角を面取りする程度。
本当は丸とか多角形の木地も
欲しいのだけどなぁ、無いしなぁ。
作るの大変そうだしなぁ。
・・・と思っていたのですがなんと。
六角形の小箱をついに手に入れました。
友人がお菓子や鰻のかば焼きに
まぎれて一緒に送ってくれました。
それも、この友人の手作りなのだとか。
(鰻もお菓子ももちろんとても嬉しいけれど
これが実は本命?!)
▲北海道の白樺を使った合板なのですって
コンピューターで計算してマシンでカット、
それから組み立て。
口で言うのは簡単だけど
実際の作業はとても大変です。
微調整につぐ微調整、なのです。
▲仕上げも美しい!
あまりに嬉しくて貴重すぎて
細工をせずに撫でまわして眺めています。
本当は量産して欲しいけれど
この友人の忙しさを見ていると
無理だろう、難しそう・・・
でも気が向いたら作ってほしい・・・
これに金箔貼ったら可愛いなぁ!
ブツブツ・・・ムフフ・・・
いやはや。
Mさ~ん!
日本唯一のボッティチェッリ 12月08日
今月1日から丸紅ギャラリーで開催中の
「美しきシモネッタ」展へ行きました。
皇居のお堀端にある丸紅ビルに
今年完成したギャラリーだそうで、
まさにこの一枚の作品のために作られたようなギャラリーでした。
▲ビル入口で迎えてくれたシモネッタ
整理券配布と聞いて並ぶ覚悟でしたが
すぐ入場でゆっくり見られました。
日本で所蔵される唯一のボッティチェッリ作品とのこと。
最初の印象は「思ったより大きい!」でした。
(作品サイズ:650×440mm)
彫刻と金のかなり力強い額縁に納まっていたのも
印象を強めていたかもしれません。
丁寧に描きこまれた部分―—顔やペンダント、
レースなど―—と、あっさりとした部分
(背中側の衣装や髪)とのコントラストが
一見未完成かと思わせつつも、その落差(?)で
描きこまれた部分の美しさが引き立っているようでした。
そして背景の窓の向こうの空の美しさたるや。
以前読んだ本で、レオナルド・ダ・ヴィンチは
「ボッティチェッリの背景は単純で趣も無くて
つまらない」と言っていた・・・と読んだ記憶がありますが、
わたしは昔からボッティチェッリの描く背景の風景画が好きです。
透明で透き通って、強い風が止まった、その瞬間のよう。
薄そうな空気感。
意味づけも無くスッキリとして、前景を引き立てます。
つまらない風景なのでは無い、
そういう風に描いたのよ!と擁護したくなる。
このシモネッタの背後の空もまた、雲さえ無いのだけれど
ただ青空があるだけでは無くて、
ほんの少し茜色に染まりつつある空なのです。
この何とも言えない陰影と趣きは、いつまででも
見ていたい気持ちにさせられるのでした。
▲丸紅サイトからお借りしました。
実物の色はこんなものじゃない、際立つ美しさ。
実は大学1年の頃、まだ一般公開されていない頃に
お世話になっていた先生のコネクションで当時社長室
(会議室だったか応接室だったか)にあった
この「美しきシモネッタ」を見る機会がありました。
その時は「わぁキレイ」という
子供っぽい単純な感想しか無かった記憶でした。
その後、テンペラ同好会に入り卵黄テンペラ画模写を経験し
ルネッサンス美術に興味が深まり、
卒業制作ではテンペラ画模写研究をし、
その後フィレンツェに留学して・・・
大学1年生の頃とはずいぶんと違う気持ちで
「シモネッタと再会」できたようです。
▲新聞広告、チラシ、チケット。
なぜカラーにしなかったんだろう?
ボッティチェッリが生涯を暮らした
フィレンツェの、ウフィッツィ美術館にある
彼の名画に比べれば小品だけれど、
この作品が日本にあって、見ることができて幸せだなと思います。
新年1月31日まで公開とのこと、
ぜひぜひお出かけくださいませ。お勧めです。
「美しきシモネッタ」 2023年1月31日まで
*チケットは現金では購入できませんでした。
クレジットカード、または交通系ICカードがあると便利です。
結局どっちも! 12月05日
初めて使うサイズの木地小箱で
作った新しい小箱です。
黒地に金と赤、地味なような派手なような、
でも好きな組み合わせの色です。
脱洋風って言ってなかったっけ、ですって?
ハイ、そうなんです。
そうなんですけれど、ほら
雲立涌文様ってありますでしょう?
あれを描こうと思ったら、こんな感じになりまして
似てますよね?
▲雲立涌 日本服飾史サイトよりお借りしました。
▲似ているのは波模様だけ・・・ですけれど。
▲すこしペイズリーにも似たような、アラブの香もするような。
▲桐木地小箱にボローニャ石膏
アクリルグアッシュで彩色。
なかなか脱洋風は難しい・・・のであります。
無理して脱する必要もありませんよね。
しばらく西洋風も東洋風も、ということで。
いかがでしょうか。
おじさんはマッチョである。 11月24日
箱義谷中店の展示会でのこと。
友人の友人(男性)がじっくり見てくださり
ぽつりと仰いました。
「ちらほらとマッチョな箱もありますね」と。
マッチョな小箱?
▲これらがいわゆる「マッチョな小箱」代表
どうやらそれは、わたしが以前から
「おじさん風」と表現していた
小箱なのでした。
▲そして選んでくださるのは女性が多い・・・
マッチョ好きな女性たち?!
そうか、なるほど!
これをマッチョなデザインと表現するのか!
そんな表現もあるんだなぁ・・・と
その場にいらした方々と盛り上がりました。
「マッチョ」と「おじさん」と
表現はそれぞれですけれど
やっぱり「感じること」はだいたい
同じなんだな、と面白く思いました。
おじさんはマッチョなのであります。
仕事の時間 2 11月21日
先日の雨の日に、我が家の座敷で
額縁の撮影大会が開かれました。
もちろんこれは仕事の一環でして
カメラマンさんと編集の方が
取り仕切ってくださいました。
狭い座敷が急きょスタジオと化し
わたしは面白くて面白くて、
でも邪魔をしないように片隅で
体育座りをして見学しました。
▲セッティング風景。三脚の足にはすべてソックスが。
畳に傷を付けないように・・・ありがとうございます。
ライトの角度、距離、暗幕の有無
ストロボの数、カメラの設定・・・
微調整に見えても撮影された写真の
明らかな違いがこれまた面白すぎて
プロの仕事に感嘆し続けました。
▲額縁の下にアクリルキューブを入れて高くすると
影が遠く柔らかくなるのですって!
今回は5枚の額縁と小箱をまとめて3パターン。
設営から終了まで4時間かかり
カメラマンさんの集中力にこれまた感嘆でした。
▲撮影を行列して待つ額縁たち。
心なしかウキウキして見える。
撮影していただいた写真は・・・もう本当に
「これ、本当にこの額縁ですか?!」
「この額縁、こんなに綺麗だったっけ?!」
あるいは
「細密に撮れて彫りの粗が見える!ひぇぇ」
「小箱ったらカーワイーイ♡」
という驚きと感動でした。
▲前回の打ち合わせ時に仮撮りしたもの(右の書面)を
ふまえて、タブレットで撮影した写真をその場で確認。
デジタルの進歩にも驚き。
いやぁ~・・・びっくり。
一事が万事って、これですね。
完成した写真を拝見すれば、
ここに至るまでの準備も精神力も、人柄までも
ひとつひとつが結果に繋がるのが分かる。
穏やかに冗談も言いながら、でも
淡々と着実に撮影を進めてくださいました。
これらの写真は来年ご覧いただける予定です。
乞うご期待です!
松屋銀座「色のカタチ」ありがとうございました 11月17日
11月9日から1週間開催いたしました
松屋銀座での催事「色のカタチ」は
おととい15日夕方に無事終了いたしました。
お越しくださった皆さま
そしてお買い上げくださった方々
ありがとうございました。
このイベントで今年の「ひとしきり」がつきました。
まだ11月半ば、ちょっと気が早いですね。
でももうクリスマスのイルミネーションや
BGMも始まっていますから、
あっという間に除夜の鐘でございましょう・・・。
ふり返れば今年3月に大阪の
阪急うめだ本店での催事を皮切りに
小箱を担いで巡業(ちょっと違いますかな)を開始しましたが
5月に銀座松屋「和の座」催事
9月に箱義谷中店で一人展示会、
そして11月に松屋銀座の新しいスペース
「遊びのギャラリー」での催事参加と
怒涛の小箱巡業と相成りました。
小箱をガサゴソ作る合間に額縁も作り
テンペラ模写も少し描き、
月曜にはアトリエLAPISの講師をして
TokyoConservationの絵画修復の助手も続け・・・
おかげ様で近年稀に見る充実ぶりでした。
始めたらきりない程に心配事は尽きませんが
いま自分に出来る事とやりたい事を
「やってみようじゃないか!」と行動できたようです。
松屋の帰り道、小さな打ち上げをしました。
寒空でしたが提灯の並ぶ外席に座りこんで長話を。
来し方行く末、心の持ちよう、
乙女座と山羊座の関係と謎が深まり、
お悩み相談も少し(いや沢山かな)して
「催事のひとしきり」と同時に
「心のひとしきり」もした夜でした。
爽やかな疲れと晴れやかな気持ちで
今日からまた進みます。
ありがとうございました。
秋の実の小箱 11月14日
豆小箱
ただでさえ「小箱」ですのに
輪をかけて小さい豆小箱ですが
その小ささ故に装飾するのも特に楽しいものです。
中世の模様をパスティリア(石膏盛り上げ)で入れて
赤ボーロに純金箔を水押し
今回は古色を付けてみました。
パスティリアで入れた丸い点々が
秋の実のように見えて、
なかなか気に入っております。
外側寸法:35×35×23mm
大切な指輪をひとつ入れて。
いかがでしょうか。
展示会「色のカタチ」に出品しております。
明日15日夕方5時までの開催
ぜひお立ち寄りくださいませ。
「色のカタチ」ito to ki no katachi
松屋銀座 7階 遊びのギャラリー1979
11月9日(水)~11月15日(火)
初日12時開場
最終日午後5時閉場
星輪違文小箱 11月10日
「たまには作ろう東洋風」と
謎のスローガンを掲げておりますが
先日の屈輪文につづきまして
こちらの小箱は輪違文様です。
輪違とは輪を交差させた模様でして
一番見かけるのは「花輪違(花七宝)」でしょうか。
輪の中央のひし形部分に花が描かれているもの。
この小箱には花の代わりに星を入れました。
言うなれば「星輪違」「星七宝」。
星の中央の点はパスティリアで
ぽちっと盛り上がっています。
▲手のひらに乗るサイズ。
可愛くできたかな、と思いつつも
星のせいで純和風とも言えない雰囲気。
それもまぁ・・・模索中ということにします。
それにしても最近は黒やグレー色の登場が多いのですが
と言うのも、どうやら華やか系より
モノトーンに近かったりシックな色使いの方が
人気がある・・・との分析。(当社比。なんちゃって。)
ふり返るとピンクや水色が多かったかもしれません。
しばらくモノトーン・シック路線も
これまた模索してみようと思います。
昨日9日から松屋銀座7階で開催の
「色のカタチ」に出品しております。
どうぞ秋の銀座へお越しくださいませ。
わたしは下記のスケジュールで店頭におります。
9日(水)16:00~20:00
10日(木)休
11日(金)12:00~17:00
12日(土)10:00~15:00
13日(日)10:00~15:00
14日(月)休
15日(火)10:00~17:00
「色のカタチ」ito to ki no katachi
松屋銀座 7階 遊びのギャラリー1979
11月9日(水)~11月15日(火)
初日12時開場
最終日午後5時閉場
竪琴をひく人のとなりに 11月07日
イタリアのシチリア島には
ローマ時代(4世紀頃)に建てられた
villa romana del casale
ヴィッラ ロマーナ デル カザーレ という
とても美しい屋敷跡があります。
直訳すると・・・
「ローマ時代の農村邸宅」でしょうか。
それはそれは凝った精密なモザイクがあり
19世紀に発掘されて今も美しく保存されています。
行ったことありませんが。
・・・行きたいなぁ。遠いなぁ。
今日完成した小箱はこのヴィッラの
床モザイク模様をお借りしました。
組紐模様です。
▲桐木地小箱にボローニャ石膏、パスティリアで装飾
赤色ボーロに純金箔水押し、古色仕上げ
モザイクは色とりどりで華やかですが
小箱は古典技法の純金箔の古色仕上げで。
▲外側寸法:45×45×20mm
▲ヴィッラの床モザイク。写真はお借りしました。
4世紀イタリアに、今と同じような
古典技法が存在していたかというと
おそらく未だ無かったと思いますけれど、
トーガを着て優雅に海を眺めながら竪琴をひく人、
その横にこの小箱・・・
などと想像してしまうのでした。
明後日水曜から松屋銀座7階で開催の
「色のカタチ」に出品いたします。
どうぞ秋の銀座へお越しくださいませ。
お待ちしております。
わたしは下記のスケジュールで店頭におります。
9日(水)16:00~20:00
10日(木)休
11日(金)12:00~17:00
12日(土)10:00~15:00
13日(日)10:00~15:00
14日(月)休
15日(火)10:00~17:00
「色のカタチ」ito to ki no katachi
松屋銀座 7階 遊びのギャラリー1979
11月9日(水)~11月15日(火)
初日12時開場
最終日午後5時閉場
ぐりぐり屈輪模様 10月31日
さて、脱洋風模様第一弾。
さりとて和風とも言えないのですが
屈輪模様小箱を作りました。
▲小箱の模様展開図
屈輪(ぐり)模様とは
中国の南宋時代(日本の平安時代末期頃)
に作られていた模様でして
渦巻きが正に「ぐりぐり」している
ところから「屈輪」と言われているとか。
▲ふむふむ、こんな感じ
上野にある東京国立博物館所蔵の
犀皮盆の屈輪模様を使わせて頂きました。
▲画像は東博サイトからお借りしました。
西洋から極東の日本へたどり着く手前
中国で止まってしまった。
まぁ大きく「東洋」と言うことで、
ルネッサンスから離れただけで第一歩です。
輝く純金に連なる渦巻き模様。
東洋の模様を西洋の技法で。
なんだかちょっと呪術的な雰囲気に
なってしまったのですが、
東西折衷で謎めいていて
これもまた「秘密の小箱」らしい
仕上がりになったと思っています。
11月9日から開催いたします展示会
「色のカタチ」に出品いたします。
ぜひ実物をご覧ください。
「色のカタチ」ito to ki no katachi
松屋銀座 7階 遊びのギャラリー1979
11月9日(水)~11月15日(火)
初日12時開場
最終日午後5時閉場
改めて考えてみる。 10月24日
以前すこし、イタリアの知人に
言われた事をここで書いたことがあります。
「なぜ日本に生まれ育ったのに
日本伝統の模様を使った小箱を作らないの?」
と言われた、という話。
じつはその前の会話がありました。
この知人にわたしは軽い気持ちで
「イタリアで小箱を販売できたらと
思っているのだけど」と言ったのです。
そうしましたら割とハッキリと
「君の小箱はミラノでは売れないよ。
もっとモダンなデザインじゃないとね。
こういった品物をイタリアで売るのは難しい。」
と言われました。
ちなみにこの人はミラノ近郊在住で
全く関係のないお仕事をされています。
でも美術に関して知識と眼を持っている。
わたしの小箱はヘンテコで古臭いのか?
売れないって簡単に言ってくれたもんだ。
それは単なるアナタの感想だろう。
やってみなくちゃ分からないでしょう!
・・・内心ムッとして
同時に「日本の伝統模様を入れた小箱を
作ってみたら?」と言われたことも
すっかり「お蔵入り」させていました。
だけど、後から冷静に考えてみれば
確かにそうです。
なぜに洋風模様にこだわる??
単に好きだから、だけど
別にこだわっているわけじゃない。
じゃぁなぜ和風模様の小箱を作らない?
前にも少し作ってみて楽しかったじゃない?
あの人の一言で避けていたのでは??
せっかくアドバイスをくれたのに。
前置きが長くなりましたが
そんな訳でして、最近すこし
日本の伝統的な模様や中国伝来模様など
改めて本を見つつ考えております。
気持ちの扉を開けたいと思っています。
秋のしつらえに 10月20日
奈良東大寺、二月堂の装飾を
参考にした小箱を3つ作りました。
そのうちのふたつは内側に布を貼らず
白木のままに仕上げていました。
茶道で使う香合(お香を入れる蓋物)に
もしかしたら使えるかも・・・と
企んでいたのです。
先日の展示会で、お茶を教えている
友人がひとつ買ってくれたのが
3つのうちのピンク小箱でした。
さっそく飾った写真を送ってくれました。
▲秋のしつらえ
この友人はピンクが良く似合う人で
とても気に入ってくれたようです。
普段、何を入れたら良いのかしら?と
問われることが多い小箱ですが
「アクセサリーでも小石でも貝殻でも」
などとお応えしています。
あまり目的を決めずに作っていますが
今回ばかりは特別でした。
お勧め・・・と言いましょうか
想像した通りの使い方をしてもらえて
とても嬉しい。
ニヤニヤしながら写真を眺めています。
また始めてしまった点々打ち 10月17日
要するに、好きなのですね
わたしはこのマイクロ点々装飾が。
月曜日の古典技法「アトリエLAPIS」で
いそいそと新しいマイクロ点々を
開始しましたところ
生徒さん方に「あら先生、新作ですか?」と。
”嫌がっていたのに、また始めるのね~(笑)”
なんて感じなのでした。
▲純金箔を2枚重ねで貼った上に下描きを重ねて
自分でも「もう当分やりたくない」と
思っていたはずなのだけど
ムラムラと再開欲求が出たようです。
今回の純金箔とは点打ちの力加減が
全く違うので面白いのです。
たった数ミクロンの厚さの箔でも
(2枚重ねで貼ってありますけれど)
細いメノウ棒で点打ちをするだけで
ホワイトゴールドはカツカツと硬く
純金箔はヤワヤワニュルニュルした
感触の違いがあります。
▲ニードルで下描きをなぞって写します。
純金箔の方が柔らかい分だけ楽で
作業も軽快に進みます。
▲とは言え2時間点打ちしてここまで。
相変わらず根気がいる作業は
アトリエLAPISで生徒さん方とご一緒に。
もくもくと石膏を磨き、木を彫り
線描きをし、箔の繕いを続ける生徒さんに
励まされながら隣で気長に作業します。
思い出の品と化す 10月10日
2020年春以降、増えた持ち物に
衛生管理道具、がありますよね。
替えマスクや除菌グッズなどなど。
今や最初の頃の戦々恐々とした感じは
減りましたけれど、それでも今も
「やつらはそこにいる」のですから。
除菌はスプレー式やボトル入りジェル。
皆さまはどんな品をお使いでしょうか。
わたしも当初はいろいろと試しました。
▲ビュリーの紙石鹸は美しすぎ。香りも最高。
▲サンタ・マリア・ノヴェッラ薬局のハンドジェル
ボトルに一目ぼれ
▲2020年春にイタリアで友人から貰ったハンドジェル。
2月、すでに入手が困難になりつつあった頃でした。
帰国時の空港や飛行機で使えてとても助かりました。
だけど結局、今は普段出かけるところの
お手洗いには石鹸は完備されていますから
紙石鹸はまだ一度も使っておりませんし、
除菌スプレーはそこかしこにあります。
ジェルボトルはかわいいけれど大きすぎて
持ち運びには不便だし、
イタリアのジェルはなんだかもったいなくて使えず。
結局、思い出の品と化しつつあります。
紙石鹸の香りはもうずいぶん消えました。
ジェルもそのうち蒸発しちゃうのかな?
いや、もったいないですよね。使いましょう。
ちなみに、わたしの手荷物はとても少ない。
いかにバッグの中身を少なくして
軽くするかが大袈裟ですが命題のひとつです。
今のところアルコールのウエットティッシュが
一番便利、と思っております・・・。
手以外も拭けますし。
ただ、ゴミが出るのが難点なのです。
一長一短でございますなぁ。
これからが正念場 10月06日
2日に無事「秘密の小箱展」終了を迎え
気が抜けてぼぉっとしておりましたら
風邪気味になり、でもまぁ
それだけ緊張感を持つ機会は大切!と
自分を納得させつつ過ごしております。
今回の展示会では数多くのお客様にご覧いただき
とてもとても嬉しい時間でした。
そしてお買い上げいただくことができました。
(目標としていた売上の倍以上でした。)
友人知人、お世話になった先生や
取引先の方々など、本当に有難いことです。
丹精込めて作った物を買って頂く嬉しさと、
同時に申し訳無さも感じています。
家族が「お祝いで買って下さったんだねぇ。
次の展示会をする時にまたご案内を送ったら
うんざりして嫌がられるかもね・・・」と言う。
うう・・・グサッと心に刺さる。
確かにその通りですよね。
暗に「また買ってくれと言われている
気持ち」にさせてしまうかもしれない。
後ろめたい、と言うのでしょうか。
見てほしい、買ってほしい、だけど
負担に感じてほしくない・・・
我ながら欲深いことです。
展示会(個展)をひらく意味と目的
気持ちと考え方、仕事としての心構え。
今が何か、わたしの「今後の作家活動」の
正念場の様です。
もちろん、今回の展示会でご購入くださった
方々全員が「ご祝儀購入」ではなく
良いなと思って下さったからのご購入なのも
理解しております。
最初は友人知人に買って頂くのも構わない。
「わたしの後ろに小箱がある」のだ。
でもこれからは
「小箱の後ろにわたしがいる」ように
なりたいし、そうなるのが本来でしょう・・・。
この先に不安がいっぱい。
これはすべての作家が通る道。
今更ながら痛感しています。
「応援してくださる方々がいるのだから
心を込めて作り続けるのがベスト、
それしかない!」なのであります。
「秘密の小箱展」ありがとうございました 10月03日
9月23日から箱義桐箱店 谷中店にて
開催いたしました「秘密の小箱展」は
昨日10月2日に無事終了を迎えました。
お越しくださった皆さま方、また
お買い上げくださった方々に
心よりお礼申し上げます。
ありがとうございました。
この場でのご挨拶をお許しください。
「中に入れる物が有っても無くても良い」
小箱は額縁とは全く違う
制作の楽しみがあって、
どちらも私を虜にしてしまう。
小さな箱にわたしの「好き」を
詰め込んで作っています。
その箱を開ければ、持ち主だけの
深遠な宇宙が、秘密が存在する・・・
というような理想を追っています。
夢のような展示会の時間は終わり
今日からまた現実生活に戻ります。
額縁の世界と小箱の世界を
行き来しながら
「古典技法KANESEI」を前進させて
参る所存です。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
何かが変わった 9月29日
ようやく最近、住宅街の空いた道など
マスクを外して歩けるようになりました。
そんな道ですれ違う人が
ひとりきりなのに満面笑顔だったりすると
「あら、あふれる笑顔があるとは
なんて幸せなのだろう。羨ましいなぁ。」
と思います。
ずっと以前だったら
「ひとりで笑っちゃって変な人」と
思っていたものです。
でもいつのまにか
ひとりで笑顔の人を見て
わたしも笑顔になってしまうような
心境の変化があったようです。
なにが変わったのかは我ながら不明です。
年齢でしょうかね?
悪くない変化でございます。
「秘密の小箱展」はじまりました 9月24日
相変わらず大騒ぎをして準備して
開催に漕ぎつけました
「秘密の小箱展」でございます。
台風の近づく金曜日の朝に搬入・展示
そしてお客様をお迎えしました。
▲小箱の他にテンペラ画模写、小さい額縁も置いています。
友人・知人も早速来てくれました。
緊張している時に知人の笑顔を見られるのは
本当にうれしいことです。
谷中という場所柄、通りがかりで
立ち寄って下さる方々も。
会場ギャラリーの「箱義桐箱店」へ
ご用でいらしたお客様と
思いがけず色々なお話が出来たりと
久しぶりに「初対面の方々と
お話をする楽しさと緊張感」も思い出しました。
▲総勢75点の小箱の全員集合
毎度のことで自分でも呆れますが
心は浮足立って焦ります。
お化粧もし忘れ(マスクを最大限に
広げて前髪を下して隠しました)
お昼休憩で気が抜けて居眠りして、
なんともトホホな面もあった初日。
本日2日目も台風大接近中ではありますが
昨日よりは落ち着いて店頭に立てそうです。
雨が心配ではありますが
お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。
お待ちしております。
▲千駄木駅から徒歩数分です。
箱義桐箱店 谷中店にて
9月23日(金)~10月2日(日)
10:30~19:00 金曜土曜日曜のみ営業
13時より17時まで在廊いたします。
その時が来た 9月22日
もう延々とずっと作業を続けて
アトリエLAPISの生徒さんには
「もはやわたしのライフワークです」などと
宣言して苦笑いされていた小箱が
ようやく、やっと、とうとう(しつこい)
完成いたしました。
いやぁ、続けると終わる時が来るのですね。
永遠に終わらないんじゃないか・・・は
大袈裟ですけれど、途中でもう
投げ出すだろうと諦めかけていました。
▲右の銀色の棒(メノウ棒)で点々を入れる。
形状サイズは鉛筆とほぼ同じです。
▲ライト付きルーペが役立ちました。
展示会が目前になって
「ここで完成させねば永遠に完成しない」と
腹をくくった次第です。
茶色ボーロにホワイトゴールドの水押し。
マイクロ点々でダマスク模様を入れました。
▲側面にも模様は繋がっています。
ほんのりとボーロの暖色を感じられる。
迷いに迷い、中は濃いピンクに。
改めて眺めても気になる点は多々あって、
でもまぁ一山越えられたような気がします。
記念碑的小箱になりました。
明日9月23日より開催の「秘密の小箱展」に
出品いたします。
どうぞお越しくださいませ。
サクランボと影 9月19日
マーシャルのサクランボ模写を
終えた小箱が完成しました。
サクランボには窓が写っていて
窓の向こうは青空・・・というのが
感じられます。(オリジナルの絵から)
明るい窓と青空、その光でできる
サクランボの影。
周囲は黒で中は真っ赤にしました。
ちょっと人形劇や紙芝居を思い出しました。
桐木地にボローニャ石膏、
アクリル絵の具で彩色、艶消し仕上げ。
内側に赤い別珍の布貼り。
9月23日からの「秘密の小箱展」に出品します。
ぜひお出かけください。
有り難や 9月15日
小箱にサクランボの絵を
模写しています。
マーシャルの絵はとても可愛いのです。
いつもは卵黄テンペラで描きますが
今回はチューブに入ったアクリルガッシュ。
テンペラは、卵黄メディウムを作って
描く都度に顔料と水と混ぜて絵具を作る。
チューブに入ったアクリルガッシュは
そのままパレットに出して水で溶くだけ。
なんたる簡便さ、手軽さ!
チューブ入りの絵具が販売されたとき
きっと世界中の絵を描く人々にとって
革命的だったことだろうなぁ・・・と
久しぶりにチューブ絵具で絵を描いて
今更ながら有り難味を感じております。
それは本当なのか? 9月12日
「継続は力なり」と思って
続けていることが幾つかあります。
止めるのはすぐだし
一度止めると再開が難しいこともあるし。
▲「小さい絵」展のテンペラ模写を始めました。
一枚は黄金背景、一枚は銀背景。
そう思って生きてきましたが
やっぱり色々、止め時というか
潮時ってあるのかもしれません。
▲メノウで磨いてマスキングを剥がす。
金は傷がついたのでちょっと繕い。
いや、「当たり前だろう」と
思われるでしょうけれども
止めるにも勇気が要りますでしょう?
▲卵黄メディウムにいつもは米酢を入れますが
今回はイタリアの白ワイン酢を入れたら
部屋中が酢のにおい・・・入れすぎたかも。
止めるのは続けるより簡単、と
思っていましたけれど
そうでもないなぁ・・・
▲描画に集中せずぐるぐる考えていた。
金の繕いも失敗した。
おまけに蚊に刺されて痒い。
刺されたのは1ヵ所なのに関係ないところまで痒いのはなぜ?
今日はもう作業しても無駄、お終いに。
こんな日もある・・・いや、自業自得?
「ひとつ止めれば次が来る」
なんてことも聞きますが
本当ですかね?
実は、止めると決めたときは既に
無意識にでも次を決めているから
なんじゃないか??
どうでしょうね。
ようやく完成、夜空の小箱 9月08日
額縁でも小箱でも
作りはじめたけれど途中で迷い始めて
「決まるまで様子見」として放置して
すっかり数年経ってしまうことがあります。
それらはいつも作業部屋の片隅の
すぐ目に留まるところに居て(あって)
ああごめんね、まだ決まらないから
もう少し待ってね・・・と言いつつ。
この小箱はそうして2年半が過ぎました。
中央の丸い彩色部分、天使かな
紋章かな、どれも釈然としなかったけれど
イタリア・パドヴァにあるスクロヴェーニ礼拝堂
天井画の写真を見ていて「これだぁ!」
と思い立ちまして、星空模様にしました。
ようやく完成、やれやれ一安心です。
出来るときは出来る。果報は寝て待て。
(ちょっと違いますかな?)
パスティリア(おなじみの)と純金箔
小さな点々打ちを入れて盛沢山な装飾に
純金泥で星を描きました。
けっこう可愛い・・・んじゃないかな。
家族に見せたところ「いままでで一番好き」と。
「10万円で売りに出そう・・・」と言うので
そんな値段で買ってくれる人は居るかしら
と答えました。そうしましたら
「もちろん売れ残るでしょう。
そうしたらちょうだい・・・フフフ。」
褒められたんだか何だか分からない。
ともあれ夜空の小箱、いかがでしょうか。
9月23日からの「秘密の小箱展」に
ぜひ実物を見にお出かけください。
桐木地小箱にボローニャ石膏
パスティリアでレリーフ、赤ボーロに純金箔、メノウ磨き。
中央にアクリルガッシュと純金泥で彩色
内側にライトグレーの別珍布貼り。
モッコウバラの教訓 9月01日
我が工房自慢の黄色モッコウバラ、
先日どうも葉が少ないし茶色いと気づきました。
やや、水やりが足りなかったか?と
早速バケツで水を運びましたら、なんと。
間近で見たら物凄い数の・・・
うう、書くのも恐ろしい・・・
2センチほどの毛虫がぎっっっっしり。
▲ちょっと息継ぎで夏の雲。
黒い物体はトーマス転炉の展示。
覚悟を決めて、家中の殺虫スプレーを
かき集めまして(キン〇ョールとか
フマ〇ラーとか、蚊用に準備したけれど)
煙幕になるくらい吹き付けたのです。
こちらまで眩暈がしそうでした。
黙々とスプレーしまくったわたしですが
心の中ではギャー!ウワワー!!と
叫びまくりでした。
▲思い出すのも凄まじいので更に息継ぎ。
また別の日の晩夏の青空とトーマス転炉。
ひとしきり後、地面には蠢きが無数に。
それを見ながらふと「小野妹子」を
思い出していましたら、いやに静かな
風が吹き抜けた夕方でした。
オノノイモコ・・・
イモコ・・・イモ・・・イモ・・・
ごめんね。
なにか罰を受けそうです。
教訓として・・・
大切な木ならマメにチェックするべし。
スプレーは効く。備えあれば患いなし。
やるべしやるべし。 8月29日
上手く行かないったら
上手く行かない。
どうにもこうにも。
だいたい建材の木地に
細かい彫刻をしようと思ったのが
間違いなのですよ。
・・・材料が悪いから?
いや、それもひとつだけれど
やっぱりわたしの技術が足りない。
見通しも甘い。
こうなったら自分との闘い。
諦めるもんか。
どうにかこうにか
完成させてやるのじゃ。
フンフン!(鼻息)
乞うご期待であります!!
小さな箱に詰め込んで 8月25日
先日の夜、ぼんやりとしていたら
親友からメッセージが届きました。
「こんな文章を書きました」と。
なんだかとても嬉しくて、
高校時代、制服を着ていたころの彼女と
母になった今の彼女と
わたしが知らない幼いころの彼女の姿が
輪っかの中で繋がったイメージ。
心の一部分は今も変わらないままね。
ぜひ読んでみてください。
あやちゃん、ありがとう。
仕事の時間 8月18日
先日、雑誌の取材をうけました。
暑い中を我が工房まで来てくださった
ライターさんとカメラマンさんは
どちらも女性でした。
わたしの経歴や留学中のこと
額縁についてや制作の上での気持ちなど
お話したのですが、当たり前ですけれど
プロの方がわたしに興味を持って
穏やかに笑顔で話を聞いてくださるのは
照れますけれど、でもとても気持ちが良い。
そしてわたしのポートレートや
額縁、小箱の写真を撮って頂きました。
華奢な女性が大きなカメラを持って
色々な角度から何枚も撮ってくださる。
撮影する対象への気持ちのようなものが
彼女の体全体からワァッと溢れ出て眩しい。
これまた当たり前ですけれども
プロの方が撮影して下さるって
緊張もするけれど、なんだかやけに
嬉しくなったのでした。
他の人の「仕事の対象」になって
現場で目の当たりにして
じわじわと圧倒されたようです。
そして気持ちが引き締まり、
励まされる午後でした。
そんな時もあるのさ 8月11日
先日完成した小箱は
古典技法の純金箔で
ゴリゴリに古色を付けました。
わー、かーわいーい・・・自画自賛。
にへらっと笑ってしまいました。
だけど。
こんなズタボロの小箱を作って
自分で喜んでいりゃ世話無い。
ひとりで目を輝かせていても
喜んでくれる人はいるのかな?
なんだか最近、自分で作った物の
良し悪しが良く分からないのです。
これは世に言うスランプ?
いや違いますね、単に自信が無いだけ。
何気なく言われたひとことが気になるだけ。
まぁ良いか・・・。
そんな時もありますさ。
すべては暑すぎるのが悪い、ということで。
開き直って愛を貫く 8月04日
わたしはたまに、ご注文の仕事以外に
古い額縁の再現をしています。
いわば「作りたい額縁を自分の為に」
チャレンジしています。
それは楽しく悩み多い作業です。
▲見本写真を見ながら彫り彫り。
写真では凹凸や細かい部分が分からないことも。
その時はその時、想像で補う・・・
美術館に納まっているような古い額縁を
集めた写真集(額縁本)に載っている
たった1枚の写真を参考にして
自分なりに考察して再現しても
正しいのか間違っているのか
分かりません。
▲石膏を塗り始めたらいつものスローガン
「手早く丁寧に」・・・これ目標。
イタリア・・・せめてヨーロッパに
住んでいれば、実物とは行かずとも
同じ時代の同じ地域で作られた
似たような額縁の実物を間近で見て
答え合わせもできるのに。
▲ボーロの色は本に記載されている。
分からなければイタリアの額縁史先生に尋ねてみる。
今回は「rosso scuro」の記載、暗い赤色。
イタリア人の知人に先日
「君はなぜ古典技法額縁を作るんだい?
日本は世界に誇る文化と歴史があるでしょう?
小箱のデザインモチーフにしたって
日本の伝統的な模様が沢山あるじゃない??」
と問われたのでした。
なんでわざわざ遠いイタリアなんだい?
なんでって言われても。
わたしも20代に始めたころは
こうなるとは思っていなかったのだけれど。
でも熱中できるものに出会ってしまった!
遠く離れた日本に生まれ育って
古典技法額縁愛に目覚めてしまった!
これを運命というのか
成るべくして成ったというのか。
「これぞ」と思えるものに出会い
それを続けることができるのは
人生でこの上ない幸せ。
我ながら物好きだなぁと思いつつ
もはや額縁からは離れられない・・・
と、諦めて開き直って
額縁愛を貫こうと思っています。
・・・独り言でしたね
どなたかに聞いていただきたかったのです。
理想のおじさん像 8月01日
わたしがこのブログのなかで
自作の額縁やら小箱を「おじさん風」と
表現しておりますが、つまり
それはどんな感じなのか??
理想のおじさんとは?
わたしのイメージする「おじさん」とは
ひげを蓄えた恰幅の良い中年以降の男性。
苦み走ってカリスマも眼力もあって
一筋縄ではいかない人物。
それでいて青年のころの様子も目に浮かぶような。
ホルバインが描いたヘンリー8世の肖像画とか
ベラスケス、ティツィアーノ、ルーベンスや
レンブラントが描いた自画像のような
そんなイメージなのです。
(あくまで絵画から受けるイメージのみ。
実際どんな人物だったかは別!)
▲ハンス・ホルバイン作「ヘンリー8世」1537年頃
Wikipediaよりお借りしました。
いくつかの額縁や小箱が完成したとき
「なんかオジサンっぽいな~」と
ぼんやりとした感想を持っておりました。
(かく言うわたしは地味なオバサン・・・)
上記の人たちを思い起こさせるような
額縁や小箱・・・のつもりだったのですが
考えてみれば図々しいですね!
彼らに認められて傍に置いてもらえたら
それはもう最高じゃないですか!
おじさん風をあえて目指しはしませんけれど
今後も敬意と愛情をもって「おじさん風」と
表現してまいる所存であります。
そしてお姫様風、熟女風のものも追及したい。
(熟女風小箱はちょっとイヤかな・・・)
などと思っております。
落ち着くのじゃ。 7月28日
いよいよ本格的に暑い毎日になって
作業部屋のカーテンを閉めて
手元のランプだけで作業しています。
明るいだけで暑いような気がしてしまう。
9月後半に初めての「ひとり展示会」を
予定しておりまして、これは一般的には
「個展」と呼ばれるのだと思いますけれど
ちょっと大げさなような感じがして、
なんとなく違うような気がしてしまう。
心と頭が右往左往しつつも
時間は着々と過ぎていく夏でございます。
気持ちを落ち着けたい。
黒と赤とおじさんと 7月25日
嗚呼、またしても、これまた
パスティリアなのでございます。
ボローニャ石膏をウサギニカワに溶き
面相筆で垂らし描きしてレリーフにする。
パスティリア装飾をいたしました。
▲面取りした桐木地小箱にパスティリア
黒の下には補色の赤を塗って、磨り出しました。
家族に見せたところ
「・・・地味だねぇ・・・」とのこと。
意外な感想です。
黒と赤って地味でしょうか?
黒ってけっこう派手な色だと思うのですが。
▲表に合わせて中にも赤い布を。
フィレンツェ伝統工芸のモザイク
ピアスを入れてみました。
黒い背景に真っ赤なサクランボです。
やっぱり赤と黒ってハッキリしていて
派手・・・とは言わずとも
強い色ではあるようです。
そしてまたもやこの小箱、ちょっと
おじさん風味に仕上がりました・・・。
中身も器も欲しいから 7月21日
わたしが小箱好きなのはもう
言わずもがな、ではありますが
ガラスの小瓶も好きです。
とくにマイユの瓶が好きなのです。
黒い地に金の文字
柔らかくカーブしたガラス瓶のかたち。
マスタードが欲しいのが瓶が欲しいのか?
どっちも!であります。
大きな瓶を収穫(中を食べ終わり)して
ホクホク並べたけれど
小さいほうがかわいい・・・
ということに気づく。
うむ。次は迷わず小瓶を買おう。
▲空き瓶は小ねじを入れるのにぴったり!
だけど、ラベルシールが剥がれない。
昔は食べ終わったら洗って
しばらく水に漬けておけば
ラベルはすっきりと剥がれたのに
最近は溶剤で拭かないと剥がれなくなりました。
きっと濡れるとすぐ剥がれちゃうラベルは
不便に思う人たちも多いのでしょうけれど。
なんだかなー・・・
と思いつつラベルをゴリゴリ剥がし
でもやっぱり集めてしまう
マイユの小瓶のお話でした。
ここぞとばかりにパスティリア 7月11日
先日の「木地に直接パスティリア小箱」
の仕上がりが気に入りまして
さらに3つばかり追加で制作中です。
桐の木地は柔らかくて木目も
開いている(と言うのでしょうか)ので
トノコを塗り磨いてから下描き。
そしていつもの石膏垂らし描き
「パスティリア」技法の登場です。
ここ最近しつこいくらい
パスティリアばっかり!
好きだから楽しい、良いのです。
こういう時って何か背中を押されるような
「パスティリアの流れ」があるので
逆らわず流れるままにしています。
そうすると心身ともに平穏に楽に
制作が出来るように思います。
見えすぎちゃって困る・・・ 7月04日
最近、細かい作業の集中力が減りました。
以前はもっと、こう・・・心身が
ぐぅぅ~っと潜るように集中できたのだけど。
それもこれもきっと寄る年波、
目が見え辛くなっているからだろう!
と理由付けしまして
LEDライト付きルーペを買いました。
これで作業もバッチリさ、ムハハ・・・
▲シンプルなランプの佇まい
▲スイッチオン!ピカッと明るい。
LED特有の青白く目に刺さる光ですが
明るくくっきり。
そしてルーペを覗くと
「ぎゃっ」と叫んでしまうほど良く見える!
何と言いましょうか、別世界な感じです。
今までどれだけ見えていなかったのか。
そして見えていた人にはどう思われていたのか。
なんだか複雑な気持ちになりつつも
金箔の繕いをしました。
でも、ものの30分で頭痛と目の奥の疲れで
ギブアップしてしまったのでした。
ちょっと見えすぎちゃってもう・・・
このルーペを選んだ理由は、ガラスレンズを
交換して倍率を変えられること。
今は2.25倍のレンズなので強いのかもしれません。
1.75倍に替えて、明るい日中にライト無しで
作業して、少しずつ慣れようと思います。
いや、それにしても。
これがあれば作業の幅が広がる予感です。
活用しようと思います。
ヴェネト額縁に古色加工と「なぜ好き?」問題 6月30日
2020年2月フィレンツェ滞在時に
木彫師グスターヴォさんの工房に通い
汗と涙に濡れながら(半分嘘半分本当)
制作しましたヴェネト額縁に
2021年6月になって箔貼りをしました。
ピッカピカにして、ひとまず完成・・・
それから1年、寝室で毎日眺めて過ごし
ようやく諦めがついたと言いますか
向き合う気力が沸いたと言いますか
「ピカはおしまい、古色仕上げしよう」
と思い立ちました。
まずは裏から作業開始です。
裏面は白木のままでしたので
アクリルグアッシュの「生壁色」を塗ります。
この色は被覆力も高く落ち着いた色味で
金箔との相性も良いようで愛用しております。
さて表面です。
まずはスチールウールで磨り出し。
▲磨り出し前。ピカピカ見納め
▲磨り出し後。分りづらいですが
下地に塗った赤褐色のボーロが見えています。
そして褐色のワックスを塗りました。
左~下部はワックス後、上~右はワックス前。
ワックスの効果で凹凸もくっきりしました。
まだちょっと生々しいので
この上にさらに灰色の粉「偽物埃」を
はたき込み磨き上げ、完成です。
やれやれ。
ほんの少し、肩の荷が下りたような気がします。
この額縁を作るにあたって参考にした
オリジナルの額縁が作られた18世紀当時、
額縁職人の方々は金箔をいかに
美しく輝く状態に仕上げるか
(恐らく金箔作業専門職人の仕事)が
重要だったはずです。
薄暗い邸宅や教会の小さな灯りを反射して
揺らめき輝く金が求められたはず。
全世界のいにしえの時代から
エジプトも南米も、中東もインドも中国も、
「金は変色(酸化)せず永遠の輝きを保つ」から
黄金が珍重され、通貨にも発展したのに。
時代は変わって価値観も変わって
「磨り出し汚した金の古色の美しさ」
「あえて輝かない金を好む」
というような感覚も生まれたわけですよね。
考えてみれば、これは贅沢なことです。
「金そのものの純粋な美しさ」が既にあるのにね・・・。
それでもやっぱりわたしは擦り切れた金が好き。
なぜ古色を付けた金が美しいと思うの?
金の一体何が好きなの?
金そのもの?それとも取り巻く文化?
背景や歴史?イメージ?箔作業??
なんだろなー・・・全部、だけども。
恋人に「わたしのどこが好き?」と訊ねられて
結局「全部だよ」などと答えてしまうのって
こんな感じかしら、と思っています。
・・・いや、ちょっと違いますかな。
やれやれ。いやはや。
こんな仕上げはいかがですか 6月27日
市が尾にある古典技法アトリエ
「アトリエLAPIS」の生徒さんが
先日完成させた額縁の色使いが
とても素敵でした。
そのイメージを拝借しまして
わたしは小箱にしてみました。
いつもは石膏を塗り磨いていましたが
今回は桐木地に直接パスティリア
(石膏盛り上げ)装飾を。
額縁には直接パスティリアは
以前から施していましたが
なぜか小箱には初登場です。
▲最近パスティリアの話題を多く
お届けしている気がしますが。
▲面取りをした小箱に直接
石膏を垂らし描きしてレリーフを。
周囲のポチポチが鋲のようになって
ちょっと武具とか馬具とか
そんなイメージにもなりました。
木地なので軽やか、でも男性的な
力強い雰囲気も出てくれたか・・・?
どうにも贔屓目になっておりますが
お気に召して頂けると嬉しいです。
いかがでしょうか。
桐木地にボローニャ石膏で
パスティリア装飾
アクリル絵の具で彩色
外側寸法:77×50×24mm
新旧交代、お別れの儀式を 6月20日
たまに画材店に行ってしまうと
もうウキウキしすぎてしまいます。
あれもこれも手に取ってから
その量と予想支払金額にぎょっとして
諦めつつ半数を元に戻す。
そしていそいそと買うのです。
▲絵具と筆、金属用プライマー
箔の上にも描きやすいに違いなし!
▲新しい筆の証し、キャップ付き
新しい筆があるって本当にしあわせ。
右6本は数百円のお手頃筆で日常使いに。
中央の2本は高い(1800円とか・・・)ので
”ここぞ”という時の頼みの綱用。
左の2本は2020年のフィレンツェ滞在時
ZECCHI(古典技法画材店)で買った
5€くらいだったコリンスキーの筆です。
プライベートブランドだからか
かなりお手頃価格でした。
そしてかなりかなり良い穂先であります。
次回行けたら10本くらい買い貯めようムフ♡
(それはいつだろうか。
その頃はもう少し円がユーロに
強くなってくれますことを願います・・・)
よく言えば物持ちが良い。物に執着する
わたしですので、古い筆はなかなか捨てられず
でも筆立てで呆然と立っているばかりで
もはや活躍の場はないであろう筆たち、
今日お別れすることにしました。
▲ボサボサになるまで働いてくれた筆一族
筆供養をしてくださる神社がどこかに
あったように記憶します。
わたしはわたしで、ひとり密かに
お別れの儀式をいたしました。
うう、寂しいような申し訳ないような。
きっと使命は全うしてくれたはず。
今日までありがとう、さようなら。
さぁ、明日から心機一転
新ピカ筆一家と共に
良いもの作りをいたしましょうぞ。
クッキーの作り方をようやく思い出す。 6月16日
今日のお話はお菓子のクッキーでは
ありませんのです。
最近いただいたご注文額縁の装飾に
パスティリア(石膏盛り上げ)を
入れることにしました。
わたしが勝手に「クッキー」と名付けた
デザインで、なかなか気に入っております。
だいぶ昔に作ったデザインです。
額縁の四隅の角に入れる小さな模様、
昔のクッキーに入っていた模様風・・・
というイメージで名付けました。
さて、下描きをしまして石膏も温めて
いざ!と思ったのですが
「あれ、これってどうやるんだっけ・・・」
と手順が思い出せず。
なんたることだ。
我ながら驚いてしまいました。
▲左のふたつは昔作った
クッキー模様コーナーサンプル
こまかい説明は省きますが
どの部分から開始して
どのように重ねるか、など一応
自分なりの「制作手順」があります。
この「クッキー模様」を作るのが
久しぶりすぎました・・・!
以前につくったコーナーサンプルを
引っ張り出して眺めてみて
そうそう!そうだった~!!
と思い出せて一安心した次第です。
昔のわたし、サンプルを作ってくれて
どうもありがとう・・・
気に入っているならもうすこし頻繁に
小箱等にも練習しておきましょうぜ・・・。
古典技法額縁の作り方見本を作る 6月13日
市が尾にある古典技法アトリエ
Atelier LAPIS では来年春に展覧会を
予定しておりまして、準備が始まりました。
その一環として、わたしが担当しましたのは
古典技法額縁の作り方を簡単にご覧いただける
見本の額縁制作です。
木地はアトリエ主催の筒井先生が
ご準備くださいましたので、わたしは
装飾デザインを考え、下ニカワ塗りから
開始いたしました。
▲下ニカワ塗りの次、石膏塗り終わり
左下から木地→下ニカワ→石膏下地と
手順を追っておりまして、次は
磨いた石膏地、そして装飾に入ります。
▲装飾模様を決めて転写準備
金箔や銀箔を使っていくつかの
装飾方法を見て頂けるようにします。
ザ・古典技法を詰め込もうと思っています。
注いだ愛情は負けない 6月09日
先日彩色が終わった小箱に
ワックスを塗り仕上げをして
ようやく完成いたしました。
イタリアっぽくなったかな・・・
ルネッサンス風に仕上がったかな。
それはさておき。
大変たのしく作ることができました。
この小箱、実際の古い小箱の
写真を見せて頂いて、レプリカと言いますか
真似をして作ってみたものです。
オリジナルは8角形で
表面の彩色も半分ほど剥がれ落ち
それでもとても美しく存在感のある小箱。
インスタグラムで知り合った
イタリアのお医者さん(趣味人)が
「君は本当に小箱が好きなんだねぇ」と
コレクション写真を送って下さったのでした。
その中のひとつに8角形の小箱があり
ひとめぼれ、欲しくてたまらない!
その小箱は4月にフィレンツェの
オークションにかけられ、わたしは
血迷って入札しようかと悩みましたが
すんでのところで思いとどまり・・・
だけど入札くらいしてみても良かった?
と、今頃思い返しています。
▲海の思い出などをいれて。
蓋と身に合印の点をいれてあります。
手に入らないなら作れば良いじゃない?
との勢いで作りはじめたこの小箱は
結果的に「あの8角形の小箱」とは
違うものになったけれど
佇まいや注がれた愛情は
負けていないぞ、と思っています。
桐木地にボローニャ石膏
赤色ボーロに純金箔の水押し
刻印装飾とアクリルグアッシュの彩色
ワックスによるアンティーク仕上げ
外側寸法:77×50×24mm
「許可」が出る日を待ちわびて 6月06日
我が家の近所の書店の本棚には
「地球の歩き方」コーナーがあります。
ほとんどが去年か一昨年のもの。
行く度に確認するけれど
もう随分長い間この様子です。
それも当然と言えば当然なのだけど寂しい。
その中でも
「ローマ」だけ2018~2019年版。
うう~む、人気が無いのかしらローマ。
そんなはずないのだけれどなぁ。
この本棚がすっかり整えられて
2022~2023版がずらりと並ぶ日を楽しみに。
そしてその日が来た暁には、いよいよ
わたしの旅路計画も立てようと思います。
ここが整えば「行っても良い」と
許可をもらえたような、そんな気持ちになります。
フガフガと鼻息荒く待ちわびています。
実は派手好み? 6月02日
引き続きオーソドックス点々小箱です。
点々打ち(刻印)を終えまして
次は彩色です。
卵黄テンペラにするか迷いましたが
今回はアクリルグアッシュで。
▲パレットは愛用のお豆腐空き容器・・・
磨き上げた金箔の上に彩色すれば
テンペラにせよアクリル絵の具にせよ
定着するのは難しくて
経年や使用で、いずれ擦れたりして
彩色は剥がれてしまうのです。
もちろんニスを厚く塗るなどで
定着を強める方法もありますが
経年変化も持ち主だけのオリジナル
として楽しんでいただきたい。
そんな気持ちで描いています。
▲ルネッサンスの写本装飾風に
いや、それにしても。
派手でございますな。
わたし、そんな派手好みでは無い
つもりですけれど、だいたい
「金が好き」などと言っている時点で
地味好みとは到底言えませんね。
キラキラ金ではなくて
すり切れたボロボロ金が好き・・・
これはなんと表現するべきか?
この小箱は暗めのワックスをかけて
もうちょっと落ち着いた色味に
仕上げるつもりです。
内職をしたら寝巻浴衣になる。 5月30日
先日ご紹介しました小箱ふたつ
「kirikami」と「丸三角四角ちらほら五角」は
3月の阪急うめだ本店での催事中
ガサゴソと内職をして考えていた
デザインなのでした。
▲小箱サイズに切った裏紙・・・
ディスプレイの影でこっそり。
ふたつは無事に形になったけれど
右のひとつは・・・なんだか
祖父の寝巻浴衣の模様を思い出し
ちょっと保留であります。
角度の問題でしょうかね。
浴衣になるかならないか、
なんとも微妙なものです。
楽しむ情熱を 5月26日
先日・・・と言ってもひと月以上前ですが
フォトグラファーの知人と話していた時のこと。
わたしが「小箱を発表するからには
もっとブラッシュアップさせなくちゃ。
だけど、ずっと以前に作った小箱を
気に入ってくださる方もいらっしゃるから
不思議だし難しい。」
と言うようなことをお話しました。
そうしたらその人は
「そうですね、ブラッシュアップも大切ですね。
だけど初期の作品から感じる情熱のようなものは
消えてしまうから難しいですよね。」
と仰ったのです。
その時大変に「はっ」とさせられたのでした。
小箱を作りはじめたばかりの頃の自分にあった
ただ好きで楽しいから作る「おおらかさ」と
迷いながら色々な装飾を試す「ひたむきさ」と。
これが知人の言う「情熱のようなもの」とするなら
今のわたしはどうなったかな?と考えました。
以前の小箱を選んでくださる方は
その「情熱のようなもの」を
汲み取ってくださったのでは?
最近作った小箱と違いはあるのだろうか?
自分と対峙してみれば
すっかり減ったように思っていたけれど
案外と実は減ってもおらず、相変わらず
迷いつつも楽しく嬉々として作っているな!
・・・と気づきました。
心の奥にすっかり追いやられていて
自分で感じられなくなっていたんだ。
ブラッシュアップ、洗練させること、
迷いを感じない仕上がりにすることに
気を取られて慌てていました。
さらに洗練した仕上がりを探求しつつ、
これからも「楽しんで作っているのが
感じられますね」と言って頂けるような
小箱と額縁を作りたいと思います。
次なる点々 5月23日
催事の「ひとりお祭り騒ぎ」が終わり
ぼちぼち日常に戻りました。
さて、先日下描きを終えた小箱です。
一時期はまっていた「マイクロ点々」装飾は
ひとまず脇に置きまして(ちょっと飽きた)、
オーソドックスなサイズの点々打ちの
刻印模様を入れることにいたしました。
この点を打つ道具、何と呼ぶのでしょう
印?タガネ?・・・とにかく
この道具は木槌で打って点を入れます。
▲奥に見える円筒形の木槌で打ちます。
尖りすぎると箔を突き抜けますし
鈍くするほど打った点が大きくなります。
サイズが大変に微妙!
好みの点を打つためにはいくつか必要。
▲KANESEI印は特注品・・・ありがたや。
今回のデザインはイタリアルネッサンス時代の
イメージですので、刻印のサイズも
正統派、クラシカルな雰囲気です。
久しぶりに凝り凝りの詰まった小箱を!
と頭の中で完成図を膨らませています。
ありがとうございました 松屋銀座「色のカタチ」 5月19日
松屋銀座「和の座ステージ」で開催しました
催事「色のカタチ」は17日に無事終了いたしました。
連休明けでお忙しい時期、そして
お天気もすぐれない日が続いた中を
お越しくださりありがとうございました。
3月の大阪阪急うめだ本店での催事
そして今回東京の松屋銀座での催事と
ほぼ連続で小箱を発表させて頂きました。
SNSで知り合い、ご来場くださった方々と
まるで古い知り合いのように感覚が通じたとき
とても良い時代だな、とつくづく思いました。
2回の催事を経て、とても励まされ
制作を続ける意欲をいただきました。
そして、大阪催事の後にうすぼんやりと
感じていた諸々の事がだいぶはっきりと
理解できつつあるようです。
1週間と言えど、人前に立つのは想像以上に
ストレスがかかることだと体感した。
「作る能力」と「売る能力」はまったく別、
自作品を販売するのは本当に大変。
だけどお客様にとっては、作った人から
直接買う安心感と喜びは格別であること。
世の中には本当に多種多様な人がいるということ。
わたしが作ったものを、目の前でお金を払って
買ってくださる方がいらっしゃる、
その「現場」を目の当たりにする恐れ多さ。
上に書いたことは「今さらやっと?!」と
呆れられてしまうような内容ですけれども、
頭では分かっていたけれど2度の催事を経験して
ようやく理解した、と言う感想です。
わたしは今まで狭いけれどホクホクした世界で
のんきに満足していましたが
これからはより沢山の方々、
私が知らない広い感覚を持った方々にも
ご覧いただけたら・・・と
そんな気持ちで発表を続けようと思います。
牛歩を自覚しつつマイペースで、でも
とにかく今は前進するべし、でございます。
この度はありがとうございました。
引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
縦か横か問題 5月16日
ただいま絶賛開催中(!)の
銀座松屋「和のステージ」での催事中
つくづく不思議に思ったことがあります。
わたしは長方形の小箱を作るとき、
ほぼ無意識に縦向きでデザインして
完成させることが多い。
(横の場合もたまにはあります。)
一方、どうやら一般的に箱とは
横向きにとらえるのが普通らしい。
この違いは一体?
▲催事の様子。明らかに縦模様以外はなんとなく横向き。
ひとつ考えられるとすれば・・・
わたしにとって額縁も縦長が基本の形。
それは恐らく・・・ですけれども
西洋絵画は縦長の絵の方が多いのでは、
という印象があります。
額縁の写真集等でも横向きの額縁が
並ぶのは見たことがありません。
そういえば本も縦長方向です。
わたしは何となく、縦向きに
慣れているのかもしれません。
なぜ箱を横向きにする人が多いのか。
これは日本人特有なのでしょうか。
単なる好みの差でしょうか??
▲たしかに横向きのほうが安定感はある。
考え出したら気になって気になって
仕方がありません。
もしかしたら建築とか
黄金比と白銀比と関連したり
しなかったり??
と想像ばかり膨らませています。
どっちでも良いでしょ!と言われそう。
だけど、箱を作る身としては
結構切実な疑問なのです。
ふうむ。
松屋銀座7階「和の座ステージ」での
催事「色のカタチ Ito to ki no katachi」
明日17日㈫18時まで開催です。
どうぞお立ち寄りくださいませ。
「kirikami」小箱 5月09日
以前に作った額縁に
kirikami というシリーズがあります。
その模様は、折り紙を畳んで
角をランダムに切り取って
開いたらレース模様になる、という
子供の頃の思い出から作ったデザイン。
シンプルながら気に入っています。
kirikami の模様を小箱にも施しました。
この模様の特徴は、凹みで模様を
表現しているところでしょうか。
ボローニャ石膏を垂らし描きして
模様を表現する「パスティリア」
(石膏盛り上げ)は古典技法で
古くからある代表的装飾法で、
その模様は凸になります。
このkirikami の模様は逆に凹みです。
不思議なことですが、
同じ模様を作ったとしても
凸だとクラシカルに
凹にするとモダンな雰囲気に
なるような気がしています。
艶消しの白、布もライトグレー。
シンプルでクリーンなイメージで。
いかがでしょうか。
この小箱は11日水曜より始まります
松屋銀座7階「和の座ステージ」
での催事に出品いたします。
どうぞお立ち寄りください。
桐木地にボローニャ石膏
凹みで模様装飾、アクリル塗料で彩色
艶消し仕上げ
外側寸法:79×58×38mm
きっと最後まで 5月02日
小箱の配色を考えようかな、と
棚から引っ張り出してきたのは
24色セットの色鉛筆です。
▲今は作られていない「はだいろ」がある。
これ、小学校4年生の時に買ってもらい
それからず~~~~~っと持っています。
そんなに頻繁に使わないので
(子供の頃はケチケチ使っていた)
まだ結構な長さがあります。
▲当時1200円だったようです。消費税も無い時代・・・
そしてオレンジ色のハサミも
これまた小学校低学年のときに
学年全員お揃いで購入したもの。
切れ味はいまも良いのです。
以前お話した、同じく4年生で買ってもらった
学童用彫刻刀といい、これらの物といい
物持ちが良いと言えば聞こえは良し
ケチ臭いとも言えるような!
▲銀色と金色があるのが
24色セットの喜びでした。
ほとんど使っていないけれど!
でもまぁ、それだけ長持ちするような
良い品を与えてもらっていた証しですし
中年になっても使っていられるのは
ある意味幸せなことですので
開き直っております。ハハハ。
きっと作業を続ける最後の日まで
手元に置いている気がしています。
・・・とか言いつつ 4月28日
小箱ばっかり作っている
とかなんとか言って
額縁彫刻もやっぱり開始しました。
あっちばかり
こっちばかり
偏るのは宜しくないでしょう。
何事もバランス良く・・・
へへへ、飽き性の言い訳でした。
今年もこの季節に 4月25日
我が家のモッコウバラもいよいよ
本格的に咲いております。
場所によってはもう満開を過ぎている
モッコウバラも見かけますが
我が家の木はどうもノンビリのようです。
▲我が工房の福の神様モッコウバラ
作業部屋の窓を開けて制作していると
風に乗って花の香りがしてきます。
あれ、モッコウバラってこんなに
香りがあったかな??と思うほど。
黄色という強いイメージとは違う
優しくてほのかな、青みを感じる香りです。
▲おかげ様で今年も福をいただき忙しい毎日
花の香に包まれて作業をするとは
なんという幸せ。
小箱や額縁にこの香りが残れば良いのに
などと思っているうちに時間が過ぎていきます。
▲この後たくさんお水を上げました
鉢植えの小さかった木が、もう塀を超えました。
来年も元気に花を咲かせてください。
問題はある日突然解決するらしい 4月21日
小箱にせよ額縁にせよ模様を決めたら
まずトレーシングペーパーに写します。
そして改めてカーボン紙等で本体に写す
という作業をするのですが。
毎度毎度イライラしてキィィとなって
結局あきらめてハァァとため息をつくのが
トレペ(トレーシングペーパー)は
ボールペンで描けないこと!
その理由は知りませんが
ペン内部にインクは十分存在するのに
インクが出なくなるのです。むむー。
昨日もまた、何度も繰り返してきた
「ありったけのペンで試す」不毛をしつつ
ひとりでキーキーしておりましたが
なぜかそこにあった、そして
なぜか初めて試してみた
パイロットのVコーンペンの青が・・・!
なんと、するすると描けたのでした。
わーお・・・
▲小箱の石膏地に直接描いてバランスを見る。
そして線を決めたらトレペに写す・・・のですが!
インクの乾きが遅くて手に付いちゃう。
もうすこし細く描けるとさらに嬉しい。
調べればもっと早く分かっていたかも。
でもまぁ、とにもかくにも!
小さいけれど鋭い悩みが解決した午後でした。
今はひとまず 4月18日
昨年9月末に、わたしは友人から
「小箱作家」と評された(?)と
お話しましたけれど、最近は本当に
額縁よりも小箱を作る時間が圧倒的に
長くなっております。
その時々で活動内容が変わるのは
以前から同じですので、今のところ
小箱活動が多い、と言うだけではある
のですけれど。
やっぱり額縁から離れているのは
寂しいと言いますか不安もあったりして。
それはさておき。
ブツブツ言いつつも小箱は大好きなのです。
最近いくつか木地作りをした面取り小箱の
極小サイズがひとつ完成しました。
全面赤色ボーロに純金箔、刻印で模様入り
古色仕上げ。
「これぞ古典技法」でございます。
目指すはルネッサンス時代にイタリアで
作られたもの。・・・なんちゃって。
中はモスグリーン、1€コインを置くと
小ささが伝わりますでしょうか。
側面4面にも模様を入れました。
手のひらに乗せて愛でてください。
いかがでしょうか。
去年から言って止まっている目標に
「ネットショップを作る」があります。
夏までには!・・・おそらく。
小箱も額縁もテンペラ画模写も。
レディメイドもオーダーメイドも!
夢ばかり膨らんでおりますが
開店の暁にはぜひご覧ください。
今日は良い日 4月14日
今日、と言いつつ数日前のお話。
小箱の内側は艶消しラッカーで
保護しているのですが
せっかちな性格が災いしまして、
ラッカーが完全に乾く前に
蓋をかぶせてしまって
本体と蓋がくっついて開かない・・・!
そんな小箱が3つばかりありました。
それは冬に起きた「事件」でした。
押しても引いても開かない。
道具を使うと壊れちゃう。
熱するか冷やすか、そもそも
そんな方法では解決しないのか。
開かない小箱はもはや
ただの四角い塊りとなり果てる・・・。
▲上が件の小箱3つ、当然大阪催事にも不参加
く、くやしい。
せっかく作ったのに~!と
思っても後の祭りです。
寝室にずっと飾っておいて
(悔し紛れに)眺めつつも
思い出したように引っ張って
早数か月。
初夏のような陽気の本日午後
ついに開きました!
はー、びっくりしました。
理由は謎です。
この陽気で完全乾燥したのか?
お天気も良いし
小箱3つとも開いたし
今日は良い日でありました。
自分への教訓:ラッカーは
きちんと乾かすべし。うむ。
秘密の小箱の使い方 4月11日
3月末に参加した大阪の阪急うめだ本店の
催事では、はじめて小箱をたくさんの方々に
見て頂く機会になりました。
有り難いことに、わざわざ小箱を見に
お出かけくださった方々もいらっしゃいますが
通りすがりのお客様もたくさんいらっしゃいました。
そうした「偶然に小箱を手に取った」方から
いちばん受けたご質問は
「これ、何を入れるの?」でした。
もちろん何を入れて下さっても御自由なのです。
ジュエリーでも貝殻でも小石でも。
だけど、そうか、箱とは「物を入れるもの」
である限り、用途が必要なんだ。
普通はみんなそう考える。
分かっていたけれど、やっぱりそうなんだ。
わたしが作る小箱の存在目的・・・
小箱の中に何を入れても良いし
何も入れなくても良い。
毎日開け閉めして使うよりも
思い出の品をいれて閉じておくもの。
ひとりで手に取りひっそりと眺めて、
たまに蓋を開けてニンマリとして
また隠しておくもの。
どこか秘密めいた謎の小箱。
極々プライベートな楽しみとして
「ただ持っているだけでも楽しいもの」
として扱って頂けたら嬉しい、と思います。
みちびかれて 4月07日
わたしの宝物のひとつにペンダントがあります。
2001年にユーロに統一されるまで使われた
イタリアの通貨500リラコインのペンダントです。
▲REPUBBULICA ITALIANA イタリア共和国
両親の友達が、わたしが小学生だったころに
プレゼントして下さったものです。
なぜ子供にイタリア硬貨のペンダントを?
それはもはや霧の向こうのお話なのですが。
▲裏面はローマのクイリナーレ(大統領官邸)
とても美しいデザインのコインです。
その後、大学を卒業してイタリアに留学して
しばらくたった後に、突如このペンダントの
存在を思い出したのです。
「あれ、そういえばこのコインは?!」
ずっと箪笥の奥にしまっていた
まさに「あのペンダント」だったのでした。
▲1985年の刻印、点字が入っていることにも感動。
留学当時はまだ通貨リラの時代で
毎日のようにこの500リラコインを使っておりました。
チンクエチェント(500)おおよそ50円の感覚でした。
まさか現役通貨のペンダントを当該国で
身に着けるわけにもいかず。
帰国後はここぞという時のお守りになりました。
「このペンダントはイタリアとわたしを
結びつける何かの暗示か導きだったのだ」と思えて
大切にしております。
わたしの手の中の、小さなイタリアです。
最初から終わりまで続く 4月04日
この小箱は数年前に作ったものです。
ずいぶんと迷いながら作った記憶があって
完成後も釈然とせず、あまり気に入らない。
▲迷いに迷い、大阪催事には出品せず。
そうして最近になって、この小箱を
手に取ってくださった方々から
思いがけずお褒めの言葉を頂戴する機会が
何度もあって
そのお言葉を受け取りながらデヘヘ・・・
などと喜んでいる現金なわたしです。
その逆に「これは!」と思うものが出来ても
期待以下の評価しか頂けないことも
けっこうあるのです。
自分の感覚は当てにならない、だけど
褒めて頂ければ良いってものでは無い。
自己満足であってはならない。
物を作るとは・・・などと今さらながら
ぐるぐると考えております。
きっと「ものを作って売る」人にとって
最初の悩み、そして人生の最後まで
考える内容でしょう。
褒められれば良く見えてくる?
他の人がどう思おうと、自分が良いと
思えるものなら、それで良いのだ。
というものでも無し。
物を作って対価ををいただくとは。
ううむ。
ありがとうございました クチュールジュエリー展2022 3月31日
小箱の初お披露目、阪急うめだ本店での
「クチュールジュエリー展2022」は
3月28日に無事終了を迎えました。
ご多忙の中を会場までお運びくださり
またお買い上げいただきまして
誠にありがとうございました。
▲1週間限定、こんなお店を作りました。
後ろの壁には額縁も。
いままではいわば自己満足で
作り続けてきた小箱を、百貨店の催事で
不特定多数の方々に見て頂くのは
大変得難い経験になりました。
そして「自分が作ったものを対面で売る」
というシンプルな作業も、なんとも
緊張しつつも大変に幸せな経験でした。
▲たまに並べ替えて気分転換したり。
小箱の可能性を感じることができ、
これからは小箱に連れられて
いままでと違う世界に乗り出せそうです。
いやはや。
まだ戸惑うことばかりですが
自分のペースは崩さずに
「好きだから作る」初心を大切に
進む所存です。
額縁も小箱も、わたしが作る物は
わたしの分身。
「自分を大切にしてこそ
良いものを作ることができる」と
この経験を経て、改めて思い返しています。
気分を変えて形を変えて 3月28日
KANESEI の小箱制作の木地箱は
いつも箱義桐箱店さんの小箱に
古典技法の加工をしております。
とても丁寧に仕上げられていて
そのままで美しい小箱なのですが
すこし形の変化を付けたいな、と思い
面取り加工をしてみることにしました。
▲右が面取り加工前、左が加工後
箱板の厚みを考慮して、最大限
削って安全(であろう)なところまで
削ってみたら、なかなか良い感じです。
直線的な精度を出すのが結構難しくて
ハラハラしながらの作業でした。
さて・・・どんなデザインにしようか。
楽しく幸せな悩みが始まります。
朝の嬉しい小包 3月24日
ある月曜日の朝、いつものように
市が尾のアトリエLAPISに着いてみると
わたし宛の小包がありました。
知らない差出人・・・なんだろう?
と開けてみたら
イタリアのトローチがふたつも!
つい「わぁ!」と一声出てしまいました。
▲さっそく開けてひとつは口の中へ!
このトローチについて、昨年秋に
このブログでお話していたものでした。
以前、すこしメールのやり取りをした方が
今もブログを読んでいてくださって
ご家族がお仕事でイタリアへいらした際に
買ってきたからとお裾分けして下さったのです。
花粉症で点鼻薬をつかうと、乾きすぎて
のどの調子もおかしくなるこの時期に
とても嬉しい贈り物でした。
メールのやり取りはもうずいぶん前のこと。
(同封のお手紙を読んで思い出しました。)
その時のことを、そしてブログの内容も
覚えていてくださったのも嬉しいのに
こうして贈り物にしてくださるとは・・・。
それはそれは嬉しい、幸せな朝でした。
このトローチがあれば
イタリアの思い出を蘇らせることができて
もうしばらく、もうしばらく!
行けるまでの我慢ができそうです。
お手元に 3月21日
先日完成しました月桂樹模様の
ハガキサイズ額縁と小箱のセット、
眺めておりましたら一つの案が。
いえ、これは小箱を作りはじめて
少しした頃から考えていたのです。
手元供養に・・・と。
大切な家族、懐かしい人やペット
写真と一緒に形見のものを小箱に入れて
お手元にいかがでしょうか。
イニシャルを入れたり、デザインも
小箱のサイズ、額縁のサイズ、
ご希望に沿って制作いたします。
明後日3月23日から始まります
大阪・阪急うめだ本店での催事
「クチュールジュエリー展 2022」で
こちらふたつも展示販売いたします。
お近くにお出かけの際には
どうぞお立ち寄り下さませ。
出戻り娘たち 3月17日
おととし2020年の12月にあった
「小さい小さい絵」展に出品しました
テンペラ画模写2点は嫁ぎ先(お客様)が
見つからず出戻りまして
我が家でノンキにしております。
がっかりしているわたしの後ろで
家族がぼそりと言いました。
「売れ筋を作れば良いんじゃないのぉ・・・
男の顔より、かわいい天使とか・・・」
まぁ、そうですね。そうかもね。
でもお花は悪くないと思うのだけどなぁ。
▲フィリッポ・リッピ作
「アレッサンドリ祭壇画」より部分模写
黄金背景卵黄テンペラ画
額縁外側寸法:170×170mm
▲アレキサンダー・マーシャル作
「チューリップ」模写
黄金背景卵黄テンペラ画
額縁外側寸法:180×180mm
まぁ、ほら、あと20年くらいしたら
本当の古色がついて
それはそれで「良い感じ」に
経年変化するかもよ?・・・と
自分を慰めております。
でもやっぱり、嫁ぎ先は探してみよう
と思います。
月桂樹の小箱 3月10日
先日ご覧いただいたマイクロ点々の
無事に完成いたしまして、さて次。
お揃いで小箱も(相変わらず小箱・・・)
も作ってみました。
▲額縁とお揃いの月桂樹を線刻して箔。
磨きましょう。
このマイクロ点々技法のときは
どうやら箔は2枚重ねで貼った方が
仕上がりは良いようです。
線刻の凹みはどうしても箔が入りづらく、
点々打ちでも輝きが深くなりますので。
▲箔が2枚重ねだと輝きの深さも2倍
相変わらず点々点々と点打ちいたしまして
前作の額縁と並べてみました。
・・・派手でございますな。
小箱は箔2枚重ね、額縁は1枚だけ。
なんとなく違いを感じて頂けるでしょうか。
2枚の方がヌメッとしているというか。
ゴージャスカップルが誕生しました。
いかがでしょうか。
螺旋の外は 3月07日
何というか、閉塞感なのであります。
きっと多かれ少なかれ皆さんが
感じておられることでしょう。
ニュースを見てはハラハラするばかり。
自分の状況はどうかと言えば・・・
同じところ、狭いところをぐるぐると
右往左往しているだけな気分になって
もう随分になりますが、俯瞰してみれば
同じところな気がしても少しずつ少しずつ
長い螺旋階段を上っていて
見下ろせばそれなりに上に来ているようだ。
でも螺旋階段は厚い壁に囲まれた筒の中で
しょせんは狭い狭い世界。
▲イタリア・オルヴィエートにある
二重らせん階段の井戸 Pozzo di San Patrizio
(wikipedia より)を上っているイメージ
風通しの良い螺旋階段に移動したいな。
外の世界を見渡しながら上りたいな。
わたしにはもっと違う階段もあったな。
でもこの階段を選んだのはわたしなんだな。
だから今日も上るんだな。
(人間だもの。はるを。・・・失礼。)
そんなことを考えております。
わたしは7の人 3月03日
額縁彫刻の下描きをするときは
木地に直接デザインを鉛筆描きして
最終的に決めた線を全体に転写する
と言う方法をとっています。
そうしていざ彫り始めるには
下描きの曲線に合うカーブの彫刻刀を
選び出していくわけですが
それがいつも7番カーブになる、というお話。
無意識に7番カーブを記憶しているのか
単純にわたしが描きやすい曲線が
7番カーブに合っているのか。
▲彫刻刀のカーブは番号順に曲線が深くなります。
1番は平刀、9番はほぼ半円になる感じ。
7番カーブはそこそこ丸いと言いましょうか。
7番シリーズの中で幅がそれぞれあります。
自然に描いた曲線が一定のラインになるのは
手の動きはもちろん、腕の長さから
ひいては身長や性格も関係しそうです。
きっとわたしは「7番カーブの人」なのでしょう。
ラッキー7な訳では無いのです。
数字なら8の方が好きです。
わたしの手持ちの彫刻刀の数は
けっして多くはありません。
そして彫刻刀の種類が多ければ多いほど
彫れるバリエーションが広がります。
色鉛筆の色数が多いと描ける世界が広がるのと同じ。
7番カーブが手に合っているらしい、と
自覚して以来、7番シリーズを揃えています。
でも、彫刻デザインによっては8番カーブや
6番カーブが合う場合も、もちろんあります。
6の人、8の人にもなりたいなぁ。
やっぱりもうちょっと種類を増やしたい・・・と
思う日々です。
ピカをボロに 2月28日
古色仕上げで承ったご注文。
今回はかなり本格的に古色を付けます。
ボロボロにするのであります。
とは言え、まずは一度ピカピカに
凹み部分にも金を入れておく必要かあります。
▲磨いてとにかくキンピカに。
そうして叩いて傷を付けたら
スチールウールで磨り出して金を取り除く。
せっかくきれいに貼って磨いた金を
取ってしまうなんて勿体ない・・・と
思わなくもありませんけれども。
▲粗目のと細目と使い分けます。
L字下は磨って赤い下地が見えている。
そうしてワックスで仕上げたら
やっぱり古色仕上げって良いなぁ!
古いもの(これは新品だけど)が
好きだなぁ、とつくづく思います。
この瞬間に、キンピカに仕上げた
苦労が報われます。
マイクロ点々 2月24日
最近自分の中でヒットしている技法
極小の点打ちで梨地風にする刻印
名付けて「マイクロ点々」
(もう少しマシな名を考え中)で
ハガキサイズの額縁を作っています。
今までは小箱にばかりしていたマイクロ点々
額縁に装飾したらどうだろう、
あまり大きなサイズの額縁には合うまい、
と考えまして、このサイズに落ち着きました。
ボローニャ石膏地に線で模様を刻んでから
ボーロ、金箔を貼ってメノウ磨き後に
ポーセレン用の極細メノウ棒で点を打ちます。
相変わらず目と手が痛くなるし
根気が必要な作業ですけれど
このマイクロ点々技法、楽しいです。
次はどんなものをこのマイクロ点々で装飾しようか
考えるのもまた楽しい。
ウチのヒヨ 2月21日
我が家の庭の片すみに父が
小鳥のための小さな餌台を作りました。
お仏壇に供えたご飯を下げてきて
水でふやかして入れておきます。
以前はスズメが何羽も来て
とても賑やかだった餌台ですが
最近巷で聞く通り、すっかりスズメの姿は
見かけなくなってしまいました。謎。
いま、この台には一羽のヒヨドリが
縄張りにして、ほぼ住んでいます。
すっかりわたしを「餌を出す生き物」と
認識しているようで、朝窓辺に来ては
室内を覗き込んではご飯を待ちます。
ぴよ、なんてぶりっ子(死語)な声で
首をかしげてはご飯を催促しちゃって。
▲「ごはんはやくちょうだい。」目が真剣。
あまりの可愛さに悶えつつ、わたしが
窓を開けて1メートルに近づいても
逃げる気配も無し。
形ばかり「逃げるポーズ」をとって
銀木犀の木に飛び込んでいます。
餌台のご飯が入れられると張り切って
チャカチャカと食べ始めるのです。
▲「よいてんきだな。」・・・ではなくて。
食事中も警戒は怠らず。
それを毎日眺める幸せ。
野鳥を飼うのは禁止されているけれど
このヒヨドリは・・・ほぼ「ウチのヒヨ」
になっております。
▲自分の可愛さを知っているに違いない。
それにしてもこの子
夜はどこで寝ているのかな。
安全な寝床と仲間がありますように。
ボロの前にはピカ 2月17日
今回作ってる額縁は全面彫刻で
最終的に古色仕上げの予定です。
古色付けにもいろんな方法があって
工房や職人によっても千差万別。
それでも共通しているのは
古色加工する前にきっちり仕上げる、
加工はその延長上にある、です。
金箔の古色仕上げも、凹凸すべてに
きちんと金が貼られていないと
美しい古色仕上げにならないのが
辛いところなのでございます。
凹凸の凸は磨り出して箔が無くなるけれど
金箔は貼りやすい。貼りやすいけど
最終的に無くなる。でも貼らねば。
凹凸の凹は金箔がとても貼りづらい。
でも加工後にも残る。だから貼らねば。
貼ってないと取れない。
貼らないと残らない。
そんな訳でして、今日も今日とて
全面に金箔を貼り貼りしております。
勝利は目前 2月10日
古典技法制作の何が辛いって
石膏磨きなのであります。
ニカワを塗った木地に
液状のボローニャ石膏を塗り
乾いたところを磨くのです。
紙やすりでひたすらに磨く。
荒いやすりで形を整えて
細かいやすりで磨き痕を消す・・・
テンペラ支持体の平らな板や
シンプルな額縁ならまだしも
彫刻が全面に入った額縁なんてもう
気が遠くなりそうです。
この石膏磨き作業を左右するのが
石膏液の塗り方です。
均一な厚さで凹凸を少なく塗れば
それだけ磨き作業も減るのでございます!
フィレンツェの額縁師匠マッシモ曰く
「結局一番難しいのは石膏塗りだよ」
でした。さもありなん・・・。
海外ではスプレーで吹き付けるような
大きな工房もあるようで
上手にできればこのスプレー方式が
一番効率が良さそうです。
とは言え設備や場所が必要ですから
わたしには縁遠い方法です。
そんな訳で、わたしは石膏塗りに
命を懸けております。大袈裟ですが。
それくらい石膏磨きをしたくない。
筆選びから始まって、石膏とニカワの
割合、濃度、温度、室温
いかなる筆さばきで塗るか etc・・・
▲塗り終わりがいかにツルンとしているか、
表面張力を味方につけるのがカギ。
すべて自分の感覚で「こんな感じ」
なので説明が難しいのですけれど、
ようやく最近になって「実験」が実を結び
今のところの最適な塗り加減
つまり、塗り終わって乾いたときに
凹凸や気泡が少なく磨く手間が減る塗り加減
というものが見えてきました。
平面と角以外は磨く必要が無い、と言うような。
最初は「いかに磨き作業をしないで済ませるか」
という怠け心から始まった探求ですが
今となってみると、ツルンと塗り上げて
紙やすりで磨かない石膏地の方が
箔を貼り磨き仕上がった時に
「品がある柔らかさ」が表現出来るようです。
もちろん、シャープでビシリとした
仕上がりを求める場合は別です。
ボローニャ石膏との闘いに勝利目前です。
ワハハ!しめしめ・・・してやったり。
闘っているのは一方的にわたしなのです。
石膏からは白い目で見られているような。
でももうわたしは闘いの気分そのもの。
最適を探す実験はまだ続きます。
性格が出る 2 2月07日
我ながら思います。
わたしは何にせよ理由が知りたい、
めんどくさくしつこい性格。
幼いころから両親と出かけるとき
「これからどこへ行くのか、それは
なぜなのか」を教えてもらわないと
「ねぇ、どこ行くの、ねぇ、なんで」
と繰り返し尋ねておりました。
うるさい子ども。
サプライズなんてあったものでは無い。
今現在もお茶の稽古などしておりますと
「ここで左手で茶碗を持つ」など
踊りの振り付けのように決められた動きがあります。
それはなぜ・・・なぜ右手じゃだめなの、
と、いちいち気になって仕方がありません。
先生に「それはなぜですか」と訊ねたら
先生は大層驚かれて「なぜはありません。
決められたとおりにしなさい」と仰います。
結局お稽古後に、先生はため息をつきながら
理由を教えてくださったのでした。
左手なのはその方が動きが少なくてスムーズだから。
お茶の動きにはすべて理由があるのです。
だけど、そんなこと気にする必要はない。
まずは正しく美しい所作で美味しいお茶をたてる。
お客様に気持ちよく過ごして頂く。
それをお稽古するのです。分かっちゃいるけれど。
そんなわたしですので、古典技法の額縁制作で
生徒さん方に手順を説明するときには
同時に理由も説明したいと心がけています。
「木地に石膏を塗る前にニカワ液を塗ります。」
と言われて、ただ漫然とペタペタ塗るより
「なぜなら木地の目留めになるからです。
次の石膏液が必要以上に木に吸い込まれない
ようにする為なのですよ。」
の一言があった方が、塗る目的も理解できて
記憶に残るのではないかな、と思っています。
▲目留めのためにニカワ液を塗る。
自分がいま、何のために何をしているか。
やっぱりいつでも知りたいと思います。
「笑顔は大切」は本当 2月03日
先日、某エレベーターホールで俳優の
吉田鋼太郎さんをお見掛けしました。
向こうから颯爽と、ものすごく素敵な人が
やって来た!と思ったら吉田鋼太郎さん。
わたしはその近くで人を待っていたのですが
夢遊病者のようにフラフラと近づいてしまいました。
エレベーターが到着し、これまた颯爽と
吉田さんが乗りこまれて、ふとわたしを見て
「一緒に乗る?」とジェスチャーしました。
そこで我に返ったわたしは「いえいえ、どうぞ!
どうもすみません」とこれまたジェスチャー返し。
そうしたら!
その時の吉田鋼太郎さんの笑顔が!
わたしを見て微笑んだ素敵さったら!!
目と目が合ったのですぞ!
今思い出しても倒れそうです。
もちろんマスクを付けておられましたが
テレビで見るままの眩しいな笑顔なのでした。
エレベーターのドアが閉まり、呆然と
立ちすくんでしまったわたしです。
▲吉田さんのキャメルのコートの裾には
ピンクの花があしらわれていました・・・。
あの笑顔の威力のすさまじさたるや。
あんなに感じの良い笑顔を知らない人から
向けてもらったことって、あったかしら。
もちろん吉田さんのお仕事柄、普通の人の笑顔の
何倍も輝くのは当然かもしれません。
だけどわたしの様な一般人でも、
知らない人と接するときにも自然な笑顔になる
努力は必要なのだなぁ、とつくづく思った次第です。
笑顔は大事、と言われていたけれど
改めて印象に残る笑顔でした。
性格が出る 1月31日
ご注文いただいた額縁制作の他に
自分のために作りたい額縁も作ります。
本を見ていて「これ作ってみたい!」
と言うこともあれば、木地があって
「この木地を生かすにはどうする?」
という場合もあります。
いま準備しているのは、ずいぶん前に
手に入れた木地です。
▲本を観てデザインを真似してみる。
おおよそこんな感じ・・・おおよそね。
トレーシングペーパーに型紙を起こして
カーボン紙で木地に写すのですが
これは本当に性格が出る作業だと思います。
わたしの場合、配分や間隔も目分量
行き当たりばったり「こんな感じ」です。
写すのもブレブレ、隙間が広かったり狭かったり。
でもいざ制作を開始すれば下描きは目安ですので
彫刻刀のサイズに合わせてアレンジしつつ彫り進めます。
ここからも、わたしの行き当たりばったりな
性格があふれ出していると思われます。
アトリエLAPISの生徒さんの中には
きっちりとデザイン画を起こして
ミリ単位で採寸してから写す方もいれば
海外の額縁彫刻の職人さんなどは
彫刻刀を入れる場所の目安のみ、点などで
入れるだけ、という方も。
要は自分が分かっていれば良いのです。
わたしがいちいち(とは言え適当に)
模様をすべ描き入れるのは、この時点で
なんとなく完成図が見えて楽しいこと、
だけど気が変わって変更しても可能な程度に
きっちり決めすぎない猶予を入れておくこと
そんな感じでやっております。
箱を壊さないでください? 1月27日
相変わらず小箱はガサゴソと
制作しております。
イタリアの友人とメッセージのやり取りをして
突然思い出したフレーズがありました。
「Non mi rompere le scatole.」直訳すると
「わたしに(複数の)箱を壊さないで。」
イタリア語で箱は scatola(スカートラ)
と言います。複数形で scatole(スカートレ)。
わたしに箱を壊す・・・?日本語では
意味不明ですが、イタリア語では
「わたしをうんざりさせないでよ」と
言いたいようなときに使います。
(わたしの記憶・感覚ですので違うかも??)
▲この箱を壊されたら・・・泣きます。
こうしたフレーズは学校で習うのではなく
日々の生活の中で聞いて覚えた記憶があります。
たぶん、額縁師匠のパオラも言っていました、
「んも~!いい加減にしてよ!」なんて意味で。
(わたしが言われた訳ではありませんよ・・・)
ちなみに
「Che rompere le palle」も同じような意味。
なんちゅーこっちゃ!やってらんねー!
と言うような感じです。
箱(scatole)が違う単語に変わりましたが
palle は「玉」(複数形)つまり
男性の大切な部分を指す言葉・・・
「『あそこ』を壊す」なんと恐ろしい!
スラングでございましょうね。ハハハ。
老若男女が普通に使っていました。
▲ようやく1面終わり、あと4面・・・
それにしても、うんざりだよ!のフレーズに
なぜ「箱」という単語が出てくるのか?
箱を作りながら「箱を壊す」について考えております。
世界共通木地問題 1月24日
インスタグラムで知り合った
アメリカの画家K君という青年が
以前からわたしの額縁を気に入って
どうやって作るのか?など
メッセージで尋ねてくれています。
(恐らく20代、既に画家として活躍中)
金箔の扱いなどを知りたいというので
アメリカで箔技術を教えている人
(この方もまたインスタのみの知人)を
紹介したりしていました。
先日K君からまたメッセージで質問が。
「この君の額縁(写真添付)みたいなの
作りたいんだけど、木地はどうやって
手に入れたら良いの?自分で作ってるの??」
(英語ですので意訳ですが、こんな雰囲気)
そうなのです。
額縁を作ろうと思ってまず最初の問題は
「木地をどうするか」なのです。
フィレンツェの額縁師匠パオラとマッシモも
留学の終わりに話してくれたことは
「君が日本に帰ってから大切なことは
まずは良い木地を見つけること。
木地工房を探しなさい。」なのでした。
老舗の額縁工房は自社工場がありますし
大きなメーカーでは完成した棹
(モールディング。切って繋げると
額縁になるような装飾加工済みの棹)を
販売するところがほとんどです。
わたしは幸いにも白木地の棹を販売している
瀬尾製額所さんや、特殊な木地を作ってくれる
千洲額縁さんとのご縁があって今に至ります。
でも、パオラは一昨年にも
「最近は良い木地が手に入らなくなってきた」
と言っていましたし、K君のアメリカでも
思い立ってすぐ入手と言う話でもなさそうです。
額縁も大量生産型と高級工芸品型と二極化が進み、
木材に関しては環境保護などの観点から、
今後また変化していくかもしれません。
▲ハガキサイズの木地。これくらいは自作します。
右上のは千洲額縁の木地サンプル。
以前はわたしも大きな木地や凝った木地を
自作していたことがありました。
ですが最近はプロにお願いしています。
それはやはり、木地の完成度が
額縁の最終完成度を左右するから。
木地の段階での小さなズレや揺れ、隙間を
「まぁこれくらいなら良いか」と妥協して、
箔を貼って磨く段階になると
致命的になることが多々あるのです。
印象がどうしても「手作り感」溢れてしまう。
その温かみや人間味(よく言えば)を
良しとするのはそれぞれの感性ですが、
わたしには「お金と交換できるもの」
とは思えなくなったのでした。
それくらい、木地は大切なものです。
瀬尾製額所、千洲額縁の皆様には大変
お世話になり、感謝しております。
長々つらつらと書いてしまいました。
それにしてもK君、インスタの
フォロワーは2600人もいますし
ギャラリーの知人もいらっしゃるでしょう。
アメリカにも古典技法額縁工房はあります。
なぜ日本人のわたしに尋ねてくれるのか。
わたしは投稿には英語を使っておりませんのに。
嬉しいような不思議なような気持ちです。
▲そして角を丸くしてみたり。これくらいは自分でします。
ちなみにK君は、わたしのことを
同世代の青年と思い込んでいる
節があります・・・。
楽しいのでこのまま訂正しないことにします。
油断大敵 1月17日
久しぶりに寝込みました。
火曜の未明に胃痛で目が覚め
悩みつつも予定をキャンセルしたところ
午前中から38度台の発熱です。
まさかのまさかコロナではあるまい、
これはあれだな、前にも同じことがあったなと
解熱剤とブスコパンを飲みました。
季節の流行病、感染性胃腸炎でございましょう。
(自己診断ですが!)
平熱が高いので、少々の熱はまぁ
ボンヤリする程度なのですけれど
ギギギィィとひねりつぶすような
胃の痛みで疲れました。
翌々日木曜は事務作業など再開しまして
一安心といったところ。
それにしても今回の感染性胃腸炎って
(繰り返しますが自己診断)ウイルスが
経口か接触で体内に入り感染するわけでして
(気持ち悪いことこの上ない)
新型コロナと同じウイルス性感染症・・・
今回はたまたま胃腸炎のウイルスだったから
まだ良かったものの
新型コロナだったらと考えると
ぞっとすると同時に、緩んでいた
自分がどこかにいたのに気付きます。
こうして知らないうちに
自分の身体にウイルスを入れてしまう。
オミクロン感染だって明日は我が身の
今日この頃、気を引き締めます。
皆さまもどうぞ引き続きご自愛ください。
オーナメントの飾りもの(名称不明) 1月13日
エポキシパテで型抜きしたオーナメント、
蚤の市で買ったヨーロッパのアンティークや
デッドストックから型を作りました。
気まぐれに色を塗ってみたりして
それをちょっとした飾りもの(何と呼ぶか
分からない・・・ストラップ?チャーム?)を
作ってみました。
手元にあったシルクのリボンをつけて
裏にはフェルトも貼り付けました。
家族に見せたら「かわいいけど・・・
どうやって使うの、これぇ・・・」と
言われましたが、そうですなぁ。
キーホルダーには強度がありませんから
クリスマスツリーのオーナメントとか
(遅い。来年のクリスマスに・・・!)
プレゼントのリボンの代わりに、とか。
子供のころ、サンリオで何か買ってもらうと
可愛らしい包みに小さなオマケを
シールで貼ってくれていたことを思い出します。
ものすごく嬉しくてドキドキワクワクしました。
それにしても、相変わらずと言いますか
ちょっと色使いが暗いですかね?
これがあれば何とかなる。 1月06日
わたしの額縁制作での重要物と言えば
型紙がそのうちのひとつです。
以前に作った額縁をもう一度作るとき
型紙があれば再現もできます。
▲2022年最初の制作はこちら。
右にある「hori-makuha」を新たに作ります。
もちろん以前の型紙を応用して。
万が一、作業部屋が火事になっちゃったり
した場合には(想像するだに恐ろしいけれど)
完成している額縁より、彫刻刀や箔道具より
この型紙を入れたファイルを抱えて
逃げ出すべし・・・と思っています。
これさえあれば、なんとか立ち直れるつもりです。
もうやめよう 1月03日
改めまして
新年あけましておめでとうございます。
久しぶりに本格的に寒いお正月
どのようにお過ごしですか。
ようやくご家族と再会なさった方
お仕事やお家の事情でお正月どころでは
なかったよ・・・という方、それぞれでしょうか。
我が家はいろいろとあった12月ですが
どうにかこうにかお正月に辿りつきました。
▲今年のお節は大皿に盛りました。
品数は減ったけれど、とにかく
体裁を保つ程度のお節料理を作って
元旦は穏やかに家族そろって迎えました。
▲変り映えしない元旦風景ですが
この変化の無さが穏やかな幸せの証しです。
迷いに迷った2022年の抱負・・・
いま唐突に思いついた「身軽になろう」
で進もうと思います。
物理的な断捨離とか片付けはもちろん
精神的に「執着をなくす」とか
「むやみにこだわったり考え込んだりしない」
「小さなことをいちいち気にしない」
がわたしに必要なのでは無いかな、と思います。
「しない・やめる」方向です。
2021年の抱負「逃げ癖を治す」はひとまず
山は越えたのですが、逃げる理由って
わたしの場合「考えすぎ・気にしすぎ」から
ひとりで勝手に一杯一杯になって逃げだすパターン。
なので、今年はその原因を減らそう
という魂胆でございます。
ああどうか、前進できますように!
あけましておめでとうございます 1月01日
旧年中は大変ありがとうございました。
新春を迎え皆様のご多幸をお祈りいたします。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
令和4年 元旦 KANESEI
抱負は辛いよ 12月27日
今年2021年1月4日のブログで
「今年の抱負は『逃げ癖を治す』
2020年に授かった
『驚くような嬉しいこと』を
諦めないで逃げ出さないで大切にして
過ごしたいと思っております。」
などと書いていたのでした。
そうして2021年の暮を迎えて
どうだったのかい?と自問しました。
そうですね、ぼちぼち合格点だったと
言っても許してもらえるでしょう・・・
誰に許されるって?それは自分に、です。
果敢に前向きに追う、は無理でしたし
諦める3秒前くらいまで追い込まれました。
でも今までなら後ろを向いて逃げ出して
断ち切っていたような場面でも、
唸りながら耐えられたと思っています。
このブログに書いてしまった以上
守るしかない、という心境になったのも
成功の一因かもしれません。
何から逃げなかったか・・・?
いや、お話すると大した内容では
ありません。お恥ずかしいようなこと。
こういう抱負は自分との約束ですからね、
何にせよ「負けなかった、約束は守れた」
そこに尽きます。
2022年のお正月にも抱負を決めるのか
自分自身に戦々恐々なのですが
ここまで来たらもう一歩進めて
「逃げ癖が直ったなら、次は攻める」
で行くべきか考えてみる所存です・・・。
いや、でも。うう・・・
抱負を持つってしんどいですね。
でも、だから良いのでしょうね。